リビングに関する情報をまとめています。
このページでは「そもそも、なぜリビングにダイニングやキッチンまで抱き合わせで一部屋に括られてしまうのか」あたりのことをお話ししたいと思います。
LDKの部屋分け・間取り設計の際に気をつけたいこと

LDKの基本的な知識を簡単に説明しながら、「じゃあLDKはどうしたらいいんだ」というあたりのことについて考えていきたいと思います。
LDKそれぞれの役割を整理する
まずは「LDKってなんだ」というあたりから掘り下げてみようと思います。
リビングの目的ってなんだ?
リビング(Living Room)は「居間」です。居間の目的は「くつろぎ」で、居住者がリラックスして過ごせるような空間を指しています。
日本古来の「居間」や「茶の間」は、食事を取るスペースや台所と隣接していたことから、狭義の居間は「LDK」に近い感覚である。
リビングはくつろぎ
リビングの目的は「くつろぎ」と言えるので、これは逆に定義がしづらい。くつろげるリビングは人それぞれなので、快適なリビングを作るハードルは高い。あとで解説します。
ダイニングの目的
ダイニング(Dining Room)は「食事室・食堂」のこと。食事を食べる目的の部屋で、テーブルと椅子のセットが置かれていることが多く、日本の一般家庭で「ダイニング」だけが独立していることは珍しい。
ダイニングは食事の機能面を支える
ダイニングはリビングよりもわかりやすく、「食事を取るところ」になります。食事を取るための道具などを集合させておき、基本的には
ただ、日本のかつての居間のように「ダイニング」と「リビング」の役割が共存する可能性は十分に考えられます。スペースで考えれば、1つの空間で兼務できる方が合理的だと言えます。ただ、役割を分けた方が物品が整理されやすく、生活動線も計算しやすいので利便性としては分けた方がいい。

ダイニングとリビングが一緒だと、作業・勉強などの工程と食事の準備がバッティングすると、どちらかを諦めないといけなくなる。
キッチンの目的
キッチン(Kitchen)は「台所」です。食事を準備する機能性の高い部屋になり、「流し台」や「加熱調理」、「換気」、「作業台」、「収納」などを全て同室に配置することになる。
キッチンは独立が理想
現代社会において、居間の中にキッチン用途までを詰め込むことはほとんどないと思いますが、生活の中でも「調理」の機能はやや特殊です。比較的相性の良い「ダイニング」部分と連結・融合することは十分に考えられますが、あくまでも連続性にとどまります。

キッチンで調理はするけど、ご飯は食べないのが基本。いや、作りながら食べることはあるけども、部屋の機能としては分かれていた方がいい。

ただ、調理スペースとしてダイニングテーブルを利用するためにキッチンとの連続性を持たせて広く使うのはアリだともいます。完全に一体、というわけにはいかないけれど。
囲炉裏のようなイメージで、ダイニングの真ん中にコンロがあったら楽しいような気がしなくもないけど、卓上IHクッキングヒーターなどを臨時で起用するくらい。加熱調理は居住空間とは共存しにくいと思います。
簡単に言えば、「キッチン」と「ダイニング」は相性がいいけど、「リビング」と「キッチン」は相性が良くない。LDKで一括りにしやすいけど、部屋の機能性について損なわれないように配置することが大事だと思います。
キッチンのレイアウト
- I型
- 2列型
- L型
- U型
- アイランド型
- ペニンシュラ型
間取りの際にはキッチンのレイアウトはかなり重要なのですが、リビングに関与する場合は、根本的に「同室」にするか「独立」させるかがポイントになる。折衷案として「半独立」と言える対面式が人気と言えそう。
リビングとダイニング、キッチンを機能的に分ける方法

目的としては明確な「食事」「料理」の機能を持つDK部分と、「リラックス」などというよくわからない要素だけで構成されているL部分について、どうやって分けるか、あるいは部分的に融合させるか、というような話をしていきます。
キッチンとダイニングは分けづらい
私の中では、「ご飯を持って移動する」のは手間だと思っています。動線としては、食事と食事の片付けはなるべくセットにして、食事が終わったらそのまま各々自分で洗い物ができる形にしておかないと、洗い物、絶対に溜まります。ここの動線はちぎりたくない。
ダイニングとリビングが一緒だと、食事を食べたらそのままだらけてしまいがちですし、意外とリビングは離しても大丈夫だと思います。
以前は「大きなテレビを置いて、ダイニングでのテレビの閲覧」なんかも兼用していたと思いますが、今、テレビはそれほど高くないですし、「みんなで一緒に同じテレビを見る」ということも時代にそぐわなくなってきました。テレビが共通の話題になる、という意見もありますが、根本的にテレビしか話題がないのも問題ですし。

そうなってくると、じゃあ「リビングって何をする空間なんだ?」から考え直さないといけないですね。子供部屋、ワークスペースの役割が求められる中で、生活空間としてのリビングの機能性とは。
明確な目的を持つDKと、よくわからないLの存在
LDKと一括りにされますが、基本的には「調理」と「食事」は機能面として突出しており、リビングの役割だけは別個で考える必要があります。
趣味が料理の場合
例えば、例外的な考え方としては、「料理が趣味」の場合。料理が趣味でも、キッチンを充実させるために十分なスペースがあれば特に考えることもないのですが、「料理が趣味だけど、余分にスペースを作ることはできない」という命題があるわけです。
この場合、ダイニングとキッチンの一部の機能を融合させることで、多少のスペースを共有することができます。わかりやすく言えば、「調理台」と「ダイニングテーブル」は一緒でもいい、みたいな話。調理スペースと兼用になるので、キッチンは開放式、かつ2列型かL字型のキッチンの背面にダイニング+調理台のような形になる。
これをやると、ダイニング+キッチンで4〜6畳くらいのスペースを取るが、LDK合計で12畳(リビング部分が6〜8畳)の狭めの部屋になっても「料理」に関しては開放感を持てる。
ただ、キッチンとダイニングの境界がなくなるし、リビングとDK部分の境界はそもそも曖昧なので、間取り面で少し工夫して視線を逸らすか、衝立・観葉植物のようなもので区切りをつけたくなるところではある。
リビングを「居間」に進化・退化させる
ダイニングとリビングの役割が共存できることは、日本人が古来からやってのけたことなのでできないことはないのは体験的に知っていると思います。このデメリットは、「食事」の時間と「くつろぎ」の時間が重なり合ってしまうので、「だらけがち」の生活スタイルになること。
この場合は、勉強や仕事などの役割を別の部屋に逃す必要性が出てくる。書斎・子供部屋が必要になると言ってもいい。ダイニングに関しては「食事時間」で区切りがつくけど、定義のない「くつろぎ」に関しては時間の境目が曖昧になる。リビングで仕事・勉強はほとんどできないのは、この「メリハリ」が聞かない構造にある。
子供部屋でうまく勉強ができない、というのは「勉強への集中の仕方がわからないから」と言えます。これが大人になると、在宅での仕事も案外できないことが多いので、子供のうちから「自分で一定時間作業に集中する方法」を身につけるのは大事。この習慣は親と一緒にいる「リビング学習」の方が捗る。

集中できる環境は、「遊び」に対しても一緒で、簡単に言えば「怠ける」ことに集中してしまう環境とも言えます。リビング学習は「一定時間」を集中して、親に作業内容を報告する一連の流れがスムーズになるのでいいんですよね。
リビングとダイニングの機能を一緒にすることは、部屋の構造上は「進化」とも言えますが、人間を自堕落にさせる「退化」につながる可能性がある、というお話しでした。
結論としては「くつろぎのリビング」はいらない
先に極論で解説してしまうと、「リビング」はなくてもいいです。

リビングがなくても「リビング的な要素=だらける場所」は人間の心理(サボりぐせ脳)が自然とみつけてくれます。ダイニングでテレビを見るようになるか、寝室で寝転んでゲームするかに変化するだけです。
家族の時間は意図的に作る
ただ、これは家族個々が自分の心の舵取りで動き出すので、構造的に「家族の動線が交わる部分」が減ってしまいます。食事を定時で家族全員で撮る場合は一定時間を家族で過ごせますが、リビングがないと「食事終了と同時に家族解散」になって、あまりにも「目的ありきの家の構造」になってしまいます。

両親が適度にだらけて過ごしている姿を見るのは、子供にとっては安心できることでもあるんだよね。

だらけることを学ぶという意味ではあまり良くないかもしれないけど、「大人も休む」は子供のうちから知っておいてほしいよね。
個人的な意見としては、子供に「親が仕事をしている・勉強している姿」を見せることは有効だと思うので、子供の生活動線と交わるところに作業スペースがあってもいいのかな、とは思っています。思っていますけど、子供がテレビ見ていると、ついつい親の視線も奪われてしまうのは罠。
共通の話題を生み出すリビングへ
つまり、「家族としての機能」を維持するためにリビングは重要だと言ってもいいかもしれません。個々のパーソナルな領域は確保しつつ、「勉強」「作業」「家事」「憩い」のような機能性はLDKの中に適切に配分することが大事とも言えます。

昔は自分の部屋にテレビとゲームがある友達の家が羨ましかったけど、居間でゲームする環境じゃないと自分は勉強できなかったと思うので、自然と「生活とルール」を身につけることができたのはよかったよね。

スマホのルール作りでも、「使用するのはリビングだけ」は大切かも。無闇に制限はしないけど、透明性を確保することは大事。

機能を配分したLDKの形
「リラックス」「憩い」が実際にはなんなのか因数分解して、改めてリビングをどう設計するのかを考えていきたいと思います。
リビングの「リラックス」構成要素
- ゲーム
- テレビ視聴
- 映画・動画視聴
- 音楽視聴
- 読書
- (軽めの)フィットネス
- 談話
- おもちゃ遊び
- 子どもの写真・動画鑑賞会
- お遊戯・習い事の練習
これらを家族が個別に行いたいなら、別個に専用の部屋を用意し、家族共有の時間としたい時には、必要な道具などをリビングに置く必要があります。

雑多なものが集合しやすいリビングは、収納が大事ということですね。
機能性の強いリビングで行う行動
ここも、別個に専門の機能(サンルームで服を片付けるなど)を分配することで、リビングの役割を減らすことはできます。逆に、リビングに作業動線を集合させることで(ごちゃつくけど)リビングである程度の家事が完結する家、にすることもできます。
個人的には、子どもの「保育園」「学校」の情報が入りにくいので、子供が自分で予定を管理できないうちは、リビングに学校・保育園関連の道具が集結した方が目に留まりやすい。動線はリビングを通すようにしたい。
我が家は乳児期まで「リビング」で全ての寝食をやり切ったけど、生活動線が集約させやすいのもリビングの特徴。キッチンもあるので夫婦でお互いの作業内容が把握しやすい。逆に、リビングではリラックスできないので「どうしても1日寝たい」という日は寝室が避難所になったりしていました。

リビングは「なんでも部屋」になりやすいからこそ、対応できるスペースや「収納」を確保しておくことが大事、と言えそうですね。
できればリビングから排除したい家事
- 洗濯物干し
- 調理
- アイロンがけ
- 仕事
- 勉強
少し矛盾しますが、本来的に言えば「仕事」や「勉強」は、やると決めた時にやれるように準備が不要な専用の部屋があった方がいいです。机に座れば勉強・作業ができる、くらいのスペースで、作業自体に連続性を持たせられるといい。

ですが、これはあくまでも「勉強・仕事が習慣化されている・コントロールできる」方の場合。優先順位を勉強中の子供は親が手伝いやすい環境にいた方がいいですね。
洗濯関連は、「湿度」などの影響もあるので生活スペースからは切り離した方がいい。あと家事としては溜め込むと面倒なので、リビングに持ち込まずに完結する動線を配備して「洗濯→干す→アイロン→収納」までできるのが理想。
家族を家事に巻き込む場合は、逆に生活動線の中に取り入れた方がいいですけどね。「帰宅→着替え→洗濯→片付け→勉強」みたいな流れを作った方が頭の処理が楽できる。逆に、リビングまで全て持ち込んで「後でやる」は、絶対にやらない。

リビングを広くするメリット・デメリット

結局のところ、生活動線をつなげる目的もあるが、DKとLを一体化させるのは「少しでも広く見せたいから」というのがあると思います。
この「広いリビングに対する過剰なまでの憧れ」と現実とのギャップあたりの話をしていきます。
最低限の機能は担保する
LDKを一括りにするのは、リビング・ダイニングを少しでも広く感じるためだと思います。利便性もあるとは思いますが。
しかし、最低限、ダイニング・キッチンの広さを確保して、家事や作業を少しでもやりやすくしておくことが大切だと思います。
リビングはなくてもなんとかなるが、キッチン・ダイニングは生活の質に関わる
これ。
リビングの適切な広さとは
リビングの広さについては、別記事にまとめました。ただ、まとめた記事の方がとっ散らかってわかりづらいので、簡単な目安を書いておきます。
家事・作業の目的を畳数に換算する
LDKの構造の話でも書きましたが、結局のところ、「やること」によって必要な畳数を考えて、作業目的ごとに「どれとどれはスペースとして共存・融合できるのか」を考えます。面倒ですね。
くつろげるソファセットは
3人がけソファとテーブルを置くと、大体4畳くらいのスペースになります。ここにテレビ台も置くことを想定すると、6畳スペースがソファとテレビセットを構築しやすい空間だと言えます。
ただ、「ソファに座ったひとの視線を遮らない」ことも考えて、ソファの背面にも空間を作る場合はさらにスペースが必要です。人が苦痛なく通れる余裕が60cmくらいだとすれば、テレビとの距離を短くするか、さらに2畳ほどのスペースを取り入れる必要があります。つまり、合計8〜10畳。こうなると、なかなか立派なリビングスペース。
家族四人のダイニングセットは
ダイニングセット自体は、四人がけの場合はテーブルサイズは120cm×80cmくらいで「手狭に食事ができる」くらい。調味料セットや内服薬などテーブルに常駐させたいものがあれば、必要分だけのばす必要があります。あとはゆとりに関しては、実際にインテリア関連のショップに行ってみるのが一番かと。
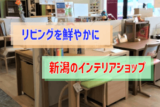
畳数としては、最低限2.5畳くらいのスペースを確保しておき、あとは周辺に簡単な収納や家電などを設置することを想定して広さを決められるといいと思います。
リビングとダイニングが隣り合う場合、空間的な余裕としては60cmほどスペースを空けたいところ。ダイニングテーブルにプラス2畳くらいを考えておくといいと思います。
つまり、ダイニング部分は大体4畳から6畳と言ったところです。4畳は体感としては狭いけど、慣れると暮らせる。ダイニング独立で4畳はかなり狭く感じるので、リビングなどの空間と続けた方がいい。
一般的なキッチンサイズは
システムキッチンの一般的な規格サイズが以下の通り。
- 2,100mm
- 2,400mm
- 2,550mm
間取りによりますが、システムキッチンをベースにキッチンの広さを考えると、ある程度の動線の自由が確保できる通路も含めて、4畳から6畳くらいとなります。6畳のキッチンは結構広く感じます。
LDKの最適畳数は
最適な畳数は人それぞれですが、「最低限必要な畳数」と考えると機能部分だけで12畳、機能以上に活動することを考えると14畳が最低限のラインと考えました。

我が家は16畳くらいで「広いとは言えないけど機能面での不便はない」と言ったところです。1階部分にもDKがありますが、ここは12畳なので狭いけど、庭や続き間にして開放させるとちょうど良くなるかな、という感じ。
冷暖房の効率は悪くなるのか
リビングを広くすると「冷暖房の効率が悪くなる」と考えがちです。私もそう考えていました。
答えとしては「悪くなる可能性は高い」のですが、家の断熱性能に依存するので一概には言えません。ただ、断熱を頑張っていない家だと「寒い」「暑い」と感じる瞬間は増えると思います。
ただ、昨今の新築で、エネルギー効率の高い基準を満たす家づくりをしていればほとんど心配することはないかと。天窓や吹き抜けのような「失敗リスクのある構造」の場合は注意が必要ですが、普通の間取りっていうのは、それなりに合理性のある形になっているので、大きな失敗もないのです。

天窓や吹き抜けは憧れますけどね。心理的高揚感に対しての家の構造としてのデメリットで採算取れなく感じます。
断熱・気密との兼ね合い
広いリビングは憧れますが、そもそも、なぜこれまでの日本は広いリビングを取り入れてこなかったのか。
日本が四季に対応できなくなってきている
日本の四季は比較的過ごしやすいが寒暖差が大きいので、季節によって過ごし方を変える必要があったわけです。夏は家中の通気をよくするために襖・障子などを開放して風通しをよくする。冬は小さく区切った部屋を暖めて狭い空間で暖をとる。四季に合わせて生活の仕方を工夫できる仕組みを日本家屋は取り入れていたわけです。
日本の間取りは、なんやかんや日本家屋の原型を保って大きな部屋も細かく区切れるように設置しがちです。日本の気候は日本家屋の誕生からものすごく大きく変動したわけではないのですが、局所的にはヒートアイランドで熱量を溜め込みやすかったり、全体的にも温暖化の影響で気温は高まってきています。また、日本家屋の形だけを取り入れて、実際には家の性能が高まったことで、熱がこもりやすい空間ができやすくなったとも考えられます。

家電も家中に設置されているから、この家電たちが熱の発生源となっていて、夏がより暑く感じるようになったひとつの要因とも言えるよね。昔の夏と、今の夏は、やっぱり違うということ。外気温だけで判断しちゃダメだね。
話を戻すと、リビングに関しても、「これまでと同じ」ではなく、これからの変化に対応した間取りを考える必要があります。広いリビングは果たして合理的なのか。
空調の機能がいいので「その部屋」は案外暖かい。
空調・暖房・冷房家電の機能は高まっているので、「広いリビング」にしてもほとんどの家では「寒い」と感じる瞬間は少なくなってきていると思います。

我が家も「新潟の冬はリビングはエアコンのズバ暖だけで乗り切った」経験はありますが、やっぱり温水ルームヒーターなどの熱源があった方が快適ですね。



スマートホーム化すれば、「朝のリビングが暖まるまでがつらい」なんてこともなくなります。温度が一定以上に下がったら暖房がつくように設定するだけですからね。

ただ、この暖房効率を高めるためには、やはり断熱性・気密性について考える必要があります。

断熱は部屋ではなく「家全体」の性能であること
まず、断熱についてはリビングというよりは家全体の性能になります。家全体の断熱の総合値で、熱を逃しやすいか熱を逃しにくくするかが決まります。
熱の移動が小さくなるほど、家全体が外気との温度変化に強くなり、節電効果は高まります。また、家全体が一定温度を保てるようになることで、脱衣所・トイレでのヒートショックなどの危険性が低くなります。
リビングだけ断熱性能を高める、という考え方もなくはないと思いますが、昨今は広いリビングにするために必要以上に壁は設けないことが増えています。断熱材は壁に仕込むものですから、リビングを囲むように断熱材を敷き詰めること自体は可能ですが、家の中に逃げる熱に関しては先ほども書いた「ヒートショック」の対応にもなるので、そこまで神経質になる必要はないと思います。

私の実家は建て付けが悪くて、窓を閉めても隙間が見えるくらいだったから、冬もガンガン隙間風が入ってきていましたけどね。案外、生きていけるもんだよね。家の中に暖気・冷気が逃げるくらい、問題ないよね。
リビングは機能を詰め込むほど「暑く」なりやすい
リビングは部屋の役割として広く間取りがとられます。
キッチン・ダイニングを同室にするかどうかは部屋の間取りによりますが、この「キッチン」と「ダイニング」は、熱源になったり、湿度を高めるものが多かったりして、室内環境としては変動させやすい要因になりがち。
これらの機能性の高い部屋と同室となることで、居心地を求めたはずのリビングが「蒸し暑い」空間になりがち。
もともと、日本は湿度が高めなので夏は不快な「暑さ」との戦いになります。
LDKは開放感がありますが、水回りと熱源を同室に置くことになるので、空調を利用することが前提となる部屋の構造となる上に、空気の流れも計画的に作り出さないと上手く排熱できずに空調の効率が落ちてしまう可能性があります。
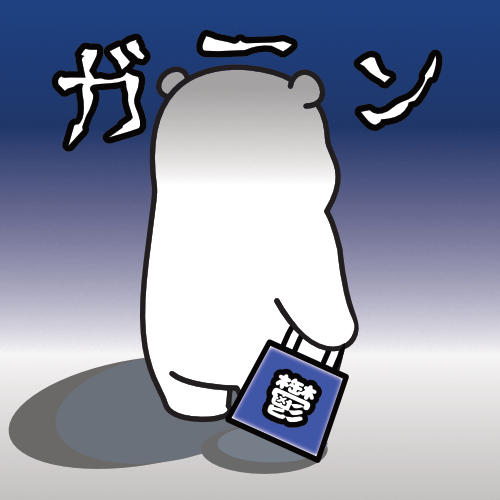
風通しさえ良くしておけば、割と過ごせる気候の時でも、新しい家に引っ越してから熱がリビングにこもるようになって電気代が異様にかかるようになったよね。
というわけで、部屋の換気も意識した構造にすることで、室温を上手に保ち、心地よい風が通るリビングにしていくことも大事ということですね。
リビング間取りで後悔したこと
我が家でのリビングに関する後悔したことをまとめておきます。何かの参考になさってください。
障子では明るすぎた話
少し書きましたが、我が家はリビングで寝たりしていました。ソファもあって案外眠れます。
ただ、昼寝の環境としては、やはりリビングの採光が問題になります。我が家、障子なので適度にあかりを取り込むのはいいのですが、昼寝の時には明るすぎるし、この調整ができない構造にしてしまったことには後悔があってもいいような気はします。

とはいえ、障子はカーテンやブラインドなどに比べると圧倒的に「スッキリ」して見えるので、お気に入りポイントなんですけどね。

2階キッチンに冷蔵庫が上がらない
直接、リビングの話ではないのですが、2階リビングにした話として。

2階にLDKを設置する場合、階段の幅を考えないと「冷蔵庫」などの大型家電の搬入ができない、ということがあります。

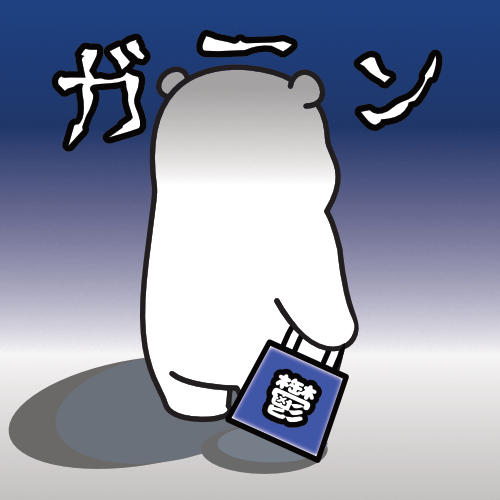
計画段階で、冷蔵庫のサイズの話もしていたのに、実際には大型冷蔵庫のサイズは搬入できないという話になって、ハウスメーカーのことは嫌いになったよね。いや、自分が悪いんだろうけど、やるせないよね。
キッチン分離はウォーターサーバーで対応
LDKとする場合は、キッチンの機能が手近にあるので気にならないのですが、2階に簡易のリビングを用意して、1階に食料品庫・キッチンやダイニングスペースを準備する「食事の機能だけを切り分ける」方法も検討しておきたいところ。
衣食住の動線を全てリビングに集めるのもいいと言えばいいのだけど、先に話したように「ワークスペース」や「勉強」「遊び」まで詰め込まれると、実際のところすぐにごちゃついて「ある程度の機能性を分けて間取りを考えるのもありだよな」とか、最近考えています。
我が家は夜勤ありの時間差勤務となるので、2階のLDKで夜勤の準備をすると家族を起こしてしまう可能性があります。1階にキッチン・ダイニングスペースを移すと、生活空間と食事機能空間が分かれるので、「食事を食べる人は準備、食事を気兼ねなくできる」ので便利。実際、リビングでご飯食べるケースは我が家の場合はほぼなかったので、将来的には1階に機能部分を移して生活するように改変する予定です。
2世帯だから1階にもキッチンがあるので、ここはダイニングキッチンとして食事専用スペースにして、2階のキッチンは潰して広めのリビングに変えるか子供の独り立ち後の荷物を入れる収納に変えたいですね。
さて、ふと食事を切り離したリビングはそれはそれで使い勝手が良さそうだと思ったのですが、喉が渇いた時に1階までいくのは面倒だなと思いました。とは言え、熱源と騒音源になる冷蔵庫は置きたくない。
そうなると、消音系のウォーターサーバーあたりが馴染みよくおけるような気がしてきます。

ウォーターサーバー関連の記事もありますのでそちらもチェックしてみてください。

まとめ:LDKの間取りは生活の質を決める作業
簡単にまとめると、「家で何がしたいか」を決めるためには、LDKの間取りを熟慮しておくことが大切です。
家族にとっての生活の場が「仕事」や「アクティビティ」になる場合は、家は「休む場所」として必要な部屋を準備し、家に「余暇や仕事」を持ち込むようであれば、そのための機能を持たせるようにLDKなどの間取りを作っていくことになります。
ほとんどの場合は、家族は「家事」や「育児」が生活の中心になってしまうので、極論はこれらの雑務を最適化するために部屋の役割と動線を考えておけば失敗はしません。
変化があるとすれば「家で仕事」ができる時代になってきたので、ここはしっかりと線引きして集中できる部屋は用意しておいた方がいいかな、とは思います。
LDKの間取りに関する要点
- ダイニングとキッチンは機能的な部屋
- リビングは「休息や余暇」を過ごす部屋
- 自分たちにとって何が大事かを考えて、間取りの優先順位を決める
LDKの間取りに関する口コミや評判
LDKの間取りに悩んだ際に参考になりそうな口コミや評判に関する情報をまとめておきます。
Twitterの情報
収納を多くして‼
— Amigo小池・建築コンサルタント (@amigo_koike) February 25, 2023
荷物が多いんです…
本当に収納足りますか?
上記のような言葉を良くいただきますが、収納の為に家を作るんですか?
収納ばかりでLDKや部屋が小さくなっている間取りをよく見ます…
家を作るかをもう一度考えて欲しいです…#注文住宅#収納#デザイン住宅
これ故にLDKの一部に間仕切り可能な一部屋を作った♫コールドドラフトは空間が広ければあまり気にならない✌️
— Julie (@foxychild77) February 21, 2023
建て替え前は2階へ行くのに玄関付近まで行かなきゃならんかったけど、今はリビング階段で2階に行くのがラクでノンストレス。
多分構造や間取りによるから、後悔するかは一概には言えない https://t.co/iDaJQG6AnN
寒くてトイレに行くのが億劫すぎる
— ゆき (@yukit_19) February 20, 2023
昔LDKから直トイレ&直洗面所、浴室の間取りはありえ無いと思ってたけどあれは体には優しかったかも…(ただしドアの位置決めは大事)
LDKの間取りに関するよくある質問
- QどうしてLDK一体型の部屋が多いのですか?
- A
一番大きな理由は「広く見せる」ことができるためです。開放感といえば聞こえはいいですが、LDKが普及すればモデルハウスやショールームでも広く体感できます。見せる側にはとても都合がいい構造です。
加えて、キッチンにプライバシーを求めず、キッチンで生じるニオイや汚れの問題を無視するのであれば、生活動線が近くなることはメリットだと言えます。
- QLDKと言いますが、リビングって必要なんですか?
- A
部屋の役割としてのリビングは、「料理を作る」キッチンや「食事をとる」ダイニングとは違い、役割が曖昧です。
いわゆる団欒としてのリビングは、家族によってはそれほど長い時間を過ごす場所ではありません。用意しなければいけないスペースや家具ほど、活用されない可能性が高い部屋だといえます。
ChatGPTによって生成された質問と回答
私の勉強用ですが、ChatGPTに少しだけ文章作らせておいておきます。まだまだ信用はできないんだなぁ。
- QLDKとは何ですか?
- A
LDKは、「リビング・ダイニング・キッチン」の頭文字をとった言葉で、一般的にリビングルーム・ダイニングルーム・キッチンが一緒になったオープンスペースを指します。
- QLDKの間取りで注意すべき点は何ですか?
- A
LDKの間取りで注意すべき点は、家具の配置や採光・換気などが重要です。家具を配置する場合は、部屋の中心よりも壁際に置くことで、広く見せることができます。また、換気や採光にも注意が必要で、キッチンの換気扇の位置や、窓の大きさや位置などが重要なポイントです。
- QLDKの間取りで最適な広さは何平方メートルですか?
- A
LDKの間取りで最適な広さは、家族の人数や生活スタイルによって異なりますが、一般的には50平方メートル以上が望ましいとされています。ただし、間取りによっては30平方メートル程度でも快適に生活できる場合もあります。
- QLDKの間取りで、リビングルームとダイニングルームを分けることはできますか?
- A
LDKの間取りで、リビングルームとダイニングルームを分けることはできます。部屋の中央に壁を設けて、部屋を2つに分けることができます。また、引き戸やカーテンで仕切ることもできます。
- QLDKの間取りで、キッチンを閉じたい場合はどうすればいいですか?
- A
LDKの間取りで、キッチンを閉じたい場合は、引き戸やアコーディオンカーテン、フレンチドアなどを設置することができます。また、キッチンとリビング・ダイニングの間に、ブックシェルフなどを置いて、視線を遮ることもできます。
LDKの間取りに関連する記事
LDKの間取りに悩んだ際に役立ちそうな記事リンクを貼っておきます。
キッチンに関する記事で読んでおいてほしいもの
おすすめの記事をあげておきます。記事数だけは豊富。
システムキッチンの選び方
システムキッチンメーカー選定に悩んだら【ローコスト7社比較】という記事が、私くらいの収入層(年収400万円くらい)で家づくりをしている方にとって参考になると思います。
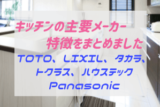
キッチンメーカーとお掃除のしやすさ評価
- TOTOのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れに関する情報まとめ
- LIXILのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れのしやすさ評価
- トクラスのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れ評価
- パナソニックのキッチン汚れ、お掃除・お手入れ評価
- タカラスタンダードのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れ評価
スマートキッチン
私は家電が好きなので、家づくりよりも「その後の生活を便利にする」キッチンでも役立つスマート家電に注目しています。安い家づくりしても、機能が拡張できていくのはいいですね。

キッチンにギリギリ関係しているくらいの記事一覧
キッチンと家電の話
- 食洗器があなたの家にも必要な6つの理由【TOTOキッチンのオプション】
- スマートホームにするためにやるべきこと「初心者のための方法解説」
- スチームクリーナーで浴室・外壁のカビ・苔を撃退する
- あえて蒸気レスの炊飯器を選ぶ理由「家と子供を守るため」
- 車にも積める、ポータブル冷蔵庫のおすすめ
TOTOキッチンレビュー
キッチンと間取りの話
- 「LDKと間取り」キッチンとダイニング、リビングの失敗しない分け方
- キッチンと水栓の話「何を選んだらいいか全くわからない場合」
- キッチンに冷蔵庫が入らない事件【搬入を断られた時の5つの対策】
- コンロ・クッキングヒーターなどの火力調理器具の話|家づくり
- キッチンコンセントは便利家電の争奪戦で埋まるので余裕を持った計画を
掃除しやすいキッチンはどこのメーカー?
キッチンメーカーの比較記事を書いています。
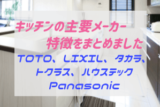
- クリナップのキッチンは汚れやすい?お掃除、お手入れで評価
- タカラスタンダードのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れ評価
- トクラスのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れ評価
- パナソニックのキッチン汚れ、お掃除・お手入れ評価
- LIXILのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れのしやすさ評価
- TOTOのキッチンは汚れやすい?お掃除・お手入れに関する情報まとめ
メーカー別キッチン情報
収納に関する記事で読んでおいてほしいもの
収納と間取りについての考えをまとめた記事があります。

収納の関連記事一覧
間取りと収納に関する記事一覧
- スペースを取らない布団の収納術!快適な睡眠環境を手軽に実現する方法
- もう、広い家はいらない? 物置シェアで収納いらず
- 小上がり和室の段差の決め方「床下収納と登りやすさ」
- 新築時の可動棚サイズはカラーボックスを参考にすべし
- 納戸、外部収納、シュークローク、ロフトは不要
- 子供部屋の収納にクローゼットはいらない「ライフサイクルを考慮」
コンセントに悩んだ時に読みたい記事
コンセントの数や位置に関しての情報をまとめた記事はこちらになります。
- リビングに必要なコンセント数を丁寧に解説する
- 外部コンセントの必要性「外構・エクステリアにあると便利な家電・設備」
- 収納・クローゼットにこそ欲しいコンセント「ウォークインやパントリーには必要?」
- キッチンコンセントは便利家電の争奪戦で埋まるので余裕を持った計画を
- 浴室・脱衣所・洗面所のコンセント数と設置に関する注意点
















コメント
「レイアウト わかり わかり レイアウト」に関する最新情報です。
この記事では、文章を書く際の「レイアウト術」に焦点を当て、特に「踊り場が無い階段は地獄」という比喩を用いて、分かりやすい文章作成の重要性を強調しています。著者は、文章を読みやすくするためのレイアウト技術が、専門家だけでなく一般の人々にも必要であると述べています。具体的には、文字の配置やサイズ、強調方法を工夫することで、読者にとって理解しやすい文章を作成することができるとしています。記事は、長年にわたり支持されている書籍の内容を基にしており、現代のニーズに合わせて内容が更新されています。
https://gendai.media/articles/-/150919
「つなげる リビング リビング 設け」に関する最新情報です。
この記事では、東京都板橋区の事例を基に、2階リビングに多様な窓を設けることで内外のつながりを適切に実現する窓設計について解説しています。特に、窓手法として「この場所」を感じる窓の効果や、眺望用窓における高さ寸法の重要性が強調されています。多様な窓の設置により、居住空間の快適さや景観の楽しみ方が向上することが示されています。
https://www.s-housing.jp/archives/381308
「住宅 配分 対策」に関する最新情報です。
国土交通省は2025年度の予算を発表し、全体で8兆4318億円を計上しました。この中で住宅局関係の予算は1兆1245億4000万円で、主に住まいの安全確保や良好な市街地環境の整備、脱炭素対策、多様な住まいの確保、DX推進に重点を置いています。また、「住宅・建築物防災力緊急促進事業」に313億500万円を配分し、地域の防災拠点となる建築物の整備や耐震化を進める計画です。全体的に、国民の安全・安心や持続的な経済成長を目指した取り組みが強調されています。
https://www.s-housing.jp/archives/381873
「住宅 配分 対策」に関する最新情報です。
国土交通省は2025年度の予算配分を発表し、全体で8兆4318億円を計上。その中で住宅局関係予算は1兆1245億4000万円となり、前年度比11.3%増加した。主な取り組みは「国民の安全・安心の確保」「持続的な経済成長の実現」「地方創生」に基づき、特にカーボンニュートラルに重点を置いている。具体的には、住まいの安全確保や市街地環境の整備、既存ストックの有効活用、脱炭素対策、多様な住まいの確保、DX推進の5分野に注力する。また、住宅・建築物防災力緊急促進事業には313億500万円が配分され、地域の防災拠点の整備や耐震化が進められる。
https://www.s-housing.jp/archives/381873
「住宅 配分 対策」に関する最新情報です。
国土交通省は2025年度の予算を発表し、全体で8兆4318億円を計上しました。住宅局関係の予算は1兆1245億4000万円で、主に「住まい・くらしの安全確保」「市街地環境の整備」「脱炭素対策」「多様な住まいの確保」「DX・生産性向上」の5分野に重点を置いています。特に「住宅・建築物防災力緊急促進事業」には313億500万円が配分され、地域の防災拠点の整備や耐震化が進められます。また、カーボンニュートラルへの取り組みも強調されています。
https://www.s-housing.jp/archives/381873
「aws ai 生成」に関する最新情報です。
クラスメソッド株式会社は、アマゾン ウェブ サービス(AWS)の公式トレーニングとして、生成AIの基礎を学ぶ1日コース「Generative AI Essentials on AWS」の受講申込を開始しました。このコースでは、生成AIの基本概念、ユースケース、責任あるAI導入の考え方を学ぶことができ、エンジニアだけでなくビジネス部門の方にも適しています。コースは座学とハンズオンを組み合わせた内容で、AWS認定(AWS Certified AI Practitioner – Foundational)の取得を目指す方にも役立ちます。コースの期間は7時間で、価格は77,000円(税込)ですが、メンバーズプレミアムサービスに加入している場合は61,600円(税込)となります。現在、生成AIに関するAWS公式トレーニングコースは全3種が開講されています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000401.000014901.html
「分ける 生死 生死 分ける」に関する最新情報です。
この記事では、2024年に発生した能登半島地震を例に、大地震がいつ襲ってくるか分からない恐怖について述べています。特に「7秒」が生死を分ける重要な時間であることが強調されており、地震の揺れが始まった際にどれだけの行動が取れるかが生存に影響を与えるとされています。著者は、防災に関するデータや対策をまとめた書籍を紹介し、誰もが大地震から逃れられない時代において、事前の準備と知識の重要性を訴えています。
https://gendai.media/articles/-/145293
「寝室 レイアウト 家づくり」に関する最新情報です。
この記事では、家づくりにおける寝室のレイアウトについての体験談が紹介されています。理想的なおしゃれな寝室を実現したものの、実際に生活してみると広い空間が十分に活用できていないという現実が浮き彫りになっています。読者の失敗エピソードを通じて、理想だけでなく現実的なライフスタイルに合ったレイアウトを検討する重要性が強調されています。また、広い寝室のメリットとデメリットについても触れられ、快適な睡眠環境を得るためのポイントが示されています。
https://sumica.niigata-nippo.co.jp/magazine/735
「サーバー easyblocks ddn」に関する最新情報です。
ぷらっとホーム株式会社は、DHCP・DNS・NTPサーバーが一体化したハイエンドモデルのネットワークサーバーアプライアンス「EasyBlocks DDN1 Enterprise」を発表しました。この製品は、既存の「EasyBlocks DDN1」の上位モデルであり、学校や医療機関、中小企業、商業施設などの大規模ネットワーク構築に最適です。
「EasyBlocks DDN1 Enterprise」は、ソフトウェア機能の強化やActive-Standby方式の冗長化機能を備えており、ネットワークインフラの運用や管理を一元化できます。また、リモートマネジメントサービス「AirManage2」が付随しており、遠隔地からの設定変更やアップデートが可能です。
さらに、2025年1月23日に製品の詳細を解説するセミナーが開催され、参加者には抽選でオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンも実施されます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000013751.html
「サーバー easyblocks ddn」に関する最新情報です。
ぷらっとホーム株式会社は、DHCP・DNS・NTPサーバーが一体化したハイエンドネットワークサーバーアプライアンス「EasyBlocks DDN1 Enterprise」を発表しました。この新モデルは、既存の「EasyBlocks DDN1」を基にしており、学校や医療機関、中小企業、商業施設などの大規模ネットワーク構築に最適です。主な特徴として、ソフトウェア機能の強化やActive-Standby方式による冗長化機能があり、これによりネットワークインフラの運用管理が効率化されます。また、リモートマネジメントサービス「AirManage2」により、遠隔地からの設定変更やアップデートも可能です。さらに、2025年1月23日に製品解説セミナーが開催され、参加者には抽選でオリジナルグッズがプレゼントされるキャンペーンも実施されます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000013751.html
「生成 動画 インテリア」に関する最新情報です。
東京都荒川区のマインは、不動産・建設業向けに生成AI技術を活用した「urvue(アービュー)」のベータ版を発表しました。このシステムでは、インテリア画像をアップロードするだけで、約2時間でリアルな3Dウォークスルー動画を自動生成します。生成された動画はプレビュー可能で、満足できるクオリティであればダウンロードでき、必要に応じて再生成も行えます。
https://www.s-housing.jp/archives/370856
「信用金庫 共通 成年後見制度」に関する最新情報です。
新潟県内の成年後見制度関連手続きが、12月2日から18の金融機関で共通化されることが発表されました。これにより、新潟信用金庫や三条信用金庫を含む6つの信用金庫が新たにこの取り組みに加わります。共通化される手続きには、利用者が記入する「成年後見制度に関する届出書」と、提出する確認書類(登記事項証明書など)が含まれ、金融機関間の連携を強化し、利便性の向上を図ることが目的です。
https://www.niikei.jp/1302387/
「設計 あか あか がわ」に関する最新情報です。
あかがわ建築設計室が新潟市東区津島屋で開催する完成見学会のお知らせです。このイベントでは、施主との密なコミュニケーションを基にした「リアルな空間」を体感できます。設計は使い勝手を重視し、生活のしやすさと温かみを兼ね備えた木の温もりが感じられる住まいが特徴です。見学を通じて、あかがわ建築設計室のこだわりやデザインの魅力を実感できる貴重な機会です。
https://niigata.jutaku2shin.com/housing_event/23705/
「1日 共通 成年後見制度」に関する最新情報です。
新潟県内の11の金融機関が、10月1日から成年後見制度に関連する手続きを共通化することを発表しました。この取り組みは、株式会社大光銀行と株式会社第四北越銀行が4月1日から始めたもので、今後は長岡信用金庫や新潟縣信用組合などの信用金庫・信用組合にも拡大されます。共通化される手続きには、利用者が記入する「成年後見制度に関する届出書」と確認書類が含まれます。
https://www.niikei.jp/1196583/
「分ける 大地震 生死」に関する最新情報です。
この記事では、大地震が発生した際の危険性と生死を分ける「7秒」の重要性について述べられています。2011年の東日本大震災から13年が経過し、再び震災が頻発する中、誰もが大地震から逃れられない状況にあることが強調されています。特に、地震の揺れが始まってからの7秒間が、どれほどの行動を取れるかによって生存の可能性が大きく変わることが示されています。記事は、宮地美陽子の著書からの抜粋であり、防災に必要なデータや対策がまとめられています。
https://gendai.media/articles/-/135407
「トイレ 掃除 暑い」に関する最新情報です。
このWebサイトは、ライオン株式会社が発信する「知らなきゃ良かったトイレの秘密シリーズ」の第10弾で、夏のトイレ掃除に関するアドバイスを提供しています。暑い夏は来客が多く、トイレが見られる機会が増えるため、特に掃除が重要です。調査によると、夏のトイレは外気温に近い温度になることがあり、掃除が億劫になる季節でもあります。また、訪問先のトイレの汚れやニオイを気にする人が多いことが分かりました。
掃除の効率を上げるためには、時短掃除がポイントで、特に「ルックプラス 泡ピタ トイレ洗浄スプレー」を活用することが推奨されています。この洗剤は便器や床の掃除を一度に行えるため、手間が省けます。また、来客目線でのチェックも重要で、普段とは異なる視点で汚れを確認することが勧められています。掃除を通じて、清潔感を保つことが大切です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000039983.html
「対策 配分 予算」に関する最新情報です。
国土交通省は、自然災害の再被災を防止するための緊急防災対策予算の初回配分として、2024年度に48億2600万円を29件の公共事業に配分することを発表した。配分予算は洪水や浸水対策、雪崩対策、崖崩れや法面崩壊対策、事前防災対策などに割り当てられる。
https://www.s-housing.jp/archives/356589
「エアコン エアコン 冷蔵庫 冷蔵庫」に関する最新情報です。
今年は電気料金の高騰を懸念している人が多く、特にエアコンと冷蔵庫の節電に関心が高いことが明らかになっています。エアコンの節電対策として、設定温度を1℃高くするだけで約10%の省エネが可能であり、風速を自動設定にすることや直射日光対策を行うことが効果的です。冷蔵庫の節電対策では、冷気の流れを良くするために吹出口や吸込口の前には食品を置かず、冷気を循環させる工夫が重要です。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHBzOi8va2FkZW4ud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTYwNDYzNy5odG1s0gEA?oc=5
「家電 エアコン 冷蔵庫」に関する最新情報です。
大船渡市では、省エネ家電の買い替えを促進するための補助金制度が実施されており、エアコンや冷蔵庫、給湯器を省エネ型に買い替える市内の世帯に最大5万円の助成金が支給されます。補正予算案に盛り込まれた第2弾の制度では、前回申請した世帯以外が対象で、助成総額が2000万円に達した時点で終了します。申請受付は8月から開始される予定で、対象家電を購入した後に申請手続きを行うことができます。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiK2h0dHBzOi8vdG9oa2Fpc2hpbXBvLmNvbS8yMDI0LzA2LzE0LzQ0Mjk3Ni_SAQA?oc=5
「エアコン エアコン 冷蔵庫 冷蔵庫」に関する最新情報です。
沖縄県が実施する「おきなわ省エネ家電買換応援キャンペーン」では、省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫を購入した県民に最大5万円分のキャッシュレスポイントが贈られる。キャンペーンは6月1日から2024年5月25日まで実施され、申請台数は1人当たりエアコン2台、冷蔵庫1台までとなっている。申請受付期間は6月1日から来年2月14日までとなっているが、予算上限に達した場合は早期終了する可能性がある。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vd3d3Lm9raW5hd2F0aW1lcy5jby5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzEzNjU3NzHSATNodHRwczovL3d3dy5va2luYXdhdGltZXMuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvYW1wLzEzNjU3NzE?oc=5
「エアコン 家庭 掃除」に関する最新情報です。
エアコンのクリーニングについて、家庭でできる部分とプロに依頼する部分があることが述べられています。家庭でできる掃除はフィルターや吹き出し口の清掃であり、これにより節電効果やカビの繁殖の予防が期待できます。一方、エアコン内部のクリーニングはプロに依頼する必要があり、予約が混雑している場合もあるとのこと。また、エアコンの試運転も重要で、気温が21度から25度の間に行うことが推奨されています。修理が必要な場合もあるため、異常があれば早めに対処することが大切です。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vd3d3LmZubi5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzY5NTcwNtIBAA?oc=5
「エアコン 節電 空調」に関する最新情報です。
電気代値上げに対抗するためのエアコンの節電術について、空調メーカーのプロがアドバイスを行っています。暑さが本格化する中、エアコンの使用が増える中で電気代の増加が懸念されています。中国電力の値上げや補助金の縮小により、家計への負担が増加する中、ダイキンがエアコンの省エネに関する誤解を解消するための情報を提供しています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vd3d3LmZubi5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzY5MzcwMNIBAA?oc=5
「amd サーバー amd epyc」に関する最新情報です。
AMDの最新サーバー向け第4世代AMD EPYC™プロセッサーは、優れたエネルギー効率を持ち、高パフォーマンスでサーバー台数と電力を削減することが可能。ベンチマーク結果によると、40%ほど少ないサーバー台数で同等の性能を発揮し、電力消費も4割程度少ない。企業ではAMDのCPUを採用することでコスト削減やCO2排出削減が実現されており、TSMCや金融機関のDBSなどがその効果を実感している。AMDのEPYC CPUはチップレット技術を採用し、小さなチップを組み合わせることでパフォーマンスを向上させ、製品バリエーションも増えている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vY2xvdWQud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL2NkYy9yZXBvcnQvMTU3OTgyMS5odG1s0gEA?oc=5
「配分 安全 確保」に関する最新情報です。
国土交通省は2024年度の予算配分を発表し、7兆5743億9700万円を「国民の安全・安心の確保」「持続的な経済成長の実現」「個性をいかした地域づくりと分散型国づくり」の3つの柱に重点を置いて配分することを明らかにした。特に住宅関連では、大阪府門真市などで老朽建築物密集地区の防災・減災対策を強化し、安全な市街地の整備を進める取り組みが行われる予定である。
https://www.s-housing.jp/archives/346832
「家事 嫌い 嫌い 家事」に関する最新情報です。
新たな学期や年度が始まる春に一人暮らしを始めた人も多い中、不動産情報サービスのアットホームが18〜40歳の一人暮らしを対象に「家事と住まい探しの実態調査」を行い、最も嫌いな家事ランキングを発表した。調査結果によると、一人暮らしの人が最も嫌う家事は「排水溝の掃除」であり、その他にも「トイレ掃除」が苦手とされている。特に水回りの家事に対する負担感が高く、トイレ掃除が最も負担と感じられる家事となっている。一人暮らしの人は、トイレ掃除では洗剤を使ったり家事代行サービスを利用するなどの工夫をしている。排水溝の掃除に関しては、汚れる前にこまめに掃除するなどの工夫がされており、掃除時間を短縮する方法が取られている。家事のしやすさは住まい選びにも影響を与えるため、キッチンのスペースや間取りなどが重要視されている。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6615e160e4b02edf20086ac5
「ai nvidia 生成」に関する最新情報です。
日立製作所とNVIDIAが協業し、エネルギーや交通などのOT領域で生成AIを展開することが発表された。この協業により、日立のソリューションとNVIDIAの生成AIを組み合わせ、センサーやデバイスが生成するデータを活用して現場の生産性や洞察力を向上させる取り組みが行われる。具体的な取り組みとして、組織横断的なCoEを設立し、NVIDIAのGPUやソフトウェアを活用した業界向けサービスの開発・展開が進められる予定だ。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiMGh0dHBzOi8veHRlY2gubmlra2VpLmNvbS9hdGNsL254dC9uZXdzLzI0LzAwNDI1L9IBAA?oc=5
「フィットネス トラッカー フィットネス トラッカー」に関する最新情報です。
2024年に注目を集めているスマートリング「Galaxy Ring」は、スマートウォッチとは異なり、主に独立したヘルストラッカーとして機能するデバイスとして注目されている。サムスンだけでなく、Ouraや栄耀(HONOR)、Appleなどもスマートリングの開発に取り組んでおり、小型フィットネスモニターに対する注目が高まっている。
https://japan.cnet.com/article/35215967/
「ドーム ウォーター ウォーター ドーム」に関する最新情報です。
住宅メーカー「一条工務店」は、2024年3月9日に、さくらウォータードーム手作り体験会を開催する。参加は無料だが予約が必要で、液体の中で満開の桜が咲き誇るウォータードームを家族一緒に作ることができる。昨年の開催では大盛況で、子どもたちやカップルが楽しんで参加した。開催は午前10時~、午後1時~の2部制で、各回10個までの完全予約制。製作したスノードームは持ち帰れるので、春のインテリアとしても楽しめる。
https://www.joetsutj.com/2024/03/03/070000
「間取り 子ども 夫婦」に関する最新情報です。
この記事では、子供がいる夫婦の間取りに関する悩みが取り上げられています。具体的には、夜の営みの音が子供部屋に聞こえてしまうことや、セックスができないことに困惑している夫婦の事例が紹介されています。記事では、間取りの問題点として、主寝室と子供室の配置や水廻りへの動線、和室の位置などが指摘されています。また、子供部屋が夫婦の寝室の隣にあることや、子供室とドアが近いことも問題とされています。このような問題を解決するためには、間取りの変更が必要とされています。
https://gendai.media/articles/-/123679
「行動 dnp デザイン」に関する最新情報です。
大日本印刷株式会社(DNP)は、独自の行動デザインメソッドを活用して、脱炭素社会の実現に向けたまちづくりを住民や自治体と検討しています。DNPは柏の葉アーバンデザインセンターと連携し、柏の葉リビングラボプログラムのワークショップに参画し、83のアイデアを創出しました。これらの成果は柏の葉エコWEEKENDで発表されました。DNPは環境省が提唱する「deco活」にも参画し、気候変動や脱炭素の基礎知識の習得、脱炭素の行動目標の設定、まちづくりのアイデア検討の3つのワークショップを実施しました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000539.000069194.html
「分ける 生死 生死 分ける」に関する最新情報です。
この記事は、大地震が発生した場合、建物の下敷きになる可能性があることや、生死を分けるためにはわずか7秒の時間があることを伝えています。首都直下地震や南海トラフ巨大地震などの過去の災害や富士山の噴火なども取り上げられています。また、2024年に東京で開催されるオリンピックに向けて、陸上競技選手が7秒間のタイムを狙ってトレーニングをしていることも紹介されています。
https://gendai.media/articles/-/122266
「ドロボー ドロボー 幼稚園 幼稚園」に関する最新情報です。
株式会社ソノリテが主催する「ドロボー幼稚園」で、限界クリぼっちを救う究極のほっこりイベントが開催されます。イベントでは、2023年12月18日から12月31日までの期間限定で、うさぎぼうしをかぶって集まることが呼びかけられています。参加者はNintendo SwitchやSteamで遊べる「ぬすんであそぼ ドロボー幼稚園」を楽しむことができます。また、クリスマスにはローストチキンのプレゼントキャンペーンも実施されます。イベントの詳細や参加方法は公式ウェブサイトで確認できます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000019738.html
「宝石 眠れ 眠れ 宝石」に関する最新情報です。
airClosetとMASHIROが初めてコラボしたキャンペーンが12月15日から開始される。このキャンペーンでは、airClosetの月額会員限定で300名に眠れる宝石をシェアする機会が提供される。参加者はSNSを活用して眠れる宝石のプロジェクトをシェアし、特別価格でオーダージュエリーを作ることができるアップサイクルクーポンをプレゼントされる。このキャンペーンは持続可能なファッションを楽しむ共通の目的を持つairClosetとMASHIROのコラボレーションによって実現されたものであり、参加者は宝石の過剰な在庫を減らし、眠っている宝石を活用することができる。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000133317.html
「chimaki 生成 ai」に関する最新情報です。
新潟県加茂市の株式会社K-walkが、完全オフライン対応の生成AIシステム「Chimaki」を開発し、加茂市役所で試験導入を開始しました。Chimakiは、AIアシスタント機能を備えた生成AIシステムであり、インターネット接続なしでデータの検索や業務の改善を支援します。同社は今後もChimakiの性能向上やシステムの継続的なサポートを進めていく予定です。
https://www.niikei.jp/905178/
「choo jimmy jimmy choo」に関する最新情報です。
2023年12月9日、日本最大級のJIMMY CHOO GINZA CONCEPT STOREがオープンしました。前日のプレオープンイベントにはクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイや人気セレブリティが多数来場し、オープンを祝福しました。この新しいコンセプトストアは、銀座に位置し、160平方メートル以上の広さを持ち、JIMMY CHOOの最新ポップアップブティックや新しいインテリアコンセプトを導入しています。また、メンズシューズ、ハンドバッグ、アイウェア、フレグランス、ブライダルコレクションなど、幅広いアイテムが取り揃えられています。この新しい店舗は、JIMMY CHOOの日本での4番目の店舗となります。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000054.000013826.html
「ジャーブネット 解散 25」に関する最新情報です。
ジャーブネットは、25年の活動を終えるため、今月末に解散することを発表しました。ジャーブネットは、住宅産業に関する情報を提供するウェブサイトで、長い間活動してきました。このニュースは、読者やフォロワーに衝撃を与えています。ジャーブネットの解散により、住宅産業に関する情報の提供に影響が出る可能性があります。
https://www.housenews.jp/association/25581
「ldk ldk 対応 キッチン」に関する最新情報です。
パナソニックは、炊飯器を必要としない新しいキッチンを狭小のLDK(リビング・ダイニング・キッチン)に対応させることを発表しました。この新しいキッチンは、パナソニックのラクシーナII型対面プランという住宅ソリューションに組み込まれており、12月から提供されます。このキッチンは、狭小なスペースにも効率的に収まるように設計されており、炊飯器のスペースを削減することでLDKの面積を縮小することができます。価格は195万円からで、新築やリフォームの際に利用することができます。この新しいキッチンは、物価の高騰による住宅購入のニーズを考慮し、キッチンとダイニングスペースを効果的に活用することができるようになっています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNmh0dHBzOi8vd3d3LndhdGNoLmltcHJlc3MuY28uanAvZG9jcy9uZXdzLzE1NTE3NjkuaHRtbNIBAA?oc=5
「映画 上映 issue 満席」に関する最新情報です。
特定非営利活動法人ブラックスターレーベルが制作した新作映画『Dance with the Issue』は、エネルギー課題をドキュメンタリーとダンスで伝える作品です。上映が下北沢K2で行われ、満席続出の大盛況となりました。映画は12月から前橋でも上映される予定であり、メディア各社からも注目を浴びています。この映画は、エネルギーの問題についての意識を高めるだけでなく、新たな映画の形式を追求している点でも注目されています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000128669.html
「bfcm comfee comfee 冷蔵庫」に関する最新情報です。
日本美的株式会社は、BFCM(ブラックフライデー&サイバーマンデー)セールの一環として、Comfee’冷蔵庫の最低価格を大々的に放送することを発表しました。11月22日にはAmazonでBlack Fridayの先行セールが開催される予定であり、全品がベストセラー超特価で販売されます。Comfee’冷蔵庫は洗練されたデザインで、イタリア、イギリス、ドイツ、EU圏で人気を集めています。日本でも2019年に上陸し、若者を中心に大きな支持を受けています。このセールは2023年11月22日から12月1日まで開催されますので、お見逃しなく。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vcHJ0aW1lcy5qcC9tYWluL2h0bWwvcmQvcC8wMDAwMDAwMjMuMDAwMTE1NDU0Lmh0bWzSAQA?oc=5
「fitbit フィットネス charge」に関する最新情報です。
Googleに買収されたFitbitの最上位モデルである「Fitbit Charge 6」が発売されました。この新しいモデルは、GoogleマップとYouTube Musicに対応しており、多機能な製品となっています。アルミボディーで高級感があり、側面ボタンも復活しています。価格は2万3800円からで、Pixel Watch 2の半額となっています。Fitbitのフィットネストラッカーとしては上位モデルであり、フィットネスやヘルスケアの機能も充実しています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3Lml0bWVkaWEuY28uanAvcGN1c2VyL2FydGljbGVzLzIzMTEvMTQvbmV3czEwNi5odG1s0gE5aHR0cHM6Ly93d3cuaXRtZWRpYS5jby5qcC9wY3VzZXIvYW1wLzIzMTEvMTQvbmV3czEwNi5odG1s?oc=5
「コヨーテ ソファ 退席」に関する最新情報です。
アメリカのサンフランシスコで、コヨーテが住宅のテラスに置かれたソファに陣取り、退席を拒否しているというニュースがありました。動物保護管理官が駆けつけ、コヨーテの様子を見守っています。コヨーテはソファでくつろぎ、近づく人に対しても警戒心を持っています。この一幕はFacebookで話題となり、多くの人々がコヨーテの様子を見守っています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/coyote-lounges-on-patio-couch_jp_654ad13ae4b0e63c9dc15e93
「エアコン 電気代 家計」に関する最新情報です。
冬になると家計に与える電気代の影響が大きくなるため、エアコンの節電に取り組んでいる人は半数以下であり、エアコンを使用する人のうち7割以上が電気代に無駄がある可能性があることが分析データからわかった。このデータは、ダイキン工業株式会社が実施した実態調査に基づいている。エアコンのしくみと電気代の関係をわかりやすく紹介するサイトと動画も公開されている。冬場には家庭の電力消費が増大し、エアコンが暖房器具として大きな割合を占めるため、節電の取り組みが重要とされている。政府も電気料金の補助金の延長などで家計への影響を緩和しようとしている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOmh0dHBzOi8vcHJ0aW1lcy5qcC9tYWluL2h0bWwvcmQvcC8wMDAwMDAwODAuMDAwMDE1NDk4Lmh0bWzSAQA?oc=5
「12 12 冷蔵庫 エアコン」に関する最新情報です。
岐阜市では、省エネ家電の購入に最大4万円の補助金が提供されることが発表されました。この補助金は、冷蔵庫やエアコンなどの家電製品の購入に利用することができます。補助金の申請は12月から開始されます。岐阜市の新着情報や天気などの情報もこのウェブサイトで確認することができます。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vd3d3LmNodW5pY2hpLmNvLmpwL2FydGljbGUvODAwOTA40gEA?oc=5
「snapdragon ai 生成」に関する最新情報です。
Qualcommは、「Snapdragon Summit 2023」でSnapdragon 8 Gen 3を発表しました。この新しいプロセッサは、CPUやGPUだけでなく、NPUの性能も大幅に向上させ、生成AIの処理も可能になりました。具体的な応用例として、写真の拡張やイラストの生成、チャットボット、暗所での動画などが紹介されました。Snapdragon 8 Gen 3は、AIの性能を大幅に向上させ、2024年までにはHexagon NPUの性能を約2倍にする予定です。また、QualcommはSnapdragon 8 Gen 3によって、ハイエンドスマートフォン市場で新たな競争軸を占めることを期待しています。Snapdragon 8 Gen 3は、CPU、GPU、NPUの組み合わせによるヘテロジニアスコンピューティングのアプローチを取り入れており、Qualcomm AI Engineによってトータルの性能を向上させています。CPUとNPUの役割が明確化され、Hexagon DSPも含めたプロセッサの性能も大幅に向上しています。Snapdragon 8 Gen 3は、機械学習やAIの処理において、前世代のSnapdragon 8 Gen 2と比較して約98%の高速化を実現し、2倍ほどの性能向上を達成しています。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2310/28/news059.html
「作る 100 dash」に関する最新情報です。
日本テレビの人気番組「鉄腕DASH」が「100年の杜を作る」という企画を進めている一方で、日本テレビ自体が都立明治公園の杜を壊していることが明らかになりました。都立明治公園では、都市公園の施設設置や整備を行う事業者を公募で選ぶPFI方式が採用されており、日本テレビはその一環として杜の整備に取り組んでいます。しかし、同局が運営する霞ヶ丘アパート跡地にも50年間コンクリートが敷かれており、杜を作る一方で杜を壊している矛盾が指摘されています。日本テレビはこの問題に対し、番組の企画として「鉄腕DASH」が2016年から始まったことや、杜の整備に取り組むPFI事業社として東京建物や三井物産、読売広告社など6社が協力していることを回答しています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/tetsuwan-dash-meiji-park_jp_6530f66ce4b03b213b08c026
「やり 家事 やり 家事」に関する最新情報です。
「みんなが一番やりたくない家事は?洗濯や食器洗いよりやりたくないのは…【ランキング】」という記事では、やりたくない家事についてのランキングが紹介されています。アンケート結果によると、1位はアイロンがけ、2位は食器洗いでした。アイロンがけはシワがつくことや準備が面倒なことが理由として挙げられています。食器洗いは食事の後に洗い物がたくさん溜まることや、シンクがいっぱいになることが負担とされています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_651385b6e4b09c7605f908d4
「まとめ まとめ ドア ケース」に関する最新情報です。
三菱電機は、細かな食品を収納ケースでまとめやすい3ドア冷蔵庫を発売する。この冷蔵庫は、フリーケースやタマゴトレイなどの収納ケースを備えており、食材をまとめて収納することができる。また、冷凍や冷蔵のフリーケースは取り出しやすく、食材の探し時間を短縮することができる。さらに、氷点下ストッカーやワイドチルドなどの機能を備えており、食品の鮮度を長持ちさせることができる。この冷蔵庫は2023年9月8日に発売され、価格は約209,000円前後と予想されている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHBzOi8va2FkZW4ud2F0Y2guaW1wcmVzcy5jby5qcC9kb2NzL25ld3MvMTUyOTg0MC5odG1s0gEA?oc=5
「テレビ 電気代 目安」に関する最新情報です。
このウェブサイトでは、テレビの電気代についての分析データが図解で紹介されています。テレビの種類やサイズによって消費電力と電気代が異なることが示されており、1時間当たりや1か月の目安が提供されています。また、テレビの電気代を節約するための方法も紹介されています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vb3RvbmEtbGlmZS5jb20vMjAyMy8wOC8yOS8xNjc1Mjcv0gEtaHR0cHM6Ly9vdG9uYS1saWZlLmNvbS8yMDIzLzA4LzI5LzE2NzUyNy9hbXAv?oc=5
「account twitter view」に関する最新情報です。
Twitterは、ツイートを閲覧するためにアカウントが必要になったと発表しました。これにより、アカウントを持っていないユーザーはツイートを見ることができなくなります。TechCrunchによると、この変更はTwitterのユーザーベースを拡大し、アプリの利用を促進するための戦略の一環とされています。Elon Muskのツイートをきっかけにこの変更が行われた可能性もありますが、Twitterはこの件についてコメントしていません。
https://techcrunch.com/2023/06/30/twitter-now-requires-an-account-to-view-tweets/