リビングの間取りを考える基本として、考えるべき「広さ」についての概念をひたすらに説明していきます。

結論としては、結局、リビングに何を求めるのか、それによって間取りは変わってくるよ、というだけの話なんですけどね。

自分が失敗したな、と思った点なども随所で解説していますので、お時間がある時にゆっくりと見ていってください!
リビングの間取り設定で大事なこと

まずは、リビングの間取りについて考えるべきことをまとめていきます。簡単にいえば「広さ」の話になるのですが、感じ方は人それぞれだけど「どう感じることになるか」を私なりに伝えて行けたらいいな、と思って書いていきます。
「広さ」と「狭さ」について
まずは広さについて。広いに越したことはないが、広さはコストへの影響が多いのと、土地という絶対条件もあるので、結局のところ「どれくらい我慢できるか」の方が大事だったりします。
「快適な広さ」とは
まず、「快適な広さ」について。ポイントは以下の通り。
移動するということ
まず、人もモノも移動します。人の通り道として、生活動線は配慮しやすいのですが、見落としがちなのは「モノ」の動線。
わかりやすい例で言えば、「冷蔵庫」などの大型家電の搬入経路などは最初から考慮しないといけないということ。大型家電・大型家具は買い替えがあります。「どのサイズのものまで家の中に入れるのか」は必ず考えておきたいところです。

また、モノの移動でいえば、「ルンバの動線」についても重要です。お掃除ロボットを含め、今後家の中を動き回るのは人だけではなくなってきます。人が我慢すればいいことでも、ロボットの通行には妨げになるようなものは家を建てる段階から配慮する必要があります。

人の移動については「人の生活動線は変わる」ということも考えておきたいところ。10年くらい前までは「職業は固定」して考えていたと思いますが、仮に転職をしなくても仕事内容は大きく変わる可能性がある。例えば、リモートワーク。職場・学校に行く必要がなくなる未来は考えておかなければなりません。
また、人は老いるもの。歳をとったら階段がつらくなるなぁ、などは考えるのですが、「介護動線」までは考慮していない方もいらっしゃるはず。介護が必要な時はリフォームなどで対応することにはなりますが、脳梗塞などは突然起きて、明日からはベッド上での生活、なんてこともありうるのです。
介護サービス導入のためには、例えばお風呂までの動線と十分な広さが求められます。必要性がなければ新築時などに無理やり車椅子を通すくらいの廊下までは必要ないかもしれませんが、最初から対応できると必要なサービスを導入する際には少しだけ考えなければいけないことは減らすことができます。
このように、「人」や「モノ」の動線だけでも考えることは山積みです。簡単な解決方法は「部屋を広めにする」ことですが、そうはいかないのが懐事情。
目的によって必要な広さは違うということ
リビングの広さについて話をしていますが、リビングって何に使用する部屋でしょうか? 案外と漠然としたものではありませんか?
例えば、こどもが「遊ぶ」スペースをリビングに設けるのと、「テレビ鑑賞をする」場所として準備する場合には要求される広さは変わってきます。遊びも「子供の数」で変わりますし、友達を呼ぶのがリビングなのか、子供用のスペースがあるのかでも違います。
後述しますが、リビングが「ワークスペース」や「学習」「家事」をする場所を兼務する可能性もあります。この時、それぞれの役割によってリビングの表情を変えるような工夫・仕掛けが必要になります。
ただ、あまり多目的に使用することを考えすぎると、今度はごちゃごちゃとしたイメージになりかねないので、適度に目的はわけながら、可変的に部屋が利用できるようにしておくことが大事と言えそうです。
なんだかんだ、人は慣れるということ
広さについては、最終的にはいい意味でも悪い意味でも、人の方が順応します。狭い空間でも生活できていても、新築すると今度は耐えられなくなったり、あるいは多少狭くても幸せに暮らせたり。結局のところ、「何を気にして生きていくか」ということに尽きます。
新築の場合は、間取りも自分で考えるので「要求する広さ」のハードルが上がります。いっそ、建売や中古物件を買った方が諦めがついて良かったりするのですが、注文住宅だと満足度の閾値が高くなりがち。
結局は気の持ちようなんだよね、ということを踏まえた上で、詳細な解説に入っていきます。ちょこちょこまとめ入れておくので、流し読みで気になるところだけ読んでみてください。
人の通り道を考える
まずは人の通り道について。

リビングまでの動線を考えても、リビングの中で家族がどのように動くか、はあまり考えなかったりするよね。

ソファの置き方でも、テレビとソファの間を通るか、回り込めるかで不快感は違うもの。
生活を間取り図に書き入れる
リビングの広さを考える上で重要なことは、人の生活を間取り図に落とし込むこと。リビングで間取りを作ると、とりあえずソファセットとテレビ台、テーブルセットなどを置いてみると思いますが、この時のサイズ感は割にアバウトだったりします。
たとえば、ハウスメーカーのプレゼントして使用される間取り図の場合、少しでも部屋を快適に見せるために、実際の家具のサイズよりも小さく描かれることがあります。
間取りだと距離感・不快感まではわからない
また、図面上では実際のサイズ感が掴めず「肩幅しか人が通る隙間がない」ところでも、間取り上だと快適にすれ違えるような気がしてくるものです。初めての家づくりだと、「プロの設計の方が考えたんだから、当然大丈夫だろう」という気持ちで、ついつい自分で考えることをやめてしまうことも。私ですけど。
これは絶対に間違いで、必ず、自分で家具を設置した状態でのイメージをしてみること。役に立つのはニトリなどの家具・インテリアショップで実際の間取りをイメージした部屋を見てみること。ひたすらにサイズ感を叩き込む作業をしていきます。
実際のサイズ感で学ぶ
ニトリで6畳間にびっしり家具を設置されているところを見ると、「これで暮らすのは厳しいな」と感じることがあると思います。個人的にはニトリのサイズ感は裏切らないので、一番お手軽に頭の中のサイズ感の調整に役立ちます。
特に、ただ寝るだけの寝室とリビングでは全く感覚が異なります。ダイニングからの連続性や、窓の位置などでも印象は異なります。テレビを見る位置も30センチ違うだけでしっくりこなくなったりします。30cmくらいなら調整はできますが、気合を入れて大きなテレビを買ったら、むしろ大きすぎて邪魔になった、なんてこともあります。
広さは「何をするか」で決まる
リビングの快適な広さは、「視覚的効果」と「機能性」で考えていく必要があります。まずは、リビングでは何をしたいのか、何をする可能性があるのか、そして自分がどれくらいの広さを心地よいと感じるのか、この辺りをしっかりと調査していくことが大事だと思います。
家を建てるときは、この辺りを楽しめるかどうかで間取りの作り込み具合が変わってきます。私は面倒くさがりでここをちょちょらにしてしまいましたが、できるだけたくさんの見学会・モデルハウス巡りをして経験値を積むことが一番失敗しない近道になるんじゃないかな、と思います。
生活のサイズ感を知る上では、やはり見学会がいいと思うけど、見学会も「正解例」というわけではないので、本当にひたすらモデルケースを頭に叩き込んで、迷惑だとしても「自分が生活することを想定して動いてみる」ことを繰り返していくことが大事なのかな、と思います。
逆に、狭いとは何なのか
お金と土地に余裕があれば、「広いに越したことはない」ので、アドバイスとしては「十分な広さとなるようにしましょう」だけ連呼していればいいのですが、実際に家を建てるときは「諦めること」の連続です。

リビングの広さに関しても、「どれくらいの広さがいいか」というよりは「どれくらい狭くても自分たちは我慢できるのか」ということに尽きる。

たとえば、賃貸で生活している時って、リビングも狭いじゃないですか。場合によってはリビングですらない空間で暮らしてきているから、一軒家に引っ越すというだけで「広くなって快適になる」と盲信しているんですよね。
ただ、我々は贅沢を覚えるもので、狭くても生活できていたのに、広い部屋に引っ越すと、広さに甘えて手狭に生活するようになったりします。「少しでも広く見せるために」収納を準備しなかったり、物で溢れかえらせたりしてしまうのです。

リビングの話で言えば、「広いリビング」に憧れて、なるべくものを置かないようにしたが故に、物を置く場所がなくなって物が溢れかえるという本末転倒な事態が起きることもあります。

勢いでつけた「小上がり和室」をまるまる収納にした方がよっぽど幸せに暮らせた、なんてこともあったりして。モノを置く場所がないと、結局、物置として一部屋潰しちゃうことになるよね。
狭さとパーソナルスペースについて
狭くて不快感が強いのは、「パーソナルスペース」に人がいるような空間だと思います。
いくら家族といえど、一定距離感に人がいるというのは落ち着かない。ソファに座るにしても、二人がけと2.5はやっぱり違う。この辺りは実際にソファに座って考えるしかありませんが、同様に、「すれ違うスペース」なども丁寧に検証していく必要があります。

廊下なんかも、ものを置いたりすると印象が変わりますしね。

廊下に物を置かないように、収納を至る所に作ることが大事なんですけどね。
リビングの機能性を保つ
リビングの機能性というと、リビングを作る目的と言い換えられるかもしれません。LDKの総合的な役割として、リビング・ダイニング・キッチンをどう分配するかについては別記事にまとめました。

リビングの目的って何だろう?
- 家族の団欒の場所
- 人が集まる場所
- 応接間としての役割
- 勉強机としての役割
- テレビなどのメディアを鑑賞するところ
- 昼寝をするところ
- 休憩するところ
- 仕事をするところ
- 家事をするところ
リビングの使用用途も「これができればいいな」はいくらでも見つかるのですが、どれを諦めるか・切り離すか、というのも家づくりでは考えていかなければいけません。
だらだらする部屋を追求するなら寝室でもいい
リビングというと、「家族が集まってだらだら過ごす場所」になりがち。家の機能として本当に必要なのか、一般的な型に囚われすぎないことも大事だと思います。
「ダラダラするのは寝室だけで十分」と割り切ってもいいですし、逆に「寝室は寝るだけのところ」としてダラダラ居心地の良い空間をリビングに持ってきてもいい。

生活空間と休憩所を分けるか、動線の中に休憩スペースを設けるか。個人的には家の中は全て休憩所にしたい。とにかくだらけて生きていきたい。
ただ、そうなると「応接室」として人をお招きする役割とは共存しづらくなるので、この辺りをどう折り合いをつけていくか、がポイントになろうかと思います。

全く人が来ない家っていうのは案外難しくて、子供ができるとやっぱり誰かしらは来るようになるよね。
ワークスペースという考え方
機能性の話のついでですが、家で仕事をするときは「書斎」のようなスペースがあると良いのですが、書斎だけのスペースというのは無駄が多く、子供の勉強シーンと合わせて考えていくことになります。
子どもの学習スペースについて
これまでは、学習机と本棚を子供部屋に置いて、生活スペースと学習スペースを切り離すようにしていたけど、これだと子供は自分で勉強について組み立てていかないといけない。
実は、学習スタイルを確立するまでは親のアシストが必要なので、リビング学習の方が監督しやすいというメリットがあります。しかし、そうなるとリビングに学習スペースが必要になり、子供部屋の学習机は形骸化しやすく、最近では学習机を用意しない家庭も増えています。
「子供が自分の部屋で生活する・一人で寝る」というのも文化的な習慣であって、各家庭で「家族一緒に寝る」ことがあっても私は良いと思います。家族川の字で寝るのは楽しいですし。

子供は自然と独り立ちを意識するときが来るので、その時に言い出しやすい雰囲気と環境を作っておくことが大事だと思います。
リビング学習は手狭になりやすい
では、仮にリビングに「学習スペース」を用意すると、子供の動線として「リビングに勉強道具を持ち込む」ことになります。こうなってくると、リビングに荷物も集まってくるので、収納スペースが必要。
ここを解決するためには、本来、子供部屋にあてがうスペースをリビングにくっつけておき、年齢によって「どれくらいをパーソナルスペースとして区切るか」を自分で選択できるような空間を用意しても良いのかもしれません。
たとえば、リビングと続き間になる小上がり和室にするようなスペースを、扉やパーテーション、間仕切り壁を仕込めるようにしておくと対応の幅が広がります。間仕切り壁は工事が発生するので抵抗感が強いですが、あれは石膏ボードなどを仕込むだけなので、工事としてはシンプル。場所さえ決めておけば、配線などの課題さえクリアしておけばいくらでも対応できます。10万円くらいでできます。

個人的には子どもがずっと親と同室というのは可哀想に感じます。子供部屋があてがわれるのが当然という世代としての感覚はあると思いますが、やっぱり「自分の場所」と言える空間は必要かな、と。
この辺り育つ環境で価値観が決まるので、子供によっては「ひとりになれる空間」があれば良かったり、音も漏れないで欲しい都合があったりとさまざま。
目線を遮るのか、音も遮れるように壁を作るのかは子供の価値観と相談しながら作れるようになると良いですね。(親は何かと決めがちですが、大事なのは子供の価値観)

子供にはそんなことは判断できない、と感じるかもしれませんが、価値観を育む、というのも意識して取り組まないと、自分の価値観・尺度を持てずに周囲の評価だけを気にする子供になってしまいますからね。
リビングが狭いと感じる要因

リビングが「狭く」感じる原因と、対策などについての話をしていきます。
天井と窓の話
リビングの開放感を生み出すのは、広さだけでは限界があります。視線を逃すための「高さ」と「窓」が重要です。
窓は換気をする上でも重要ですが、リビングの場合は「心理的な閉塞感」などにも関与します。
窓がないと息が詰まる、ということ
窓の無い部屋にいるとストレスが溜まるのは研究結果から示唆されるところと、なんとなく体感的にも「窓がないと息が詰まる」ような感覚はあると思います。
建築基準法でも、居室には「床面積に対して1/7以上」の大きさの窓が必要だということになっています。窓は断熱性能の観点からすると小さいに越したことはないのですが、採光や開放感という面では大きく取ったほうが気持ちがいいと感じられるようです。
心理的な側面へのアプローチとしては、窓の無い空間でも「擬似窓」として高精細なディスプレイを準備して置いておくことで心理的な効用が得られることもわかっていています。

大きめのディスプレイほど効果が得られそうだ、という見解がありますね。
大きめの窓で部屋を開放的にする
リビングがどうしても狭く設計せざるを得ない時は、ベランダ・バルコニーなどと連続性のある作りにして外部にもリビングの延長となる空間を用意することで対応することもできます。
窓のせいで視線が気になる
一方で、外部からの視線が気になって窓を開けて置けない、結局カーテン・ブラインドを閉めたまま生活してしまう、ということも起こり得ます。
部屋での生活を見られたくないから、リビングは2階にするという選択肢もあるくらいです。

開放感を天井に求める
一般的な天井高は2m20cm〜2m40cmと言われています。人間は上方に約60°ほどの視野が得られるので、身長の影響も受けはしますが、一般的な天井の高さであれば視線に天井が入ってくることになります。
視界の中に壁や天井のような圧迫感のある構造物があると、塞ぎ込んだような気持ちになってしまいます。閉所恐怖症はまた別の心理的な要因が関係しますが、狭くて閉鎖的な空間というのはそれなりにストレスを感じるものです。
3m近い天井高になると、天井が視界にほとんど入らなくなります。また、吹き抜けや天窓を設けることでより開放的な印象を与えることもできます。部屋の広さを変えることができない場合、閉塞感を和らげるために天井を高くするという対応も考えられます。部屋は広くなりませんけどね。
天井を意識させない部屋にする
天井の高さはそうそう変えられませんが、リビングに置く家具の背丈を統一させたり、少し低めのものを置くようにすると、部屋がスッキリと見えるようになります。人間は自然と「目を留めるもの」を探すもので、モノが下にあれば当然視線も下がります。
それでも、立って行動することが多いリビングの場合は、やはり少し高めに天井高を設計すると閉塞感を和らげられていいと思います。勾配天井で部分的にも高くすることで視線を逃す空間を作ることができます。
照明・日差しの話
窓にも関係することですが、照明の取り方によってもリビングについて考えることはあります。
フォーカルポイント
まずは目線を操作すること。先程の天井の話にも通じるところです。
これは家具の配置にも多分に影響しますが、人の集中力は「変化」に意識を持っていかれます。意識的に照明・灯りを作ることで、フォーカルポイントを作ることはできます。
光は色合いに変化をつけたり、強弱をつけることに役立ちます。逆に、意識を向けたくないところには間接照明などを取り入れてぼんやりと馴染ませる効果を生んだりすることもできます。
照明ってのは本当に奥が深くて、照明アドバイザーとかに憧れますね。
照明を自動で管理する話
照明に関しては、今後はスマートホーム化して、自然採光とのバランスを見ながら自動で明るさ・色合いを調整してくれるようになってくると考えられます。色合いの調整などが可能なLED電球なども登場しているので、電気をつけたり消したりするだけではない、新しい家での照明ライフを演出してくれる未来が待っていそうです。

日差しは明るさだけじゃないということ
採光のはなしのついでに、我が家のリビングは夏場にものすごい暑さになります。2階リビングの影響もあり、採光の良い南側という影響もあり、とにかく暑い、暑すぎます。
日差しとテレビの話
日差しのデメリットとしては、まず「テレビへの反射」があります。テレビの奥位置と窓の位置によっては、太陽光が反射してテレビが見れなくなります。当然、ブラインドなどを占めて対応することになるのですが、リビングだと遮光の甘いおしゃれなカーテン・ブラインドを準備している場合もあり、日差しが強すぎてリビングが明るすぎる、という問題に繋がる可能性があります。
我が家はリビングに障子を入れて良かったと思いますが、障子は「程よく明かりを通してくれる」とも言えるし、「夏の日差しを遮りきれない」とも言えます。

日差しと熱の話
日差しは日向ぼっこなどをするときには気持ちのよい天然の布団になってくれる分けですが、日差しはやはり熱を持っています。天窓や高窓などをリビングに設置する方も多いと思いますが、遮光対策も念頭に入れておかないと、メインで過ごすリビングでありながら、もっともエネルギー効率の悪い部屋になって電気代が余計にかかるようになってしまう可能性があります。
空間とメディア(映像と音)の話
日差しの話で「テレビが見えづらくなる」という話をしたついでに、リビングとメディアに関する話もしておきます。
音楽視聴の空間としては劣悪
音響が好きな方はリビングで音楽を聴いたりはしないと思いますが、音楽を聴く空間としてはリビングはあまり良くないと考えられています。
リビングはどうしても余計な家具などを設置するので反響が計算しづらく、ソファで聴くのかダイニングなのか、あるいはキッチンで聴くのか、リスニングポイントが定まらないところがあります。
でも、音響側が進化して自動で最適化してくれるように
とはいえ、そこまで拘って音楽を聴くことがなければ、リビングにシアターセットを組み上げて映画鑑賞などをする場合もあります。最近は空間音響の音源(Dolby Atomosなど)や機材・スピーカーも充実しているので、簡単に設置するだけでスピーカー側が最適化してくれるものもあります。つまり、そんなに拘らなくてもリビングで手軽に音楽が楽しめるようになりました。

私の場合は、もうHomePodだけで手軽に音楽を楽しめるだけで満足するようになりましたしね。

視聴空間としてのリビング
リビングに大型のテレビを置いて、家族みんなで映画鑑賞をする、なんとも幸せな光景です。
この点に関しては特に文句のようなことを言うこともないのですが、テレビのサイズに関してはちょっと気をつけたほうがいいです。
視聴距離とリビングの広さ
リビングにテレビを設置する際、設置するテレビの高さと視聴距離が重要です。テレビはどんどん高精細となり、薄型になったのでテレビの奥行きがなくなり画面が少し壁際によったこと、視聴距離によって疲労感となったりすることも減ってきたので、言い換えるとどんな部屋でも大画面が推奨されるようになりました。

とはいえ、流石にテレビとの距離が近いのに大画面にしても、視野の問題で見づらくなるだけですけどね。
LDKの場合、リビングの広さが少し曖昧になってしまいますが、ソファとテレビの距離を考えて、高さと視聴距離を割り出して最低なテレビサイズにするようにします。
テレビサイズの決め方
| 部屋の広さ | 視聴距離 | 画面サイズ |
| 4.5畳 | 0.8m | 43V |
| 6畳 | 0.9m | 49V |
| 8畳 | 1.0m | 55V |
| 10畳 | 1.2m | 65V |
| 16畳 | 1.4m | 75V |
家具・家電の設置位置
テレビの話のついで、このような大型家電・家具を置く際の注意点を簡単に説明します。コンセント位置に関する記事も書きましたので、こちらもチェックしてみてください。

大型家電・家具の搬入は命取り
リビング全体の間取りを考える際には、家具・家電を実際に置いた状態でシミュレートする必要があります。テーブルの位置などは「実際の部屋に住んで大きさを考えよう」と思うかもしれませんが、最低でも間取り上で大きさ、置く場所は想定しておく必要があります。
間取り図を決める際に、ハウスメーカーなども参考としてテーブルなどを置いたシミュレーション図を作ってくれる場合もありますが、この時にテーブル・ソファのサイズもしっかりと指定しておくほうが無難です。
家具・家電を置いてみないと、扉の開け閉めやテレビとの距離感、コンセント位置などの想像がしにくいので、とにかく一度は家具・家電を置いた状態での生活動線を作り上げた方がいいです。絶対に。
今は、AR技術の進化が凄まじくて、家具を置いた状態での映像が作れたりもしますけど、何にせよ、どの家具・家電を置くかは間取り図の打ち合わせの段階でしっかりと決めた方がいいです。ハウスメーカー側は余計に悩ませる分工程が遅れるので、「当たり障りのない図面」でお茶を濁そうとしますが、この辺りは自分の家、自分で責任を持って考えていく必要があります。
他の部屋の目的と兼務するが故の手狭感
リビングを多目的に使用する場合、書斎や子供部屋の役割も担うことになります。他の部屋との兼ね合いによる注意点などを簡単にまとめておきます。
ワークスペースをリビングに
たとえ家族とはいえ、一人きりになれるような空間があると便利です。ワークスペースの話にもなるのですが、リモートワークが加速することを考えると、「仕事に打ち込める部屋」は今後、必須になってくると思います。
職場のチームくらいのカンファレンスならまだいいのですが、今後は他社との商談なんかも自宅で対応するケースが増えてくると思います。その時に、自宅で落ち着いて取引できるような環境は必要になってきます。
家族団欒のスペースとしてリビングを広く取るのはもちろんいいことだとは思いますが、家族みんなが使うスペースを仕事で独占するわけにもいきません。ワークスペースをリビングの中に共存させる方法はあると思いますが、この辺りを意識した間取りを考えていくことは今後重要だと思います。
子供部屋の消失
子供が勉強する寛容として子供部屋を用意していた家庭も多かったと思いますが、最近では「リビングで宿題に取り組ませた方が効率が良くなる」みたいな意見も出てきていて、学習机もいらない、参考書は電子化して嵩張らなくなる、なんてことを考えると、子供部屋っていらないのかな、という意見も聞かれるようになってきました。
子供専用のスペースというよりは、成長に合わせて多目的に使用できる空間を準備しておくことで対応する準備をしておけばいいと思います。とはいえ、そうなると「子どもの発達段階に合わせたプライバシー」についても少し考えておきたいところ。
部屋じゃなくても子供の自立心が育つ空間を
先ほど、リビングにワークスペースを準備する話をしましたが、子供が集中して何かに打ち込んだり、自分で自由にできる空間というものは用意しておく必要があると思います。簡易的な間仕切りなどで対応するか、簡易な工事で壁を作れるように準備しておくか、リビングの一区画を仕切れるように扉を仕込んでおくか、方法はさまざまではありますが、広いリビングに空間としての可動性を仕込んでおけると、対応する幅は広げられそうです。
リビングに小上がり和室などをつける場合も、「誰がこの小上がりを使うのか」を将来性も考えて検討するといいと思います。子供が小さい時には寝っ転がって遊べるスペースとして、子供が勉強する時になったら小上がりじゃなくてしっかりと壁と扉を用意して子供部屋のようにする。子供が独り立ちした後は、客間として利用する。みたいな感じですね。小上がりにしちゃうと大変だけど、最初から扉などをつけておくと工事などしないで対応はしやすくなる。
家族の団欒としてのリビングの役割
最後に、家族の団欒としてのリビングの役割を書いて終わりにします。

結局、色々書いたけど、リビングっていうのは「家族が集まる場所」と言うことだよね。
リビングの機能とは、「家族で集まって何をするか」ということに行き着くと思います。それが食事などに限定されるのか、あるいは家族で集まってゲームを楽しんだり、映画を見て体験を共有したりするのか。
自分がだらだら過ごすのか
まず、突き詰めれば家族がだらだら過ごすためのリビングを設計するなら、こどもが多少散らかしても気にしないようなリビングを目指します。ズボラな片付けで、おもちゃも箱に入れてすっとしまえるような形にしておくといい。小上がりなどのリビング付属部屋みたいなところを遊ぶ部屋にして、客人が来たら隠すだけだとストレスが減ります。

自分が子供ができてからの客人てのも、大体子連れだから、究極、子供が過ごしやすい部屋が客人にとっても良かったりするんですけどね。おしゃれママは知らん。
つまり、自分たちがだらけられるスペースこそ、自分たちも家族も、そして気の置けない友人たちと過ごす上では大事な指標となるのかもしれません。
作業部屋としての役割を追求するか
今後、在宅ワークが進むのは間違いないとして、リビング周りはもう「ビシッと作業する空間」に作ってしまうのも正解なのかな、と思います。

私は基本的に在宅で仕事をするようになりましたが、やはりメリハリは大事。だらっと過ごすリビング設計だと、仕事中もだらっとしがちです。
リビングに書斎やワークスペースとしての役割を持たせるなら、いつ、誰がきても商談ができるくらいの「かっこいい・綺麗なリビング」を心がけます。作業効率も高まります。
子供たちも、勉強の際にはワークスペースで宿題などに取り掛かり、メリハリを持って学習に打ち込んでもらいます。食事が終わったら、たとえば隣接する遊び部屋・趣味部屋などで息抜きするようにして、リビングは「最大効率で作業する場所」としての地位を固めます。

私は自分が書斎にこもったほうが作業しやすいので、リビングを巻き込むことはないのかな、と思いますが、子供がちゃんと勉強する環境としては、この「メリハリリビング」タイプがいいんじゃないかな、と思います。
リビングに最適な「広さ」まとめ
さて、色々と書きましたが、何かしら数値的なところで「リビングの広さ」についての答えを出していきます。
8畳あれば大体できる
まず、私の体験談としては、8畳あればなんとかなります。ソファセットなどおくと手狭に感じるくらいではありますが、真ん中にこたつでも置いて家族で食事だってできます。
8畳の生活空間を基本として、まずは8畳で生活するために必要な「収納」をビルドしていきます。収納さえしっかりしていれば、8畳リビングでもおしゃれで快適に過ごすことができると思います。逆に、10畳あって収納ない場合は、生活空間に物が溢れるようになるので、広さほど快適ではない生活になると思います。
ダイニングもあるなら10畳
ダイニングテーブルを置いてリビングにソファセットを置く、の限界値は10畳かな、と思います。ダイニングセットかソファセットを諦めれば、10畳は快適な空間になります。欲を言えば、12畳は欲しいなとは思いますが。
キッチンと続き間にしなければ、LD部分で12畳はかなり広く感じるはずです。逆に、全ての機能性をLDに集約した場合、つまりダイニングとリビングをそれぞれ独立して機能させようとすると、10畳はかなり厳しい数字になります。
LDKワンセットの場合は14畳が限界値
この14畳もキッチンの形によるところがあります。対面式だとかなり厳しい。LDKの壁一面をキッチンとして、キッチンの背後にダイニングセットを調理台と兼務し、リビングに生活空間をある程度確保すればそれなりに快適な広さになりそうです。ただ、キッチンとダイニングがほぼ一体、しかもリビングとの境界も曖昧になるので、嫌がる人はいそうです。
LDKの快適な下限値は16畳+収納
当サイトの結論としては、ストレスなくLDKが機能する下限値は「収納を別途用意しての16畳」とします。収納量は各家庭によってまちまちだとは思いますが、平均的なクローゼットサイズの棚があるだけでもだいぶ違うと思います。

おそらく、生活空間が18畳や20畳になっても、収納がないとそれほど広さのメリットは感じられないと思います。モノが仕舞い込めないと、そのモノが生活空間に飛び出してくるので、これは案外にストレス。視界の圧迫にもつながります。





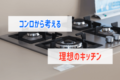

コメント
「ベッド ソファ 椅子」に関する最新情報です。
新たに登場した『どこでも座椅子』は、ソファを置くスペースがない方に最適なアイテムです。この座椅子は床だけでなく、ベッドの上でも使用でき、ソファのようなくつろぎ空間を提供します。背もたれがしっかりしており、ふっくらとした座面で快適な座り心地を実現。14段階のリクライニング機能により、好みの角度でリラックスできます。コンパクトで軽量なため、持ち運びや収納も簡単です。お部屋の限られたスペースを有効活用し、心地よいおうち時間を楽しむことができます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000290.000039747.html
「記事 メディア 記事 閲覧」に関する最新情報です。
電子工作メディア「fabcross」が2023年3月31日に閉鎖されることが発表され、4月1日以降は記事の閲覧ができなくなる。fabcrossは2013年10月にオープンし、ものづくりコミュニティに支持されてきたが、閉鎖の理由は明示されていない。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2503/18/news175.html
「記事 メディア 記事 閲覧」に関する最新情報です。
電子工作メディア「fabcross」が2023年3月31日に閉鎖され、4月1日以降は記事の閲覧が不可能になることが発表されました。このメディアは2013年にオープンし、ものづくりコミュニティに支持されてきましたが、閉鎖の理由は明示されていません。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2503/18/news175.html
「ガザ 攻撃 映像」に関する最新情報です。
ガザ地区は、2023年10月から2025年1月までの間にイスラエルの攻撃によって甚大な被害を受け、4万7000人以上のパレスチナ人が命を落とし、11万人以上が重傷を負った。ドローン映像では、攻撃前の2023年6月には活気ある街並みが広がっていたが、停戦が発効した2025年1月19日には、ほとんどの建物が破壊され、がれきの山となっている様子が確認できる。ガザの人口の90%に当たる約190万人が避難を余儀なくされ、数十万人が衛生状態の悪い避難所で生活している。国連によれば、ガザの住宅の9割が破壊または損壊され、学校や病院も被害を受けている。停戦後も、ヨルダン川西岸ではイスラエル軍の攻撃が続いており、緊張が高まっている。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_67919694e4b06448cdc84fed
「ブラインド 断熱 遮光」に関する最新情報です。
コメリは、独自のL型スラットを採用した「遮光断熱できる L型ブラインド」を新たに発売しました。このブラインドは、L字型のスラットによりシャッターのようにしっかりと閉まり、高い遮光性と断熱性を実現しています。これにより、冷暖房効率の向上が期待できます。また、室内に調和する壁紙風の布地調プリントが施されており、カラーはベージュとグレーの2色が用意されています。
https://www.s-housing.jp/archives/374169
「バレエ トレーニング パーソナル」に関する最新情報です。
「めるもバレエ」では、2024年12月から2025年2月末まで、綱島高田に新設されたプライベートレッスン専用スタジオでバレエ・マシンピラティスの個別指導を行います。この期間中、各メニューが通常料金から1,000円割引されるキャンペーンを実施します。プライベートレッスンは、正しい姿勢や動作を習得するために非常に効果的であり、個々の技術的課題に対しても集中して指導が行える環境が整っています。
プライベートレッスンは高額ですが、特に大人になってから運動を始める場合、正しい動作を身につけるためには定期的な個別指導が重要です。生徒自身が理解し、努力することも必要ですが、マンツーマンでの指導がそのプロセスを加速させる可能性があります。プライベート空間での指導により、他の生徒の目を気にせず、安心して技術向上に取り組むことができます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000132510.html
「階段 使う 調査」に関する最新情報です。
この調査は、全国の主婦を中心に1000人を対象に行われた「駅の階段」に関するアンケートです。結果によると、駅の階段を使うのが好きな人は19%にとどまり、31%は嫌いと回答しました。階層移動の手段としては、56.6%が「エスカレーター」を選び、32.5%が「階段」、8.8%が「エレベーター」となりました。階段を利用する理由としては、「筋力アップ、健康のため」が28.3%で最も多く、次いで「階段を使うのが一番早いと思うから」が16.5%でした。また、駅の階段で気になる点は「歩きやすさ」が26.2%と最も多く挙げられました。フリー回答では、階段利用時の困難や思い出が寄せられ、多くの人が階段の利用に対してさまざまな感情を抱いていることがわかりました。バリアフリー法に基づき、利用者の多い駅にはエレベーターの整備が進められています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001723.000080271.html
「学習 スペース 学習 スペース」に関する最新情報です。
愛知県半田市では、冬休み期間中に中学生・高校生向けの「学習スペース」を瀧上工業雁宿ホールに開設します。この取り組みは、地域の「子どもの居場所」づくりの一環であり、安心・安全な学習環境を提供することを目的としています。過去の試行では高い満足度が得られたため、今後も定期的に開設することが決定されました。市内の若者の学習ニーズに応えるため、利用方法に関する会議も開催される予定です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000137040.html
「長岡 花火 映像」に関する最新情報です。
長岡市のアオーレ長岡シアターで、11月25日から12月7日までの期間限定で「長岡花火8K3D映像上映会」が開催されます。このイベントでは、株式会社NHKテクノロジーズから寄贈された高精細映像を使用し、2024年長岡まつり大花火大会の代表的な花火を専用のメガネをかけて観覧できます。上映時間は約22分で、料金は無料ですが事前予約は不可です。また、12月9日からは新たに4K高画質の長岡花火コンテンツも登場します。詳細はシアターのホームページで確認できます。
https://www.niikei.jp/1295214/
「松山 ポスト 視聴」に関する最新情報です。
俳優の松山ケンイチさんが、NHKの連続テレビ小説「虎に翼」に出演していたにもかかわらず、これまで朝ドラを視聴していなかったことを告白しました。彼は全130話を一気見することを宣言し、視聴後に感想を1話ずつ投稿するという新たな試みを始めました。彼の感想は多くのファンから「贅沢すぎる」と称賛され、視聴記録に対する期待が高まっています。松山さんは、最終回を迎えた後に視聴を始めた理由として、共演者の伊藤沙莉さんからの勧めを挙げています。このドラマは、日本初の女性弁護士を主人公にしたオリジナルストーリーで、松山さんはその中で重要な役割を果たしました。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_66f9f216e4b06bc72dbb5c82
「16 iphone iphone 16」に関する最新情報です。
新型iPhone 16シリーズの発売が近づく中、ReYuu Japanが実施した購入意識調査の結果が発表されました。iPhone 16の購入予定者100人に対する調査では、最も人気のあるモデルはiPhone 16で、63人が購入を予定しています。カラーに関しては、iPhone 16/16 Plusではブラックが23票で1位、ホワイトが22票で2位、ピンクが12票で3位となりました。一方、iPhone 16 Pro/Pro Maxではブラックチタニウムが9票で1位、ナチュラルチタニウムが7票で3位にランクインしています。全体として、落ち着いた色味が好まれていることが分かります。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_66e3ed15e4b02a333c0b986d
「16 iphone iphone 16」に関する最新情報です。
新型iPhone 16シリーズの発売が近づく中、人気のカラーランキングが発表されました。購入予定の100人を対象に調査した結果、iPhone 16の機種別人気は、1位がiPhone 16(63人)、2位がiPhone 16 Pro(18人)、3位がiPhone 16 Plus(10人)、4位がiPhone 16 Pro Max(9人)でした。
カラーに関しては、iPhone 16/16 Plusで最も人気があったのはブラック(23人)、次いでホワイト(22人)、ピンク(12人)、ティールとウルトラマリン(各8人)でした。また、iPhone 16 Pro/Pro Maxでは、ブラックチタニウムが最も人気(9人)、次いでナチュラルチタニウム(7人)、ホワイトチタニウム(6人)、デザートチタニウム(5人)となっています。全体的に、落ち着いた色味が好まれていることが伺えます。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_66e3ed15e4b02a333c0b986d
「石丸 メディア 伸二」に関する最新情報です。
石丸伸二氏の実父がメディアに対する本音を明かし、「人の粗探しして、あんたらを打ちのめしたいよ」と発言。石丸氏のメディア対応が批判を受けており、その素顔や考え方についても議論が広がっている。
https://gendai.media/articles/-/133651
「竜巻 アメリカ 映像」に関する最新情報です。
アメリカ中西部のネブラスカ州で撮影された竜巻の映像が話題となっています。映像では、竜巻が建物を根こそぎにして屋根を巻き上げる様子が捉えられており、衝撃的な光景が広まっています。この竜巻によりアメリカ中西部では複数のけが人が出たほか、オクラホマ州などでも竜巻による被害が報告されています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS80LzgvMzExXzhfcl8yMDI0MDUwOF8xNzE1MTI0ODgzMDgwODk40gEA?oc=5
「シップ メディア メディア シップ」に関する最新情報です。
新潟県内のGWイベント情報として、5月3日に「ヒラメキパーティーinメディアシップ」や「妙高サンシャインランドのキャラクターショー」などが開催される。新潟市内や他地域で様々なイベントが予定されており、詳細は記事内で紹介されている。
https://www.niikei.jp/1038981/
「bsn bsn メディア メディア」に関する最新情報です。
BSNメディアホールディングスとテクノクラフトが業務提携し、ゴルフカートナビ事業などを展開するテクノクラフトの一部株式を取得したことが発表された。この提携により、両社は幅広いサービス提供を目指し、健康管理デバイス普及など新たな取り組みを進める計画となっている。BSNグループは放送事業や技術開発、コンサルティング事業などを展開しており、提携によって安心・安全・快適・利便性の提供を拡大することを目指している。BSNメディアホールディングスは2023年12月15日にテクノクラフトの発行済株式総数の2.0%相当を取得している。
https://www.niikei.jp/988219/
「パイシュー ナルス ナルス パイシュー」に関する最新情報です。
原信ナルスの「さくさく♪パイシュー」の食感が話題になっており、その実際の「さくさく」感を検証した結果が驚きをもたらした。商品のパッケージには警告文があり、外見からは特別な食感を感じられなかったが、実際に食べてみるとどうだったのか、詳細が記されている。
https://www.niikei.jp/983959/
「灯り 空間 照明」に関する最新情報です。
照明計画術を活用して、高品質な光源を使用し、明るさや色温度を調整することが重要である。ダウンライトを使用してダイニングテーブルやソファテーブルを照らし、間接照明を使って空間の隅をホワイトアウトさせることで広がりを感じさせる効果がある。建築空間を認識する際に視覚の影響は大きく、光の反射が重要である。
https://www.s-housing.jp/archives/342050
「ハサミ 映像 えら」に関する最新情報です。
1月26日に、魚のえらからカニのハサミのようなものが出ている映像が拡散されました。しかし、この映像の信憑性には疑問があります。撮影者が魚のえらにハサミをつけた可能性や、映像が編集された可能性もあります。さらに、この映像には福島県への差別や偏見を助長するコメントが多数ついており、注意が必要です。この映像についての他の情報や同様の魚の映像は見つかっていません。したがって、この映像が本物の魚であるという根拠はありません。差別や偏見を助長するコメントの拡散も問題です。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/fukushima-dema_jp_65c32dd4e4b0dbc806aea69d
「すぎ 10 news」に関する最新情報です。
2024年、寒すぎるリビングを暖めるために、あるガジェットを導入した結果、快適に過ごせるようになった。以前はリビングの暖房を23〜25度に設定していたが、今年は20度以上に上げることはなかった。この暖冬の影響もあるかもしれないが、導入したガジェットの効果が大きかった。また、仕事部屋の寒さ対策にも電気ひざかけ+フットヒーターを使用している。以前は着るこたつ系のガジェットを使っていたが、立ち上がったり歩いたりするのが大変でやめた。長年悩んできた寒さの問題に、この冬ガジェットの進化が光を与えてくれた。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2401/29/news107.html
「映像 le le sserafim」に関する最新情報です。
韓国の人気ガールズグループLE SSERAFIMの新曲映像が話題となっています。公開された映像では、メンバーのSAKURAが鼻血を出し、HONG EUNCHAEが階段から落ちるという衝撃的なシーンがあり、視聴者に強烈なインパクトを与えています。映像のセリフには、「自分らしく生きているってだけの理由でその人をけなしていいと思う」「運が良い人たちは悪口を言われてもいいの」「人生の半分は苦しみだろう」といった強いメッセージが含まれています。所属事務所は、「LE SSERAFIMの堂々とした姿の裏に存在する不安や悩みが率直に語られている」と説明しており、ファンからも反響が広がっています。LE SSERAFIMは今後も活動が期待されており、アメリカの野外音楽フェスティバルにも出演予定です。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65b34607e4b014b873b0b044
「こたつ ソファ 一人」に関する最新情報です。
最新のこたつ5選を紹介する記事では、電気こたつの省エネ性と暖かさが再び注目されていることが述べられています。こたつは部屋全体を暖めるエアコンと比べて、スポット的に暖まる場面に適しており、節電にも貢献します。また、一人用のこたつが増えており、洋室にも合う製品やオフシーズンに出しっぱなしにできる製品も登場しているため、こたつを選択しやすくなっています。紹介されているこたつの中には、一人用でソファの上にも乗せられる超小型のこたつや、ソファ座りや床座りどちらでも使用できる2段階で高さ切り替え可能なこたつ、2人掛けソファでも使える横長のテーブル型のこたつ、足を包み込んで温めることができる「巻くコタツ」などがあります。各製品の特徴や価格も紹介されています。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_special/kaden__trend/1561621.html
「積み 積み 積み 階段」に関する最新情報です。
「ぷよぷよ道場~階段積みと鍵積み編~」は、eスポーツのぷよぷよのプレイ方法について解説した記事です。記事では、階段積みと鍵積みのメリットや組み方について詳しく説明されています。階段積みはドミノ倒しのような連鎖を作る方法であり、ネクストやネクネクを見ながら効率よく組んでいくことがポイントです。鍵積みは特定の手順に従って積んでいく方法であり、その手順を理解することが重要です。初心者にとっても役立つ記事となっています。
https://chara.ge/puyopuyo/puyopuyo-e-sport-kaidandumi-kagidumi/
「甘い ng ng バランス」に関する最新情報です。
「甘いものをいきなり口にするのはNG!」という記事は、バランスのいい食事が難しい場合でも、脳のために守るべきルールについて解説しています。糖を食べたのに低血糖になる理由や、アクセスランキング、おすすめの記事も紹介されています。記事では、脳の健康を保つためには、食事のバランスだけでなく、甘いものを食べる際には注意が必要であることが述べられています。また、糖質を摂取することで血糖値が一気に上がり、その後急激に落ちることが脳にとって負担となることも説明されています。
https://gendai.media/articles/-/121985
「オジサン 子供部屋 子供部屋 オジサン」に関する最新情報です。
この記事は、32歳で実家暮らしの正社員である「子供部屋オジサン」の週末の遊び方を紹介しています。彼は自称「最強の子供部屋オジサン」として知られており、週末にどのように遊んでいるのかを公開しています。記事では彼の日常や週末のルーティン、そして彼の友人である佐藤さんとの対話を通じて、彼の週末のライフスタイルを探っています。彼は一人暮らしの佐藤さんと比べて、自分の安定した生活に満足しており、刺激的な人生よりも安心感を求めているようです。記事では、彼の週末の過ごし方について詳しく紹介しています。
https://gendai.media/articles/-/119760
「スイーツ スイーツ 愛知県安城市 メディア」に関する最新情報です。
メディアで話題の「いつでもスイーツ」が愛知県安城市に新店舗をオープンしました。このスイーツは24時間営業で、365日いつでも購入することができます。株式会社Createurが展開しており、全国に100店舗以上あります。新店舗は11月4日にオープンし、オープニングイベントも開催されました。来店者には限定の旅行チケットや国産牛ステーキが当たる抽選会も予定されています。また、愛知県安城市の他にも広島県中区や東海エリアの鈴鹿店、豊橋店、豊田店など、全国に4店舗目まで展開しています。このスイーツはオンラインで購入することもでき、送料がかかりますが、全国に届けられます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000119767.html
「iphone pro 14」に関する最新情報です。
iPhone 15 Proは、iPhone 14 Proからの進化ポイントがいくつかあります。まず、USB-Cポートによる拡張性が向上しており、高速なデータ転送や外部ストレージの利用が可能です。また、Vision Pro用の空間ビデオやアクションボタンの追加など、新しい機能も搭載されています。さらに、光学5倍ズームに対応した望遠レンズが追加され、カメラ機能も強化されています。iPhone 15 Proは軽くなり、持ちやすさも向上しています。これらの進化ポイントを考慮して、iPhone 14 Proを持っている人が買い換えるべきかどうかは個人の判断になります。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKWh0dHBzOi8vZ29yaS5tZS9pcGhvbmUvaXBob25lMTVwcm8vMTQ5Njk20gEA?oc=5