断熱材についてご説明します。
まず、断熱材を素材で選ぼうと考えている方。

「あそこの工務店は〇〇が標準だからいい」とか、「ハウスメーカーがいいと言ってたから」なんてことで、良い悪いを決めてませんか?
断熱性能の高い断熱材を使っても、厚さも施工も不十分なら効果を発揮しません。
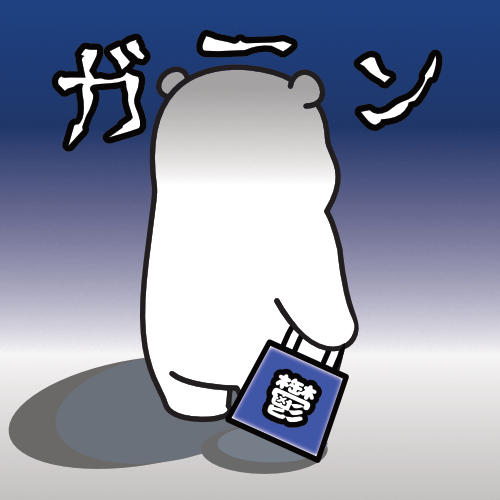
どれだけいい断熱材を使ったところで、窓や扉、換気などの家の総合性能が悪ければ、効果は半減以下です。
もう一度、断熱材について考え直してみませんか?
2023年以降は断熱性能に関しては淡々とこちらのページで加筆修正しています。最新情報が欲しい場合はこちらも合わせてご確認ください。

- 断熱材はグラスウールでも性能は十分
- 大工による施工技術が影響しやすい
- 変だなと思った時に伝えられる勇気が大事
断熱材に悩んだらまずは硬質ウレタンフォームを検討せよ
私が硬質ウレタンフォームを推薦する理由は、わたしの経験に基づきます。
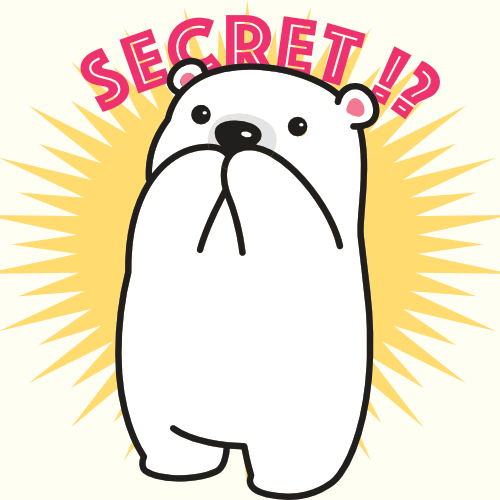
ぶちくまの家はロックウールという、まぁグラスウールの強化版みたいなやつが採用されています。
素材は安いのですが、安い分、程度の厚みを保ちやすく、断熱効果も期待できます。
断熱材のあれこれを比較してみる
まずは断熱材ってどんなものがあるの、ということから調べていきます。
断熱材と火事や防音性についての比較
| 断熱材比較 | 断熱材 | 不燃性・防火性 | 防音・吸音 |
| 繊維系断熱材 | ロックウール | ◎ | ◎ |
| – | グラスウール (高性能16K) | ◯ | ◎ |
| – | グラスウール(10K) | ◯ | ◎ |
| 発泡プラスチック系 | ビーズ式ポリスチレンフォーム 押出式ポリスチレンフォーム フェノールフォームなど | △ | △~◎ |
| – | ウレタンフォーム など | △ | △ |
発泡プラスチック系は火事に弱い、なんてことが言われますね。

まぁ、家具も建具もほとんど木だから、火事の時は断熱材の防火性ばかりを気にしていても仕方がないけどね。

ただ、家事の際に「燃えやすい」素材であったり「有毒なガスが発生する」ものだと、生存する可能性が下がるのだから、やはり気にはしておきたいよね。
断熱材の性能|外環境との適応力
| 断熱材比較 | 熱伝導率 | 熱抵抗値 (厚さ100mmの場合) | 防露対策 | 防蟻性 |
| 繊維系断熱材 | 0.038 | 2.6 | ◯ | ◎ |
| – | 0.038 | 2.6 | ◯ | ◎ |
| – | 0.05 | 2.0 | ◯ | ◎ |
| 発泡プラスチック系 | 0.020~0.039 | 5.0~2.6 | ◎ | △ |
| – | 0.034~0.04 | 2.9~2.5 | △ | △ |
熱伝導率は、当然、熱を伝えない方が断熱材としては効果が高いと言えます。
この熱伝導率と、断熱材をどれくらい使ったか(厚み)によって、熱抵抗値がもとめられます。

つまり、熱伝導率がよい、断熱性能の高い素材も、厚みが不十分であれば効果は弱まってしまいます。
ただ、壁の厚みは柱の厚さに応じて決まっているので、仕込める断熱材の厚さにも限りがあるので注意が必要です。
断熱材と価格・材料の比較
| 断熱材比較 | 価格 | 主な工法 | 原料 |
| 繊維系断熱材 | 1 | 充填 断熱 | 高炉スラグ、 玄武岩など |
| – | 1 | 充填 断熱 | ガラス |
| – | 0.8 | 充填 断熱 | ガラス |
| 発泡プラスチック系 | 2~3 | 外張り 断熱 | ポリスチレン樹脂、 フェノール樹脂など |
| – | —- | 充填 断熱 | ウレタンなど |

さすが、ロックウールの会社が用意した資料だけあって、とてもロックウールが魅力的に見えますね!
実際、私も、ロックウールを採用したこと自体は後悔していません。安いし、断熱性能は十分だし。窓や扉、換気性能だって普通だし。

断熱材ばっかりいいものを使っても仕方がないのと、後述する「施工力に左右される」ものなのに、施術者を知らない状態で契約するんだから、気にしすぎても仕方がないとも言えます。
後悔|施工不良が気になりすぎて神経すり減った
これは断熱性能は十分なのですが、なにせ施工が悪かった。

グラスウールってのは気密性を保つために防湿シートというのを貼るのですが、これがガタガタで、隙間だらけ。
指摘しようと思ったが、まだ日が空いているので、

さすがにこれはやり直すよね?
という気持ちでいたらいつのまにか、石膏ボードが貼られていて、確認できないままに、最終工程まで進んでしまいました。
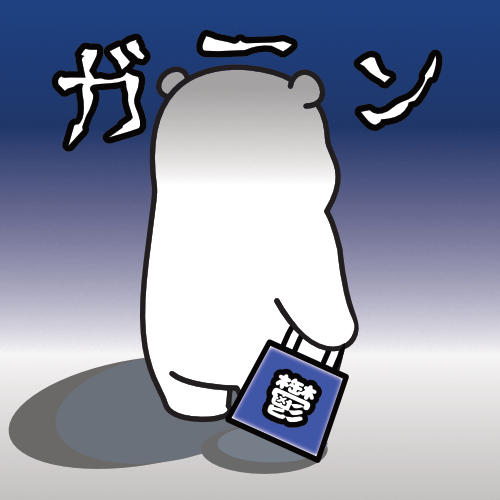
いっときゃよかった、という後悔と今後の断熱の不安を考えると、性能云々よりも、施工が安定している硬質ウレタンフォームの吹き付けがよかった。
絶対に確認した方がいいグラスウールの正しい施工方法
まずは、しっかりとした知識で「確認・チェック」できるようになりましょう。

自信がないと大工さんに指摘できないよ!

どこもこんな感じですよ
結局、こう言いくるめられた時に、ちゃんとやり直しを伝えられるかが、安心してグラスウールを使えるかのキーポイントとなります。
グラスウールが正しく施工されると圧巻

こんな感じで、悪い施工の場合は雑な印象を受けるので、違和感を感じるはずです。


隙間があったらおかしいな、と思っていいサインです!
グラスウールは施工さえしっかりされればいい断熱材
わたしはグラスウールは好きです。
ただ、大工さんの腕前次第、あるいは現場監督が無知であれば、こうして断熱・気密効果のない「名ばかりの高断熱・高気密住宅」が出来上がってしまいます。

わたしの後悔は、自信がなかったばかりに指摘できなかったことです
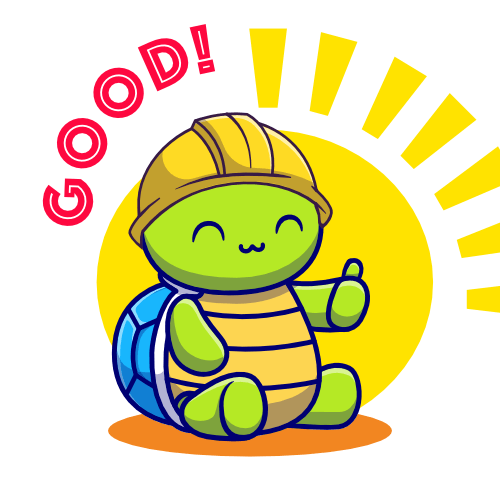
自分の家ですから、少しでもモヤモヤしないためにも、いまのうちにしっかり学んでおきましょう!
家を建てる前に知っておきた断熱材のこと
断熱材の基本的な知識をまとめておきました。できれば、家を建てる前に知りたかったことばかりです。
断熱材とは空気層をつくって熱の交流を最小限にすること
読んで字のごとく、断熱材は家の内部と外部を遮断して、熱の移動を最小限にすることで、夏は涼しく、冬はあったかにするためのものです。
発泡スチロールみたいなもので家を包み込んでいるイメージで間違い無いです。副次的に、遮音効果や、不燃性を生み出すものが多いです。
2種類の断熱方法
まずは、ざっくり、中に断熱材を詰めるか、外に断熱材をはるか、2種類あります。
外張り断熱
柱や梁の外からすっぽりと家を覆うように断熱材を貼っていくタイプ。
外張り断熱の特徴
- 気密性が取りやすいし、とりあえず貼れればいいので期待通りの断熱効果が得られやすい。
- 外部から家全体を守るので、家自体が長持ちします(耐久性の向上が期待できる)
- 分厚い断熱材は使用できず断熱力に限界あり。
つまり、外壁材を選ぶ可能性がありますね。
充填断熱
いわゆる外に対する、内側の断熱ですね。
充填断熱の特徴
- 柱の間に断熱材を挟み込むことで、家の中を密閉するイメージ。
- 必然的に、柱の部分は外部と内部を交通していることになるので、柱が熱を通すことになります。
- しかし、柱の太さの分、断熱材を仕込むことができるので、外張りよりも断熱材自体の断熱効果を上げることができます。
- 安い断熱材も使用できるので、コストが浮く場合が多いです。
- さらに、外と内のダブルで断熱効果を上げる方法もあるようです。
その場合、せっかく外張りだけにできるところを、無駄なスペック向上のために、本来の外張りのメリット(躯体の耐久性向上など)は失われてしまうこといは注意が必要です。
外壁材や屋根自体に断熱効果を持たせているものもありますね。
断熱材の種類は繊維系と発泡系をおさえておこう!
先ほども比較表を張り出しましたが、断熱材はおおきく二つのグループに分かれます。
- グラスウールが含まれる「繊維系」の断熱材
- 最近流行りの硬質ウレタンフォームが含まれる「発泡系」
繊維系の断熱材
いわゆるグラスウールといわれるものが一般的。

我が家はロックウールでした。
繊維系のメリット
- とにかく安い。流通量も多く、施工できる会社が多い。
- 吸音力が高く、不燃性で火事にも強い。
- 軽くて施工しやすいので、大工に喜ばれる。
繊維系のデメリット
- 施工はしやすいのだけど、正しく施工してもらわないと、断熱力が発揮できない。
- 結露に弱いとされている。湿度を含むことで、ずれ落ちることがあり、気密性がなくなります。
ガラスウールとロックウールの違い
ちなみに、ガラスとロックの違いですが、若干ロックがお値段的にも性能的にも高いです。
高いとはいえ、後述します最近はやりの発泡ウレタン吹き付けの半額以下ですけどね。
発泡プラスティック系断熱材
硬質ウレタンフォームやEPS、フェノールフォームらがこれに当たります。
最近はアクアフォームなどの安価な発泡系のウレタン素材が現れて、ローコスト組合のくまにも手の届く断熱材となってきました。
よく、発泡系のウレタン素材は新世代、繊維系はもう古いみたいな言い方してます。

実際にはどちらもそれなりの歴史があります。
特徴としては、よくアイシネンとアクアフォームがどっちがいいかで喧嘩してます(笑)
たくさん種類があるので、ざっくりと最近多い発泡ウレタンの特徴を書きます。
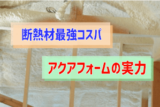
発泡系のメリット
- 現場で家の形状に合わせて施工できる。隙間ができにくい。
- 専門業者による施工なので
- アイシネンは永久保障。(壁の内部のことなので、一体どのように査定するかは疑問ですが)
発泡系のデメリット
- 繊維系の倍以上するので、特に大きな家を建てる場合コストに響きやすい。
- 情報操作が著しく、実際のところがわかりづらい。最近多く増えたので、10年後にどう評価されているかは疑問。
- 燃えるだの水に溶けるだの言われている。業者はどちらも問題ないという。
ロックウールの「ホームマットNEO」レビュー
我が家で採用したグラウウール(ロックウール)が、結局どうなんだということについて説明していきます。
我が家はロックウールを採用
さて、先にも述べたとおり、ぶちくま家はホームマットneoというロックウール系の断熱材を取り入れております。

というよりも、建てる段階ではあまり断熱材のことを考えておらず、ハウスメーカーの言われるがままに契約していたというのが実のところであります。
そして、家を建てる段になってようやく、「ホームマット」って大丈夫なの?と断熱材について調べ始めたのでした。

おそい!
さらに、同時期に家を建てていた、ローコスト組合の友人は、どこのものかはわからないけれど、発泡ウレタン系を吹き付けていたとのこと。
その頃、うちも断熱材を張っていたのだけど、向こうが「吹き付けている」のに、うちは何やらビニールの安っぽいマットを壁に詰めているだけ!
と心配になった次第でありました。
繊維系断熱材ロックウールの最大の弱点は施工力
さて、ぶちくまが考える、繊維系断熱材の一番のデメリットは、「大工による施行なので、断熱材の効力が最大限に発揮されない」ことにあると思っています。
だいたい、断熱材が入れられるのって、序盤から中盤にかけてなんだけど、まだ大工さんたちの力が本領発揮する前なんですよね。
そんで、断熱材がちょっと雑に入れられるじゃないですか。

不安になるんだけど、「ここ隙間あるんで、もう一度詰め直してください」ってなかなか言えないんですよね。
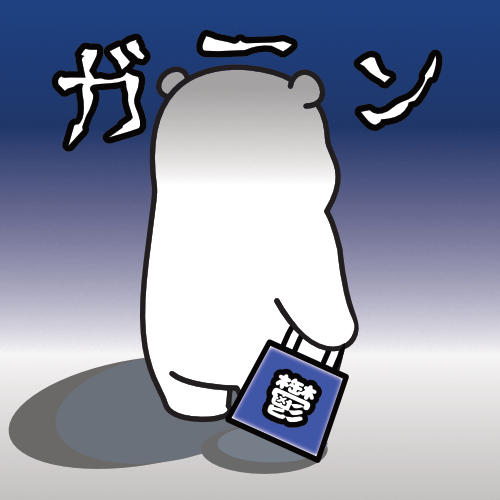
「仕事雑ですね」って、これから仕事もたくさんあるのに言えないし。機嫌を損ねて、他の作業が却って手抜きになっても嫌だし。

素人にいらぬ口出しされるのって嫌なもんですしね。
「これでも十分ですよ」って言われるのも想定されますし。
発泡系はそのみちのプロが施工しにくるのが普通
これが、発泡ウレタンの吹き付けだと、専門業者が来るので、文句も言いやすいですよね(てへ)

発泡ウレタンのいいところは、隙間ができにくいところだと思います。
断熱材としてのメリットは、実際のところはなんとも言えないところはまだあるし、課題は山積していると思っています。

発泡ウレタンだから断熱材は完璧、ということはないと思います。
これも、当然のことながら業者の施工力も関係してきますし、施工時にしっかりとした厚さが、均等に施行されているかどうかチェックが必要です。
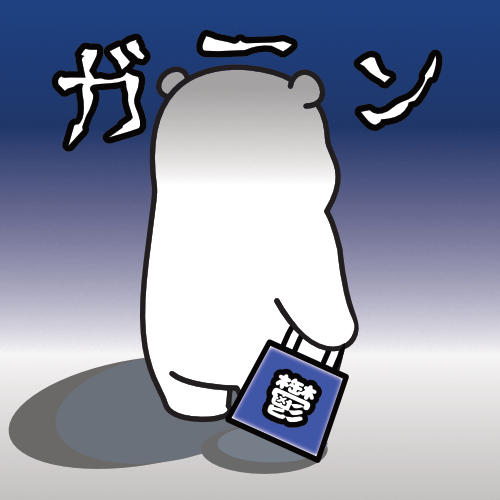
でも、毎日チェックするのなんて実際は無理だよね。気がついたらすぐに壁で閉じられちゃうし。
というのが現実的に悩ましいところですな。
ホームマットNEOの評価〜この冬を迎えて〜
ようやく冬が到来したので、この「ホームマットneo」ならびに繊維系断熱材が実際のところどうなのか、レビューしてみたいと思います。
繊維系の評価は築年数10年の中古物件を冬場にみればいい
これまでの家づくりの8割程度が繊維系断熱材だったのですから、ここ10年の家づくりレビューを見てみればよくわかると思います。
繊維系の断熱材で検索すれば必ず見つかるのが、10年ほど経って、湿気を多く含んで真っ黒になった断熱材の姿。
よく、繊維系は湿気に弱くカビが繁殖して、さらに湿気を含んだ断熱材が近くの躯体を腐食させる、ということが言われています。
そして、繊維系断熱派の方々が、これは施行方法が悪く、しっかり防湿シートで覆っておけばこんなことにはならない、と擁護しています。

でも、その施工が保証されないからみんなこまってるわけでしょ?

一声かけるだけで大工さんの気合の入り方も違うんだろうけどね。
意外と、断熱材の施工方法は気にしない方も多いし、そもそも立ち会えない人だっていっぱいいるからね。
いずれにせよ、繊維系断熱材にはそのような危険性があるということは、施主としては知っておくべきだと思います。
どこのハウスメーカーも自分のところが採用している断熱材を悪くいうことはないですからね。
どうしても断熱材の性能を体感したい場合は、冬場に中古物件の見学に行くのがお勧めです。
発泡ウレタンは専門業者の施工、技術不足の新人もいるからピンキリ
さっき、発泡ウレタンの方が安心と書いたのは、施行方法が業者が行うから安定している点です。
ただ、これも結局、しっかりと施行されていなければ断熱性能が落ちる。
最近、明らかに発泡ウレタンの採用率が上がっているので、多分この業界も職人不足だと思います。
故に、せっかく高い断熱材を導入したのに、施行技術が悪くて、蓋を開けば安いグラスウール以下、なんてこともありうるわけです。
発泡ウレタンでも素材の性能は商品次第
さらには、発泡ウレタンは特にピンキリな素材らしくて、100倍発泡なんていう、いわばカルピスウォーターを水で薄めたみたいな商品もあります。
特にローコストで発泡採用しているところは注意が必要と言わざるを得ない。
もちろん、しっかりとした材料を、しっかりとした技術者が行えば、これ以上ない断熱性能を得られるのは事実で、それでローコストで建てられればベストな選択と言えるでしょう。
ローコスト住宅会社で発泡ウレタンが採用される理由
高コストの断熱材を安易に採用しているローコストハウスメーカーが増えていることから、目を背けてはいけないと思います。
これは、断熱材自体の価格が手が届きやすくなってきたとも言えますし、名前ばかり高断熱材を採用して、施主の見えにくいところコストカットしている可能性もあると言えます。
断熱材は最近注目されているから、「断熱材だけいいのを使っておけば高断熱で評判が良くなる」という宣伝効果もあります。

気密性は計測することができるからクレームになるけど、断熱性能を測定する方法はないからな
断熱材は、取り組めばとりあえずそれでOKなので、住宅会社としては宣伝に出しやすい商品なんですよね。
その辺りのことをこの記事にも書きました。

いずれにせよ、注意が必要なのです。
あくまでもグラスウールもいい断熱材だということ
長々と書きましたが、そういったわけで、結局、いろいろ悩むようであれば、少なくとも安くてある程度の断熱性能を保てる繊維系断熱材でいいのではないか、というのがぶちくまの結論です。

大工が施工するので心配、はつきものですが、同時に、施工に一番慣れている素材が繊維系断熱材とも言えます。
昔ながらの家に住んでいた方からすれば、断熱材さえ入っていれば、十分暖かく感じられるのです。
大寒波の冬、電気代も高くて財布の中まで猛吹雪の模様

早々に大寒波がやってきたおかげもあって、ぶちくま家はしっかり寒いです(苦笑)
ですが、エアコンさえつければ靴下なしで快適に過ごせていますし、エアコンの風が苦手なじじばばくまの部屋にはガスの温水ルームヒーターを入れているので、柔らかな温風でめちゃめちゃぬくぬくできます。

言ってしまえば、確保する熱源だって日々進化しているので、断熱材に強くこだわる必要もないのかもしれません。
とは言え、長く住む家ですから、断熱材の選択には、断熱性能だけでなく、長く家を守ってくれる耐久性にも目を向ける必要がありそうです。
ぶちくま家の電気代大公開
ぶちくま家の電気代、知りたくありませんか? 新潟の冬をズバ暖だけで乗り越えるという記事で公開しています。

断熱材の耐久性について知りたい
いわゆる劣化しやすいかどうかをみていきましょう!
繊維系(グラスウール)は何年もつの?
繊維系は湿気に弱いと言われています。
ぶちくま家も施工する様子を見ましたが、スポンジのような素材なので、経年劣化は確かにあるだろうし、何年かしたら、ずるずると上の方が下がってきて、隙間ができるなぁ、というあたりは避けられないと思います。
グラスウールの耐久性自体は高い
20年経っても断熱性能自体は変わりないようです。つまり、きちんと施工された場合のグラスウールのコストパフォーマンスと断熱性能は折り紙つきです。
※なお情報源はグラスウール関連会社の模様
グラスウールは、初期性能であるJIS熱抵抗値とまったく変わらない値でした
https://www.isover.co.jp/product/glasswool/durability
発泡ウレタン系の耐久性は
一方の発泡ウレタン系も、100倍発泡の軟質性のウレタンは水に弱いそうですし、経年劣化が全くない、という素材ではないようです。
グラスウールは、シロアリの食害に強い断熱材です。一方発泡プラスチック系断熱材はシロアリの食害を受けやすく、シロアリの食害を受けると断熱材に隙間ができ、断熱性能の低下をまねくばかりか、住宅の耐久性も影響を及ぼす恐れがあります。
https://www.glass-fiber.net/glasswool_short_taikyu.html

個人的には硬質発泡ウレタンが一番良さそうだなぁ、というイメージです。
おそらく家を建てたときに断熱材の素材についての知識を得ていたとしても、結局コスト面で、繊維系を選択していたとは思います。

だって、どんな素材でも劣化することは間違い無いのだから、それなら20年後、リフォームすることを想定して、20年後の新素材に期待をかけた方がいいと思います。
断熱材とローンの考え方
断熱材の話だけでまさか住宅ローンにまで言及することになるとは。
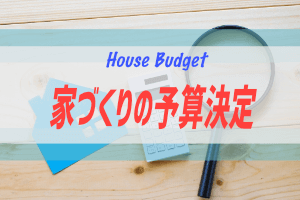
20年後に建て替えるかリフォームするか
断熱材は日々進化しており、
- 「最高の性能を高コストで利用するか」
- 「汎用価格でまずまずの性能にするか」

このどちらかの考え方に自分が近いのか、考えると判断の基準になると思います。
これは、20年後、あるいは30年後に、家をどのように維持させたいか、という考え方にも繋がると思います。
計画的リフォームとそのための積立について

いやいや、リフォームなんてしないで、少しでもいい家を建てた方がいいに決まっているじゃないか。
そういう声が聞こえてきそうです。
「家づくり」と言えば、何かと一度の家づくりに全ての財産をかけて、多くの借金をして「一生に一度の買い物」にしてしまいがちです。

でも本当にそれでいいの、とぶちくまは少し心配してしまいます。
建て替え費用が手元にあるのが最良のリスクヘッジ
ローコスト住宅と大手ハウスメーカー、場合によっては建物価格でも倍くらいの値段が違うことも。

これって、もう一度家が建て替えられるくらいの価格差です。ローンの複利も考えると納得されると思います。
例えば、リフォームを20年後に想定して、ローコスト住宅で安く建てて、差額分を積み立てていけば、それなりのお金になります。

積立をしておけば、リフォームではローンを組む必要もないでしょう。
これが、ギリギリの返済額で設定してしまった場合、次に家を直すのが30年後になったとしても、その時に改めてローンを借りる必要が出てきます。

一生ローンに縛られた人生、結構しんどそうですよ
ハウスメーカーにとっては最大利益は「高い家を建てさせる」こと
ハウスメーカーは自分たちの利益を増やすためにそう促しますからね。
ローンを少しでも減らして、早くローンを返してしまった方が、トータルで得することまではなかなか想像しづらいところです。
自分たちの経済力も考えて、無理にコストをかけない、という選択も大事です。
この辺りのことは誰も教えてくれませんからね。
自分たちは借金をしている、という最大のライフリスクから目を背けてはならないのです。
断熱材と気密性の話
断熱材と深い関係にある、気密性についての情報です。
断熱材と換気はセットで考えなければいけない
断熱材の話をする上で、切っては切れないのが換気の話です。
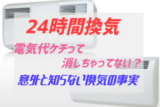
計画換気とは
断熱性能が高ければ、当然換気の必要性も高まります。
最近の住宅では24時間換気システムは当然導入されていますが、私としては、高気密・高断熱であること以上に、この換気方法がしっかり確立されているか、というところに注目すべきだと思っています。

というか、換気がしっかりできないのであれば、もはや高気密・高断熱である必要もない、とすら思っています。
熱循環の話
外界との熱をいくら遮断しようと思ったところで、新鮮な空気を安定して確保する方法がなければ、暖めた/冷やした空気は結局外に逃がさないといけなくなります。
なんだか、この断熱と換気の矛盾が気になって仕方がないのですが、ただ、マツシタホーム社長ブログの「誤解だらけの断熱その2」にある通り
「換気システムは、気密がしっかりしていてはじめて、計画通りに換気されるんです」
http://mhome-syatyou.jugem.jp/?eid=946#sequel
という言葉にはなんだか納得してしまいました。
無駄な断熱性能よりも手近なコスト
換気というのはやっぱり隅々の空気を全て入れ替えるのが正しい換気であって、熱循環についてもしっかり対策しないことには断熱って意味ないなぁというのが結論です。
熱循環にまでお金がかけられないなら、断熱性能に大きなお金をかけることもないような気がします。
断熱材総評と感想
実は、ぶちくま自身は、あまり断熱材のことを調べないままにハウスメーカーを選択してしまったことをしばらくの間後悔していました。

調べてみると発泡ウレタンの方が新しい技術だし取り入れて見たいなぁ、と思う部分が多かったからです。後の祭りとは、まさにこのこと。
ただ、同時に繊維系にもいいところはあるし、住んでみれば別に困ることはなかったので、まぁそれならそれでいいか、というのが今の結論です。
多分、10年後には違う感想だと思いますが、10年後には10年後で違う問題があるだろうし、違う解決法もあるかもしれません。
まずは20年、という気持ちでローコスト住宅での家づくりを楽しんでみるのもいいかもしれません。





コメント
「ストレッチ 施術 first」に関する最新情報です。
新潟県上越市のストレッチ専門店「Beauty Stretch FIRST」は、疲労回復や姿勢改善を目的とした施術を提供しており、トレーナーの手技で筋肉をほぐすスタイルが好評です。特に冬季は寒さや除雪作業による筋肉の固まりやすさが問題となるため、ストレッチが推奨されています。新規来店者には1100円オフの特典があり、2025年1月からは個人宅や企業への出張施術も開始します。利用者は1400人を超え、腰痛や肩こりの緩和を目的とした3つのコースが用意されています。完全予約制で、着替えの貸し出しもあり、手ぶらでの来店が可能です。
https://www.joetsutj.com/2024/12/24/070000
「プラスティック フナックス 配合」に関する最新情報です。
有限会社フナックスは、新潟県燕市の金型メーカーで、天然の抗菌作用を持つ笹を配合したプラスティック製のテーブルウェア「リーフテーブルウェア」を開発しました。この商品は、小さな子供が安心して使用できる食器を目指しており、笹の葉のパウダーを使用しています。試験結果によると、笹配合のプラスティックは、一般的なプラスティックに比べて、細菌の増殖を抑制する効果が確認されています。現在、プレートやマグカップ、カトラリーセットなど、5種類の製品がラインナップされています。デザインは一般主婦や子供たちの意見を取り入れており、幅広いニーズに応えることを目指しています。
https://www.niikei.jp/1308718/
「エネ エネ 弱点 エネ 組み替え」に関する最新情報です。
現在、経済産業省の総合資源エネルギー調査会では、第7次エネルギー基本計画の策定に向けた議論が進行中です。主要なテーマは、エネルギーの安定供給を確保しつつ脱炭素化を進める方法とその移行過程です。脱炭素化の焦点は再生可能エネルギー(再エネ)と原子力発電の拡大にあり、特に経済界出身の委員からは原発の新増設を求める声が強まっています。しかし、白石氏は国産の太陽光や風力発電、蓄電池の急速な価格低下を考慮し、これらが電力の脱炭素化と安定供給にどのように寄与するかを分析しています。再エネを第一に据えたエネルギー基本計画の重要性が強調されています。
https://toyokeizai.net/articles/-/822787?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「施術 人気 58」に関する最新情報です。
新潟県上越市の「カイロプラクティックセンター上越」では、2024年8月12日から18日まで「夏バテぶっ飛ばし施術会」を開催します。この期間中、人気メニューの「ドライヘッドスパセット」が通常価格1万3300円から58%オフの5500円で提供されます。施術は完全予約制で、初めての利用者を対象としています。ドライヘッドスパは、女性スタッフによる手技で頭をもみほぐし、リフレッシュ効果が高いと評判です。また、施術中には美容液たっぷりのフェイスマスクも使用され、体の姿勢改善や体操指導も行われます。さらに、参加者にはサプリメントがプレゼントされる特典もあります。技術を学びたい方のために「お店見学会」も同時開催される予定です。
https://www.joetsutj.com/2024/08/08/140000
「不燃 ウレタン 性能」に関する最新情報です。
アサノ不燃(東京都江東区)は、硬質ウレタン断熱材の表面に不燃木粉パックを重ねることで、国土交通大臣の不燃材料認定基準を満たす性能を確認しました。試験体は合板12mmの上に硬質ウレタン23mm、不燃木粉パック10mmを塗布し、コーンカロリーメーターを用いて発熱性試験を実施。約750℃の熱を20分加えた結果、延焼せず、有害な変形や煙・ガスの発生も見られませんでした。試験体の総発熱量は1.29MJ/㎡で、基準の8MJ/㎡以下をクリアし、今後正式な不燃認定を取得する予定です。
https://www.s-housing.jp/archives/360141
「火事 燃える 倉庫」に関する最新情報です。
大阪の東成区で倉庫2棟が火事になり、消防が消火活動を行っている。同時に、大阪市西成区や西成区でも火災が発生しており、けが人の確認が行われている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzUvMjUwXzVfcl8yMDI0MDYxNl8xNzE4NTEwNzAyNTA4MjIw0gEA?oc=5
「住宅 火事 住宅 火事」に関する最新情報です。
岩見沢の住宅で火事が発生し、男性が倒れているのが見つかりました。男性は意識があり、病院に搬送されました。火災の詳細や原因については明らかにされていません。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzUvMzM2XzVfcl8yMDI0MDYwNV8xNzE3NTM5MzAyNjI3Mjgz0gEA?oc=5
「アパート 火事 アパート 火事」に関する最新情報です。
山梨県南アルプス市山寺のアパートで火事があり、2階の1室から性別不明の焼死体が発見された。警察は遺体の身元特定と出火原因の調査を進めている。火災は近隣に延焼せず、午後9時51分に鎮火した。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiOGh0dHBzOi8vbmV3c2RpZy50YnMuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvdXR5LzExOTE0NTc_ZGlzcGxheT0x0gEA?oc=5
「東京 死亡 火事」に関する最新情報です。
東京・練馬区の西武新宿線沿いの住宅で火事が発生し、逃げ遅れた高齢男性が死亡しました。隣接する専門学校など4棟が焼け、ポンプ車など28台が出動したと報じられています。愛知・豊橋市でも木造平屋建ての住宅が焼け、70代の男性が死亡したとのことです。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMzA5XzJfcl8yMDI0MDUyMl8xNzE2MzQ2NTkyNzQzNDE30gEA?oc=5
「隙間 性能 遮音」に関する最新情報です。
木造住宅において、防音性能が軽視されていることがあり、生活音を抑えて快適に過ごすための方法について、遮音工事とデコスドライ工法の施工について取材したQ&A形式の記事がある。隙間があると遮音性能が低下し、音は隙間から逃げるため、徹底的にシーリングすることが重要であり、20dBも遮音性能が落ちる可能性がある。
https://www.s-housing.jp/archives/346504
「延焼 火事 速報」に関する最新情報です。
大阪府四條畷市で建築中の木造建物が火事となり、周辺の住宅や車にも延焼しました。約190世帯が停電になりましたが、けが人はいないと報告されています。建築中の集合住宅が全焼し、周辺の住宅6棟と約10台の車にも延焼が及んだとのことです。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzUvMjUwXzVfcl8yMDI0MDQyNV8xNzEzOTk1MTMyMDU5MjUz0gEA?oc=5
「塩害 サイディング 弱点」に関する最新情報です。
金属サイディングの最大の弱点は塩害による影響であり、雨よりも寿命が短くなる可能性があるという解説がされています。特に塩害の影響により、金属サイディングの寿命が1/3以下になることもあるとされています。
https://www.s-housing.jp/archives/346441
「火事 燃える 燃える 火事」に関する最新情報です。
横浜市保土ケ谷区で木造2階建ての住宅が激しく燃える火事が発生しましたが、幸いにもケガ人はいなかったようです。火災の詳細については警察が調査中です。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzIvMzk3XzJfcl8yMDI0MDQxMV8xNzEyODQwOTQxOTIyMzY00gEA?oc=5
「窯業 lixil 新素材」に関する最新情報です。
LIXILは、竹や籾殻の炭、鉱石など自然由来の素材を使用した窯業系新素材「textone(テクストーン)」を開発しました。
https://www.s-housing.jp/archives/346729
「序盤 なれ なれ ヴェーダ」に関する最新情報です。
「星になれヴェーダの騎士たち」の初心者向け序盤攻略の効率的な進め方について紹介されています。序盤では光属性のキャラクターを育成し、特に「ルシアン」が優秀なヒーラーとして活躍します。パーティ編成や戦闘時の回避などのポイントも解説されており、ワールドクエストをクリアしてコンテンツを解放することが重要です。記事のライターはゲーム好きの20代男性で、ゲームを通じて多くのことを学んできたと述べています。
https://chara.ge/hoshininare/hosininare-knights-of-veda-how-to-proceed-efficiently/
「1人 火事 1人 遺体」に関する最新情報です。
兵庫県姫路市の集合住宅で火事が発生し、1人の遺体が発見された。同日、大阪府松原市でも別の住宅で1人が死亡する火事が発生した。また、京都府福知山市や滋賀県近江八幡市でも火災が報告され、それぞれ1人の遺体が見つかった。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzUvMjUwXzVfcl8yMDI0MDMxNF8xNzEwMzg2NzYyNTk3MzU10gEA?oc=5
「火事 1人 住む」に関する最新情報です。
福島県三島町で住宅一棟が全焼する火事が発生し、焼け跡から1人の遺体が見つかった。火災後、住民と連絡が取れなくなっている長谷川和男さんの身元確認が警察によって進められている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRmh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3VzaGltYS10di5jby5qcC9sb2NhbG5ld3MvMjAyNC8wMy8yMDI0MDMxMzAwMDAwMDEyLmh0bWzSAQA?oc=5
「1人 1人 遺体 火事」に関する最新情報です。
兵庫県姫路市の共同住宅で火事があり、火元の家から80代の男性の遺体が見つかった。現在、住人との連絡が取れていない状況である。この火事で共同住宅6軒が被害を受けた。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzUvMzYyXzVfcl8yMDI0MDMxNF8xNzEwMzg1NjkyNTQ2MzYw0gEA?oc=5
「火事 守る ハンカチ」に関する最新情報です。
火事で煙を吸わないためには、ハンカチやタオルで口と鼻を覆い、低い姿勢で逃げることが重要です。消防庁の研究によると、濡らしたタオルの方が除煙効果が高く、煙を吸わないために推奨されています。ただし、濡らした場合は呼吸がしにくくなるリスクもあるため、早めの避難が重要です。火事に遭遇した場合は、乾いたタオルで口と鼻を覆い、低い姿勢で逃げることを心がけましょう。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65f0f81ce4b01707c6d22b40
「死亡 火事 2人」に関する最新情報です。
福島県いわき市の住宅で火事が発生し、男女2人が死亡した。死亡したのは西山功さん(83歳)と妻の昭江さん(81歳)であり、火事の原因や身元の特定が警察によって調査されている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiRmh0dHBzOi8vd3d3LmZ1a3VzaGltYS10di5jby5qcC9sb2NhbG5ld3MvMjAyNC8wMi8yMDI0MDIxNzAwMDAwMDAzLmh0bWzSAQA?oc=5
「火事 民家 民家 燃える」に関する最新情報です。
甲府市北口三丁目で朝の住宅街で民家が燃える火事が発生しました。消防によると、火事は午前7時46分に鎮火しました。警察が火事の原因を調査しています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3c2RpZy50YnMuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvdXR5Lzk5NzA4Nz9kaXNwbGF5PTHSAQA?oc=5
「繊維 化学 化学 合成」に関する最新情報です。
艶栄工業が化学合成繊維の染色に使用する乾燥機を更新するために、10億円の投資を行うことが発表されました。新しい乾燥機は1分間に40メートルの繊維を乾燥することができ、省エネと高品質を両立させることができます。艶栄工業は蒲郡市に本社を置き、化学合成繊維の染色を専門としています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQWh0dHBzOi8vd3d3LmNodWtlaS1uZXdzLmNvLmpwL25ld3MvMjAyNC8wMi8wNi9PSzAwMDI0MDIwNjA2MDFfMDEv0gEA?oc=5
「1人 意識 火事」に関する最新情報です。
長崎市晴海台の住宅地で火事が発生し、1人が意識不明の状態で見つかりました。火事は木造の2階建て住宅で起き、午前11時前に消防に通報されました。現在も消防が消火活動を行っており、住宅密集地であるため注意が必要です。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNGh0dHBzOi8vd3d3Lmt0bi5jby5qcC9uZXdzL2RldGFpbC5waHA_aWQ9MjAyNDAxMjkwMDTSAQA?oc=5
「家屋 火事 火事 火元」に関する最新情報です。
山梨県南アルプス市で夜に発生した火事で、4棟の住宅が燃え、1人の遺体が見つかりました。火元となった家屋は木造の2階建てで、午後9時10分過ぎに110番通報がありました。火事は隣接する2棟の飲食店と1棟の住宅にも燃え移り、全焼しました。遺体は火事の火元となった家屋の焼け跡から見つかり、身元はまだ確認されていません。警察は遺体の身元と火事の原因を調査しています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3c2RpZy50YnMuY28uanAvYXJ0aWNsZXMvdXR5LzkwNTk4Mj9kaXNwbGF5PTHSAQA?oc=5
「猛吹雪 往生 立ち」に関する最新情報です。
新潟では最強の寒気による猛吹雪が発生し、多くの人々が立ち往生しています。JAF(日本自動車連盟)への救援要請が3倍に増加しており、「急な行動は避けるように」と呼びかけられています。また、北海道留萌市でも同様の状況が報告されており、路面の凍結や車のスタック、事故などが発生しています。これにより、交通渋滞や立ち往生する車が目立ち、一部の地域ではホワイトアウト状態となっています。現地では積雪量が50cm以上に達し、道路や駐車場の利用が制限されるなどの影響が出ています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiQGh0dHBzOi8vbmV3cy50di1hc2FoaS5jby5qcC9uZXdzX3NvY2lldHkvYXJ0aWNsZXMvMDAwMzI5MDM2Lmh0bWzSAQA?oc=5
「新潟大学 火事 教育学部」に関する最新情報です。
新潟大学教育学部の建物で火事が発生し、職員が炎上を発見しました。火は鎮火されましたが、建物は一部焼失しました。火事の原因やけが人の有無などは現在捜査中です。
https://www.niikei.jp/906429/
「施術 男性 疑い」に関する最新情報です。
新潟市秋葉区の32歳の柔道整復師男性が施術費をだまし取る詐欺の疑いで逮捕されました。彼は自身が勤める整骨院で交通事故の治療を受けた患者に対し、通院日数を水増しして保険会社に請求し、現金をだまし取っていたとされています。逮捕された男性は院長を務めるなど、3年から4年にわたりこの詐欺行為を行っていたとのことです。現在、警察は捜査を進めています。
https://www.niikei.jp/889593/
[…] とのこと。 概ね、我が家と同じ断熱性能な感じですね。 我が家の断熱に関する記事はこちら。 […]
[…] […]