家づくりをしているときに軽視しがちで、一番後悔するのは「住宅性能」に関すること。特に、光熱費も上がってきた今の日本では「もっと断熱性能について考えておけばよかった」と後悔されている方は多いと思います。
このページでは2024/03/22時点で参考になる情報をまとめておきましたので、「断熱で失敗したくない」という方には役立つ情報になっていると思います。
2024年の「断熱材」新着情報まとめ
断熱材について調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。
断熱材に関する新着ニュース
断熱材に関する新着ニュースをまとめています。
2023年の「断熱材」新着情報まとめ
断熱材について調べているついでに見つけた新製品情報や発売が噂されるものなどの情報をざっくりまとめて置いておきます。
カテゴリ名に関する新着ニュース
1級建築士が選ぶ「採用したい断熱材メーカーランキング2022」
2023年7月12日の、断熱材メーカーに関する情報をお届けします。
- 1位は旭化成建材、2位は旭ファイバーグラスが占めています。
- 機能性や省エネ性能が評価されている共通のポイントです。
- 旭化成建材を採用したいと考えている人は約47%で、まだ多くの建築士が未採用の状態です。
補足情報:調査概要
- 調査対象は、1級建築士5000人と、1級建築士2万1780人。
- 調査方法はインターネット調査で、調査対象となる全49部門の製品を8グループに分けて調査。
- 調査期間は2022年8月22日~9月26日。
名古屋市で開催された「断熱体感フェア」にて省エネ・高性能リノベーション体験
2023年8月30日の、住宅リノベーションに関する情報をお届けします。
- 名古屋市で「省エネ、性能向上リノベーション(全館空調 エコキューブ)」が体験できる断熱体感フェアが開催されました。
- リノベーションされたマンションでは、エアコン1台で全室の温度と湿度をコントロールでき、温度のムラがほとんどなく、快適な生活が可能です。
- このリノベーションにより、年間6万1,732円のエネルギーコストが削減できるとされています。
補足情報:リノベーションの特長と利点
- 「高気密」「高断熱」「高機能換気」の3つのポイントから、「一生気持ちよく暮らせる家」が実現されています。
- 高機能換気システムにより、空気中のほこりや花粉、PM2.5やウィルスなどを排除し、24時間新鮮な空気が確保されます。
- 次世代断熱材(ミラフォーム)を使用することで、外からの熱の伝わりを少なくし、夏は涼しく、冬は暖かく過ごせます。
補足情報:リノベーションの対象層と将来性
- リノベーションに関心を寄せるのは、30代40代の層と高齢層まで多岐にわたります。
- 社会全体で求められる快適な住環境は、リノベーションで十分に実現可能とされています。
このように、リノベーションによって省エネ効果や生活の質(QOL)を高めることが可能であり、多くの人々にとって有益な選択肢となっています。
デコス社、新聞紙を原料とした断熱材「デコスファイバー」で湿度20%減少
2023年8月29日の、環境とエネルギー消費に関する情報をお届けします。
- 株式会社デコスが製造・販売するセルロースファイバー断熱材「デコスファイバー」は、リサイクルした新聞紙を原材料としています。
- デコスファイバーを使用した場合、室内の湿度が約20%減少することが実験で確認されました。
- この湿度の低下は、エアコンの消費電力を削減するだけでなく、長引く暑さに対する新たな対策ともなります。
補足情報:デコスファイバーの特性と利点
- 「デコスファイバー」は、新聞紙(パルプ)の調湿機能を活かして、夏場の除湿と冬場の乾燥防止が可能です。
- 2025年には、新築住宅での「省エネ義務化」がスタートします。この観点からも、デコスファイバーのような高性能な断熱材が注目されています。
補足情報:環境への配慮と今後の展望
- デコスファイバーは、世界的な環境ラベル「エコリーフ」を日本の断熱材として初めて取得しています。
- 製造時のエネルギー消費量が低く、30,000棟以上の施工実績があり、熊本地震時にも採用された信頼性を持っています。
会社概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社デコス |
| 代表者 | 代表取締役 安成信次 |
| 本社所在地 | 山口県下関市菊川町田部 |
| 設立 | 1974年 8月 30日 |
| 資本金 | 30,000,000 円 |
| 従業員数 | 31名 |
| 事業内容 | 断熱材製造販売・施工、FC事業 |
| ホームページ | Decos Co., Ltd. |
以上のように、デコスファイバーはエネルギー効率、環境性能、そして人々の生活の質(QOL)を高めるための非常に有望な製品と言えるでしょう。
断熱材の新製品情報
断熱材の新製品情報についてまとめています。
添付情報を参考に、テンプレートの「」を埋めるように情報をまとめてください。
【テンプレート】
#### 新製品:「紹介する商品の名前」
「今日の日付」時点での「メーカーなど」の「商品名」について紹介します。
##### 「商品名」の特徴
– 「」
– 「」
– 「」
##### 価格
「」円(税込)
##### 「商品名」のおすすめポイント
– 「他社製品と比較して特徴的なポイントなど」
– 「メリットをまとめる」
##### 「商品名」の気になるところ、注意点
– 「購入時の注意点」
– 「デメリットなどあれば」
##### 「商品名」の購入時参考情報
– 「販売日程や価格、販売店舗など」
– 「」
【添付情報】
【出力方法】
マークダウン、日本語
今、知っておきたい「日本の断熱」に関すること
2024/03/22時点で更新した情報についてまとめています。
現在の「断熱」に関する住宅性能
断熱の前回記事がずいぶん前だったので、「とりあえず情報をアップデートしていく」場所としてこのページを作成しました。
断熱に関しては「改正建築物省エネ法(【令和4年6月17日公布】)」の情報が比較的新しい法案となります。
これにより、これまで以上に住宅性能が客観的に評価されるようになり、メーカー側の説明義務もあるので仮に施主が無知であっても断熱を含めた住宅性能は説明を受けやすくなりました。
断熱仕様の基準
断熱に関してだけまとめますが、住宅性能に関しては日本は後進国と言われており、特に窓周りを含めた断熱については昨今の住宅事情を踏まえて「より一層厳しい基準が求められる」可能性があります。
言い換えると、毎年のように補助金と基準底上げが検討される項目であり、最新の情報を追うように心がけていただけたらと思います。私自身はすでに家づくりを終えているので、情報アップデートは頻回ではありません。
住宅性能の地域
改正建築物省エネ法によって各地域によって住宅性能の基準が定められています。また、現在の基準は実態に則しておらず、将来的に求められる基準「誘導基準」が今後の目標値となるため、こちらも合わせて調べていただくのが良いかと思います。
地域は寒い地域を1として、温暖な地域を8として8地域に区分しています。私が住む新潟でも寒暖の差があり、同じ県内でも2〜3区分に分かれている場合があり、一度自分が住む地域がどこの区分の属するのかを調べてみるといいかと思います。
- 【誘導基準編】木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック2022:1~3地域版
- 【誘導基準編】木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック2022:4~7地域版
- 【誘導基準編】木造・RC造戸建住宅の仕様基準ガイドブック2022:8地域版
断熱基準の算定
以下の項目を、使用する断熱材やその厚みなどから「熱の移動しやすさ」を計算して数値化します。
外皮の断熱性能等に関する基準
- 外皮の熱貫流率の基準
- 断熱材の熱抵抗の基準
- 構造熱橋部の基準
開口部の断熱性能等に関する基準
- 開口部比率と熱貫流率の基準
- 開口部の建具、付属部材、軒等の設置に関する基準
一次エネルギー消費量に関する基準
断熱性能を評価する場合に、一次エネルギー消費量も算定して、いわゆる「ゼロエネルギー」となる住宅づくりを目指すことになります。使うエネルギーは少なくなるように家を建て、住宅で消費/産生するエネルギー量のバランスをとっていきます。
- 暖房設備、冷房設備、全般換気設備、照明設備及び給湯設備の基準
情報収集用リンク
私が情報収集用に参考にしているリンクになります。
関連省庁
断熱に関する諸情報
以下はChatGPTに生成してもらった文章で、検索意図を満たすために補助的に作成したものになります。
一般の読者の方には冗長で退屈で、かつ情報の真偽が怪しいところがありますが、何も考えなくてもChatGPTに考えさせると数分でこれくらいの情報が生成できるということを知り、今後はこのような情報が羅列されたサイトが増えることを憂慮していただければ幸いです。
日本の住宅の断熱性能とは?
日本は気候が四季折々であり、特に冬は寒さが厳しい地域も多いため、住宅の断熱性能は非常に重要です。断熱性能の高い住宅は、熱の流入・流出を抑えることができるため、冬は暖かく、夏は涼しい室内環境を保つことができます。また、エネルギー効率の向上にもつながり、光熱費の節約や地球温暖化の防止にも寄与します。
日本の住宅の断熱性能の重要性
日本の住宅の断熱性能について考える上で、まずは省エネ性能基準を知ることが重要です。日本では、2019年に改正された省エネ法に基づき、住宅における断熱性能基準が定められています。これにより、住宅の外皮性能や窓のU値、換気システムの性能などが指定され、断熱性能の向上が求められるようになりました。
また、日本の住宅の断熱性能は、気候条件に応じた設計が重要です。日本は四季があり、冬には屋内であっても生活に支障が出るような寒さに悩まされる地域も存在します。そのため、北海道や東北地方などでは、より高い断熱性能が求められます。
逆に、九州や沖縄などでは、断熱性能が高すぎると夏場に蒸し暑くなる可能性があるため、適切なバランスが必要です。
日本の住宅における断熱材の種類
日本の住宅における断熱材の種類には、グラスウール、ロックウール、ウレタンフォーム、セルロースファイバーなどがあります。それぞれの断熱材には特徴があり、使用する箇所によって最適な断熱材が異なります。
例えば、グラスウールは耐久性が高く、防音効果もあるため、壁や天井に適しています。一方、ロックウールは断熱性能が高く、耐震性にも優れているため、地震が多い地域では壁や床に使用されることが多いです。ウレタンフォームは断熱性能が高く、施工性が良いため、天井や屋根裏などに使用されます。
日本の住宅の断熱性能を高める方法
日本の住宅の断熱性能を高めるためには、以下の方法があります。
- 外断熱の採用:外壁に断熱材を設置することで、冷気や熱気の侵入を防ぎます。
- 窓の断熱性能の向上:二重窓や高断熱ガラスの採用など、窓の断熱性能を向上させることで、熱の出入りを抑えます。 3. 換気システムの設置:適切な換気システムを設置することで、断熱性能を高めつつ、湿気やカビの発生を防ぎます。
- 断熱材の厚みを増やす:断熱材の厚みを増やすことで、より高い断熱性能を実現できます。
- 冷暖房設備の効率化:冷暖房設備のエネルギー効率を高めることで、断熱性能を補完することができます。
- これらの方法を組み合わせることで、より高い断熱性能を実現することができます。住宅の設計段階から、断熱性能に配慮した設計を行うことが大切です。また、リフォームにおいても、断熱性能を向上させることで、快適な住まいを実現することができます。
日本の断熱材市場の現状と動向
日本の断熱材市場は、省エネルギー要求の強化や環境意識の高まりから、近年拡大傾向にあります。以下では、日本の断熱材市場に関する資料から抽出した3つのポイントを紹介します。
- 市場規模の拡大 日本の断熱材市場は、エネルギー消費効率の向上や地球温暖化対策のための政府の取り組みにより、需要が拡大しています。特に、省エネルギー基準の見直しや住宅の断熱改修支援制度などが市場拡大の要因となっています。
- 環境に優しい断熱材へのシフト 環境への配慮から、従来の石油系断熱材から、天然素材やリサイクル材料を使用した環境に優しい断熱材へのシフトが進んでいます。例えば、木質系の断熱材や紙質系の断熱材が注目されています。これらの断熱材は、CO2の排出量を抑えるだけでなく、調湿性能にも優れていることから、快適な室内環境を提供します。
- 技術革新による性能向上 断熱材市場では、新しい技術や素材の開発が活発に行われており、高性能な断熱材が次々と登場しています。例えば、薄型でありながら高い断熱性能を持つエアロジェルや、熱伝導率が非常に低い真空断熱材などが開発されており、市場に新たな選択肢が提供されています。
以上のように、日本の断熱材市場は、市場規模の拡大や環境に優しい断熱材へのシフト、技術革新による性能向上など、様々な動向がみられます。今後もエネルギー消費の抑制や地球環境への取り組みが求められる中で、断熱材市場の重要性はさらに高まると考えられます。
日本の断熱材市場の規模と成長要因
近年、日本の断熱材市場は拡大傾向にあります。これは、エネルギー消費の削減や地球温暖化対策への関心の高まりによるもので、政府による省エネルギー基準の強化や、住宅の省エネ性能向上に関する支援策が影響しています。また、高齢化社会を背景に、より快適な室内環境を求める消費者のニーズも市場拡大の要因となっています。
主要な断熱材メーカーと製品の特徴
日本の断熱材市場には、複数のメーカーが存在し、それぞれ独自の製品や技術を展開しています。以下に、主要な断熱材メーカーとその製品の特徴を紹介します。
- 東レ: トーヨボード 東レのトーヨボードは、高い断熱性能と防湿性能を持ち、耐久性にも優れています。また、環境負荷の低い素材を使用しており、リサイクル可能な製品として人気があります。
- キッツ: フェノールフォーム キッツのフェノールフォームは、発泡性のポリスチレン断熱材で、低い熱伝導率を持っています。また、防火性能にも優れており、さまざまな建築物に対応しています。
- グリーンマテリアル: セルロースファイバー グリーンマテリアルのセルロースファイバーは、木材を主原料とした環境に優しい断熱材です。調湿性能にも優れており、快適な室内環境を維持する効果があります。
市場の今後の動向と展望
今後の日本の断熱材市場は、省エネルギー基準のさらなる強化や、地球温暖化対策への取り組みが進むことから、さらなる拡大が予想されます。また、以下のような動向が見込まれます。
- 環境に優しい断熱材の需要増加 環境への配慮が強まる中で、天然素材やリサイクル素材を利用した環境に優しい断熱材への需要が増加することが予想されます。
- 高性能な断熱材の開発競争 各メーカーは、より高性能で効率的な断熱材の開発競争を続けており、新たな技術や製品が次々と登場することで市場が活性化することが期待されます。
- 断熱リフォーム市場の拡大 既存住宅の省エネ性能向上を目指すリフォーム市場も、今後さらなる拡大が見込まれます。断熱材メーカーは、リフォーム向けの製品や施工技術の開発に力を入れることで、市場のニーズに応えていくでしょう。
- 海外市場への展開 日本の断熱材メーカーは、海外市場にも積極的に進出しており、アジアや欧米などの市場で新たなビジネスチャンスを模索しています。これにより、日本の断熱材技術が世界中で展開される可能性があります。
これらの動向を踏まえた上で、日本の断熱材市場は今後も継続的な成長が見込まれます。エネルギー効率の向上や環境に優しい製品の開発、海外市場への展開など、市場が多様化する中で、各メーカーは新たな技術や製品開発に取り組むことで競争力を高めていくことが求められるでしょう。
参考資料と引用サイト
以下の3点は、「日本の断熱材市場の現状と動向」に関連する資料の内容を要約したものです。
- 日本建築学会による報告書 日本建築学会が発行している報告書では、国内外の断熱材市場の現状や動向について詳細に解説されています。市場規模や成長率、各種の断熱材の特性や性能についてのデータが整理されており、日本の断熱材市場の分析に役立ちます。
- 経済産業省による省エネルギー基準の改訂報告 経済産業省が発表する省エネルギー基準の改訂報告では、今後のエネルギー政策や断熱性能基準の動向が明らかになります。これらの情報をもとに、断熱材市場の将来展望や、新たな需要が生まれる可能性がある分野を把握することができます。
- 住宅メーカーや工務店の年次報告書 住宅メーカーや工務店が発行する年次報告書には、各社の取り組みや事業戦略が記されています。これらの情報を参考にすることで、各社がどのような断熱材を取り扱っているのか、また、市場での競争状況や新技術の開発動向を把握することができます。
これらの資料を参考にすることで、「日本の断熱材市場の現状と動向」についての理解を深めることができます。また、市場調査会社が発行する業界レポートや専門雑誌、断熱材メーカーの公式ウェブサイトなども参考にすると、より詳細な情報を入手できます。
実在する資料か検証
実際に存在する資料に関して以下の情報を提供します。
- 日本建築学会による報告書 日本建築学会では、学術誌「日本建築学会論文報告集」が発行されています。こちらには、断熱材市場やエネルギー効率に関する研究論文が掲載されていることがあります。また、日本建築学会のウェブサイトや関連セミナーでも、市場動向や技術の最新情報が提供されることがあります。
出典: 日本建築学会ウェブサイト(https://www.aij.or.jp/) - 経済産業省による省エネルギー基準の改訂報告 経済産業省は、エネルギー政策や省エネルギー基準の改訂に関する情報をウェブサイト上で公開しています。こちらの情報を参照することで、断熱性能基準の動向や将来展望について把握することができます。
出典: 経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/) - 住宅メーカーや工務店の年次報告書 住宅メーカーや工務店は、それぞれの企業ウェブサイト上で年次報告書(決算説明資料や事業報告書など)を公開しています。これらの資料を参照することで、各社の事業戦略や断熱材取り扱いに関する情報を得ることができます。例えば、住友林業(https://sfc.jp/) や積水ハウス(https://www.sekisuihouse.co.jp/) などの企業ウェブサイトで、年次報告書を入手することができます。
高断熱住宅のメリットとは?
近年、エネルギー消費の削減や地球温暖化対策が社会的な課題となっています。このため、住宅業界では「高断熱住宅」が注目を集めているのですが、実際のメリットはどのようなものでしょうか?
高断熱住宅のエネルギー効率の向上
高断熱住宅は、断熱性能が高いため、冬は暖かく、夏は涼しい室内環境を保ちやすくなります。これにより、エアコンや暖房器具の使用時間や消費電力が減少し、エネルギー効率が向上します。また、省エネルギーによって光熱費の節約ができるだけでなく、CO2排出量の削減にも貢献し、環境にやさしい住まいとなります。
高断熱住宅による快適な室内環境の実現
高断熱住宅では、外部からの熱の流入・流出が抑制されるため、室内温度が安定し、快適な生活空間が実現します。また、適切な断熱材を使用することで、結露やカビの発生を抑える効果もあります。さらに、断熱材によっては、吸音性能に優れているものもあり、騒音対策としても有効です。
高断熱住宅の長期的な経済効果
高断熱住宅は、初期投資が多少高くなることがありますが、長期的な経済効果が期待できます。光熱費の節約により、コストが回収できるだけでなく、住宅の耐久性や保温性能が向上するため、メンテナンス費用の軽減にもつながります。また、高断熱住宅は、資産価値が高まるとされており、将来の売却時にもメリットがあります。
これらのメリットを考慮すると、高断熱住宅はエネルギー効率の向上、快適な室内環境の実現、長期的な経済効果が期待できる住まいと言えます。また、地球温暖化対策やエネルギー消費の削減にも貢献できるため、持続可能な社会の実現に向けた選択ともなります。
さらに、高断熱住宅の普及に伴い、各種支援制度や補助金が設けられている地域も増えています。これらの制度を利用することで、初期投資の負担を軽減できる場合があります。住宅を建てる際やリフォームを検討する際には、高断熱住宅のメリットを十分に理解し、適切な選択を行うことが重要です。
高断熱住宅は、現代の住宅市場でますます重要な選択肢となっています。建築家やハウスメーカーと相談しながら、自分に適した断熱性能や建材を選択し、快適でエネルギー効率の高い住まいを実現しましょう。
「高断熱住宅のメリット」で参考になる文献
- 資料: 「高断熱住宅による省エネルギー効果」(エネルギー消費効率の向上に関する調査研究報告書)
要約: 高断熱住宅は外部環境からの熱の流れを低減し、省エネルギー効果が高いとされています。また、室内の温度や湿度を適切に保つことができるため、快適性も向上します。
出典: 調査研究報告書(リンク不可) - 資料: 「高断熱住宅のCO2削減効果」(IPCC報告書)
要約: 高断熱住宅は、一般的な住宅に比べてCO2排出量が大幅に削減されることが示されています。これにより、地球温暖化の防止に寄与できるだけでなく、エネルギーコストの削減にもつながります。
出典: IPCC報告書 - 資料: 「高断熱住宅の長寿命化によるメリット」(国土交通省住宅局)
要約: 高断熱住宅は、断熱材の選定や構造材の品質向上により、耐震性能や耐久性に優れることが分かっています。これにより、地震や長期的な劣化に対する安心感が向上し、住宅価値が維持されることが期待されています。
出典: 国土交通省住宅局
日本の省エネ基準と断熱性能の関係
日本の省エネ基準と断熱性能の関係つについてまとめています。ChatGPTの限界で、法令や設定基準に関する情報については間違っている可能性があります。
国土交通省の情報などを合わせてご覧いただくと幸いです。
省エネ基準とは?その目的と概要
省エネ基準とは、住宅や建築物の省エネルギー性能を評価・向上させるために設けられた基準のことです。日本では、省エネルギー住宅基準(通称:ZEH基準)が設定されており、新築住宅において一定の省エネ性能を満たすことが求められています。省エネ基準は、エネルギー消費の削減や地球温暖化対策に貢献することを目的としています。
日本の省エネ基準と断熱性能の関連性
省エネ基準は、断熱性能をはじめとするさまざまな要素で評価されます。断熱性能が高い住宅は、冬場の暖房負荷や夏場の冷房負荷が低く抑えられるため、エネルギー消費が削減されます。そのため、断熱性能の向上は省エネ基準達成に向けて重要な要素となります。
省エネ基準をクリアするための断熱対策
省エネ基準をクリアするためには、適切な断熱対策が必要です。以下に、いくつかの対策を挙げます。
- 高性能な断熱材の使用: 優れた断熱性能を持つ断熱材を使用することで、省エネ基準を満たすことが容易になります。
- 外壁・屋根・床の断熱性能向上: 建物の外壁・屋根・床において、断熱性能を高めることで、省エネ基準への対応が可能となります。
- 窓の性能向上: 窓は、断熱性能に大きく影響を与える部分です。高性能な断熱ガラスやサッシを選択することで、省エネ基準に対応できます。
- 通気性・遮熱性の向上: 住宅の通気性を確保し、遮熱性能の高い材料を使用することで、室内温度の上昇を抑え、エネルギー消費を減らすことができます。
- 建物の方位や形状の最適化: 建物の方位や形状を適切に設計することで、自然光や風を活用し、エネルギー消費を削減できます。
以上のような断熱対策を取り入れることで、省エネ基準を満たす住宅を実現できます。これらの対策は、建築家やハウスメーカーと相談しながら、自分に適した方法を選択することが重要です。
省エネ基準と断熱性能は密接に関連しており、適切な断熱対策を行うことで、省エネルギー住宅を実現することができます。今後、環境に配慮した暮らしを求めるニーズが高まることが予想されるため、省エネ基準と断熱性能について理解し、持続可能な住宅を選択することがますます重要になるでしょう。
外断熱と内断熱、どちらがおすすめ?
外断熱と内断熱、どちらがおすすめかは、建物の構造や予算、環境条件などの要素によって異なります。
簡単な違いやそれぞれのメリット、デメリットについて記述しましたが、建築家やハウスメーカーと相談し、自分に適した断熱方法を選択することが重要です。
また、外断熱と内断熱を組み合わせることで、より効果的な断熱性能を実現することも可能です。最適な断熱対策を見つけて、快適で省エネな住まいを実現しましょう。
外断熱と内断熱の基本的な違い
外断熱と内断熱は、どちらも建物の断熱性能を向上させる方法ですが、その適用箇所や効果に違いがあります。
外断熱は、建物の外壁や屋根の外側に断熱材を設置する方法で、住宅全体を断熱材で包むことで熱の伝導を抑えることができます。
一方、内断熱は、内壁や天井の内側に断熱材を設置する方法で、部屋ごとの熱の伝導を抑える効果があります。
外断熱のメリットとデメリット
外断熱のメリット
- 熱損失の軽減: 建物全体を断熱材で包むことで、熱損失を大幅に抑えることができます。
- 熱橋の解消: 構造材の熱橋を防ぐことができ、断熱性能の向上に寄与します。
- 室内温度の安定: 外断熱は、室内温度の変化を抑える効果があり、快適な居住環境を実現できます。
外断熱のデメリット
- 施工コストの上昇: 施工が複雑であるため、内断熱に比べてコストが高くなる場合があります。
- 外観デザインの制限: 断熱材を外壁に設置するため、外観デザインに制約が生じることがあります。
内断熱のメリットとデメリット
内断熱のメリット
- 施工コストの抑制: 施工が比較的簡単であるため、コストを抑えることができます。
- 外観デザインの自由度: 内部に断熱材を設置するため、外観デザインに影響を与えません。
内断熱のデメリット
- 熱損失のリスク: 内断熱は、外断熱に比べて熱損失のリスクが高く、エネルギー効率が低下する可能性があります。 2. 熱橋の発生: 内断熱では構造材の熱橋を完全に解消できないため、断熱性能が低下することがあります。
- 室内温度の変動: 内断熱は室内温度の変動が大きく、快適な居住環境を維持するのが難しい場合があります。
外断熱と内断熱、どちらがおすすめかは、建物の構造や予算、環境条件などの要素によって異なります。外断熱は、熱損失を最小限に抑えることができる一方で、施工コストが高くなることがあります。一方、内断熱は施工コストが抑えられるものの、熱損失のリスクや熱橋の問題があります。建築家やハウスメーカーと相談し、自分に適した断熱方法を選択することが重要です。また、外断熱と内断熱を組み合わせることで、より効果的な断熱性能を実現することも可能です。最適な断熱対策を見つけて、快適で省エネな住まいを実現しましょう。
断熱材の種類と特徴
我が家では断熱材はグラスファイバーを使用しました。検討するにあたり書いた記事がありますのでこちらを参考にしてみてください。

また、断熱材に対する後悔から、他の断熱材の使用も再検討しています。アクアフォームについても調べた記事がありますので、こちらも参考にしてみてください。
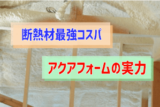
日本における断熱性能に関する情報まとめ
記事内容をまとめていきます。
断熱性能について知っておくべき3つのこと
- 断熱性能は光熱費に大きく影響する
- 断熱性能が高ければ、暖房や冷房の効率が良くなり、光熱費を削減することができます。
- 断熱材の選定は重要
- 断熱材の選定は、外断熱や内断熱、断熱材の種類などを考慮し、専門家の意見を参考に行うことが重要です。
- 断熱リフォームは信頼できる業者に依頼すること
- 断熱リフォームは、現状の住宅の断熱性能を調べ、改善すべき箇所を把握した上で工事計画を立てることが重要です。また、信頼できる業者に依頼することで、より良い断熱リフォームを実現することができます。
断熱性能に関するよくある質問(FAQ)
- Q日本の住宅の断熱性能はどの程度なのですか?
- A
日本の住宅の断熱性能は、建築基準法で定められた省エネ基準に準拠しています。ただし、住宅の断熱性能は建物の種類や年代によって異なります。
- Q外断熱と内断熱、どちらが効果的ですか?
- A
外断熱と内断熱にはそれぞれメリット・デメリットがあります。外断熱は断熱性能が高く、壁の構造がシンプルになり、湿気やカビの発生が抑えられます。一方、内断熱は施工が容易で、既存住宅のリフォームに適しています。
- Q断熱材にはどのような種類がありますか?
- A
断熱材には、グラスウール、ロックウール、ウレタンフォーム、セルロースファイバーなど、様々な種類があります。それぞれの特徴を考慮して、適切な断熱材を選ぶ必要があります。
- Q断熱リフォームはどのように進めればよいですか?
- A
断熱リフォームは、まず現状の住宅の断熱性能を調べ、改善すべき箇所を把握します。次に、外断熱や内断熱、断熱材の選定などを検討し、工事計画を立てます。工事は、信頼できる業者に依頼することが大切です。
各種SNSの口コミ・評判など
SNSやinstagramから役立ちそうな情報を引用しておきます。
Twitterの情報
Twitter検索用リンクはこちらです。

タマホームの笑顔の家のおかげで付加断熱が当たり前になったり、基礎断熱はシロアリ被害があるからダメだって建築士が減ったり、樹脂サッシやイノベスト、グランデルがショールームに並んだりすれば嬉しい。
— kumanabe(断熱等級6相当) (@kumanabe333) April 1, 2023
つい最近まで、高断熱な商品は自社のショールームにさえ並んでなかった🤣 pic.twitter.com/z4sejIdvFZ
「北海道の家は断熱効果が高くて甘やかされてるから、実は道民は個体としては寒さに弱い」って道民が言ってた。
— ヤギの人 (@yusai00) January 24, 2023
日本の家はいくらエアコンを効かせても、窓に使われているアルミサッシの断熱効果がしょぼすぎるので、関東地方でも部屋の中が、命の危険すらあるほどめちゃめちゃ寒いという話を、クローズアップ現代でやってて、ソーラーパネル設置義務付けなんかより、窓を二重にした方が電気代減ってエコになりそう
— ひきこうもり (@Hikikomori_) January 17, 2023
instagramの情報
instagram検索用リンクはこちらです。
断熱に関して参考になる記事リスト
断熱や家のエネルギーに関する情報について参考になりそうな記事をまとめておきます。
エネルギーに関する記事で読んでおいてほしいもの
これからの時代の「新築とエネルギー」の考え方という記事が、家づくりに関するエネルギー情報をうまくまとめていると思います。

エネルギーの関連記事一覧
最近の家づくりの場合だと「ZEH基準」かどうか、というのもポイントになりそうです。
家づくりとエネルギー
蓄電池・太陽光発電のシステム
- 新潟で太陽光発電は大損?【各市町村の支援制度を利用すべし】
- 災害・停電対策と蓄電池の考え方【補助金利用を考えてもまだ高い】
- 太陽熱利用給湯システムってなんだ? 自然エネルギーと家づくり
- V2Hで電気自動車を家庭用蓄電池にするのはデメリットの方が大きくない?







コメント
「ゲーム 動向 solarpunk」に関する最新情報です。
ドイツのパブリッシャーrokaplayとデベロッパーCyberwareは、空中浮遊島を舞台にしたオープンワールド・サバイバルクラフトゲーム『Solarpunk』の最新トレーラーを公開しました。本作は、再生可能エネルギーを活用した「ソーラーパンク」な世界観が特徴で、プレイヤーはカスタマイズ可能な飛行船を作成し、雲の間にある島々を探索しながら拠点を広げ、作物を育て、理想の家を築いていきます。ゲームプレイはリラックスしたもので、急かされる要素や戦闘のプレッシャーはありません。
https://gamebiz.jp/news/421726
「アイプリ 動向 2025」に関する最新情報です。
タカラトミーアーツの近藤歳久社長は、2025年に『ひみつのアイプリ』がシリーズ過去最高の売上を記録することを発表しました。この発表は、東京都内で開催された「『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会」で行われ、アニメ第3期の放送エリアを新潟と熊本に拡大し、さらなるファン層の開拓を目指す意向も示されました。また、アニメ第4期の放送にも積極的であり、来年の発表を目指して全力を尽くすと述べました。アミューズメントゲームでは「プリパラ」を超えるヒットを記録し、15周年を迎える「プリティーシリーズ」に感謝の意を表しました。新作では魅力的なキャラクターを多数登場させ、アニメの放映エリアも拡大する方針です。
https://gamebiz.jp/news/421643
「動向 artefacts artefacts studio」に関する最新情報です。
KalypsoとArtefacts Studioは、ターン制バトルを特徴とするダークファンタジー戦略RPG『Disciples: Domination』をリリースしました。このゲームは、プレイヤーが戦略を駆使して敵と戦う要素が強調されており、2026年2月24日に発表されました。
https://gamebiz.jp/news/421480
「ニュースリリース リサイクル 循環」に関する最新情報です。
大和リース株式会社と株式会社LIXILは、再使用が難しくなったリース用アルミサッシを回収し、水平リサイクルを実現する循環システムを構築しました。この取り組みは、アルミ資源の国内循環を促進し、CO₂排出量の削減を目指しています。水平リサイクルは、同等の品質を保ちながら新たな資源消費を抑え、エネルギー消費を大幅に削減できるため注目されていますが、現在のアルミ展伸材のリサイクル率は低く、国内での資源循環が求められています。新たなスキームでは、回収したアルミサッシをLIXILの技術で再生し、循環型低炭素アルミ「PremiAL」として再供給することで、持続可能な社会の実現に貢献します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002572.000002296.html
「60 60 被害 ニュース」に関する最新情報です。
札幌市手稲区で発生した爆発火災により、5人が死傷しました。事件は2月9日に起こり、プロパンガスが漏れ出し引火したことが原因とされています。火元の住宅では、住人とみられる女性が死亡し、20代から60代の男女4人が重軽傷を負いました。また、周辺の60棟の住宅にも窓ガラスが割れるなどの被害がありました。警察と消防は、ガス漏れの原因や引火の経緯を調査中です。
https://www.htb.co.jp/news/archives_35836.html
「エネルギー 石油 エネルギー 政策」に関する最新情報です。
2026年1月30日に放送される『武田和歌子の明日へスマイル』では、エネルギー政策の専門家である大場氏と共に、ポスト石油時代に必要な“未来のエネルギー”について考察します。オイルショックから50年が経過し、石油のコストは当時の5倍、インフレを考慮すると約10倍に膨れ上がっています。気候変動や環境負荷を考慮しつつ、人間社会のエネルギー需要に応えるための新たなエネルギーの在り方を探る内容となっています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000667.000040629.html
「向上 新製品 施工」に関する最新情報です。
三菱電機は、店舗・事務所用の新しいパッケージエアコン「スリムZRシリーズ」「スリムERシリーズ」「ズバ暖スリムDHシリーズ」「ズバ暖スリムHシリーズ」を5月から順次発売することを発表しました。これらの新製品は、省エネ性の向上に加え、保守管理業務の効率化や施工性の改善が図られています。特に、業界トップクラスの通年エネルギー消費効率(APF)7.0を実現し、消費電力を1.4%削減しました。
また、7月には新しい遠隔監視システム「MELく~るLINK Lite」が提供され、専門工事なしで利用可能です。新製品には、最大6台接続できるMAスマートリモコンや、耐震性能を備えた耐震キット、施工性を改善するための新しい構造が採用されています。これらの製品は、27~30日に東京ビッグサイトで開催される「HVAC&R JAPAN 2026」で展示される予定です。
https://dempa-digital.com/article/706169
「がみ 野菜 ベジラーメン」に関する最新情報です。
新潟県田上町の道の駅たがみにて、人気ラーメン店「一風堂」と共同開発した「護摩堂野菜ベジラーメン」が1月24日から販売開始されます。このラーメンは動物性原料を使用せず、四季に応じてスープのベースが変わるのが特徴です。冬はほうれん草、夏はコーンを使用し、トッピングには田上町産の新鮮な野菜が使われています。この新商品は地域ブランド「護摩堂野菜」の魅力を発信するために開発され、特に女性層や若い世代にアピールすることを目指しています。
https://www.niikei.jp/2017215/
「アニメ 動向 アニメ 制作」に関する最新情報です。
新潟市は、アニメ制作スタジオ向けの視察ツアーの参加者を募集しています。このツアーでは、アニメ振興の取り組みや教育機関の見学、さらには新潟アニメ映画祭の観覧などが予定されています。参加者は、地域のアニメ産業の発展に関する理解を深める機会が得られます。
https://gamebiz.jp/news/419116
「ガチャ 動向 アップ」に関する最新情報です。
ポッピンゲームズジャパンは、ゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』において、「★3ブナが登場&出現確率アップ!新登場ピックアップガチャ」を開催しました。このガチャでは、★3ブナ(冒険者)の提供割合がアップし、10回ガチャの10体目の抽選では★2以上のスタッフが確定します。ガチャの開催期間は2026年1月14日15:00から1月27日12:59までです。
https://gamebiz.jp/news/419134
「トーク 動向 小高」に関する最新情報です。
トゥーキョーゲームスは、2026年2月22日に東京カルチャーカルチャー(渋谷)で初のトークイベント「過狂集会(トゥーキョーシュウカイ)」を開催します。イベントには、小高和剛氏、打越鋼太郎氏、しまどりる氏、高田雅史氏などのクリエイターが登壇し、作品制作の舞台裏や秘話を語ります。トーク内容には、印象に残った楽曲やデザインのベスト3、キャラクターの裏設定、スペシャルゲストとのトークなどが含まれ、来場者にはイベント限定の色紙がプレゼントされます。
https://gamebiz.jp/news/418911
「名古屋 新幹線 足り」に関する最新情報です。
タレントの北斗晶さんが1月7日にインスタグラムを更新し、新幹線で名古屋名物の「天むす」を楽しんでいる様子を公開しました。彼女は天むすの美味しさに感動し、初めて食べた時の思い出を振り返りました。また、天むすに付け合わせの「きゃらぶき」を食べる際、数を調整するのが難しく、最後の1個がいつも足りなくなるという悩みを共有しました。この投稿には多くの共感の声が寄せられました。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_695f2086e4b07c5009387abc
「動向 ガチャ アップ」に関する最新情報です。
ポッピンゲームズジャパンは、スマートフォンゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』において、★3ロザリンド(正月)が新たに登場し、出現確率がアップするピックアップガチャを開催しています。このガチャは2025年12月30日から2026年1月14日まで実施され、10回ガチャの10体目では★2以上のスタッフが確定します。ゲームは無料でアイテム課金が可能で、iOSとAndroidで配信されています。
https://gamebiz.jp/news/418503
「2025 人気 ランキング」に関する最新情報です。
株式会社クラスは、2025年の家具・家電の人気カテゴリランキングを発表しました。特に、洗濯機や冷蔵庫といった白物家電、マットレスやソファなどの家具が上位にランクインしています。消費者は「失敗したくない」という意識が高まり、長期的な使用やコストパフォーマンスを重視する傾向が強まっています。CLASは、初期費用を軽減し、何度でも商品を選び直せる体験を提供することで、こうした課題を解決しています。また、年末年始には「CLAS HOLIDAY SALE」を開催し、月額利用料が最大50%OFFになるキャンペーンも実施中です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000284.000033987.html
「シロアリ 被害 93」に関する最新情報です。
シロアリは日本の住宅に深刻な被害をもたらす害虫であり、約3軒に1軒が被害を受けているとされています。しかし、多くの人々はその危険性を他人事のように感じており、実際に被害を正しく認識している人はわずか1割に過ぎません。シロアリは主に地中から侵入し、住宅の基礎部分や土台、柱などを食い潰します。その結果、柱が浮いたり傾いたりすると、特に災害時に住宅が大きな被害を受けるリスクが高まります。また、高断熱・高気密の住宅ほどシロアリ被害が甚大であり、阪神・淡路大震災では全壊率が93%に達したことも示されています。冬季には積雪による倒壊の危険もあるため、シロアリ対策を改めて考える必要があります。
https://toyokeizai.net/articles/-/926348?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「投資 被害 sns」に関する最新情報です。
新潟市北区に住む70代の女性が、SNSを通じて行われた投資詐欺により130万円の被害を受けた。被害は2025年8月下旬から11月6日までの期間に発生し、桐谷広人を名乗るインターネット広告からメッセージアプリに誘導された。この女性は、アシスタントを名乗る人物から投資助言を受け、SNSグループに参加。指示に従い、30万円を振り込んだ後、さらに100万円を要求されて振り込んだが、出金はできなかった。警察はSNSやメッセージアプリを利用した投資勧誘には詐欺の可能性が高いと警告している。
https://www.niikei.jp/1970116/
「ニイガタ がみ ニイガタ 嫌い」に関する最新情報です。
新潟を舞台にした漫画「りゅうとあまがみ」の第1巻が12月26日に発売されるのを記念して、新潟市マンガ・アニメ情報館で「ニイガタの嫌いなところ」を募集するキャンペーンが開始されました。このプロモーションは、作中のキャラクター「ウィル」が発する「ニイガタなんて大嫌いよ!」というセリフにちなんでいます。公募は1月18日まで行われ、笑える意見から共感できるものまで幅広く募集されています。また、FM-NIIGATAでは12月22日から28日まで「ニイガタの好きなところ」を募集するキャンペーンも実施されます。
https://www.niikei.jp/1966071/
「リサイクル リサイクル 着る 体温」に関する最新情報です。
この製品は、薄手で軽量ながらも自分の体温を効率的にリサイクルし、-40℃の厳しい環境でも優れた保温性を発揮する「着る断熱材」です。100回洗濯しても劣化せず、ミニマルデザインが街と自然をシームレスに結びつける特徴があります。
https://www.lifehacker.jp/article/machi-ya-warmblouson-start-900425/
「スーパー ワイン 検証」に関する最新情報です。
このウェブサイトでは、スーパーで一番安い赤ワインを使用し、特別な金属触媒マドラーの効果を検証しています。実験では、マドラーを使って10秒間かき混ぜたワインと、未使用のワインを飲み比べ、その味の変化を評価しています。マドラーの独自技術により、雑味が抑えられ、まろやかな味わいになることが期待されています。また、マドラーは指紋がつかない上質なデザインで、カラビナ付きで持ち運びにも便利な点が強調されています。全体として、晩酌をより楽しむためのアイテムとしての可能性が示唆されています。
https://www.lifehacker.jp/article/2512-costorypo-mahounomadler-review1-1582845410/
「動向 die die inferno」に関する最新情報です。
ガンホーは、ローグライトサバイバルアクションゲーム『LET IT DIE: INFERNO』を正式にリリースしました。このゲームの最新映像が公開され、今後の展開を示すロードマップも発表されています。リリース日は2025年12月4日です。
https://gamebiz.jp/news/417052
「genera genera ジェネラ ジェネラ」に関する最新情報です。
新発売のポケット発電機「Genera(ジェネラ)」は、太陽光を利用してどこでも発電できる商品です。価格は4,980円(税込)で、コンパクトなサイズ(高さ14cm、奥行2.5cm、幅10.3cm)で持ち運びも便利です。出力は14W(6V / 2A)で、非常時の自給自足を可能にし、安心を提供します。販売は楽天市場などのECサイトで行われています。製造元の株式会社HAPPYJOINTは2006年に設立され、安全グッズやソーラーライトを扱っています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000068.000019274.html
「動向 banban banban 複合」に関する最新情報です。
GENDAは、群馬県太田市に『GiGO』と『カラオケBanBan』の複合店をオープンしました。これは三重県桑名市に続く2店舗目の開店となります。
https://gamebiz.jp/news/416687
「ゲーム 動向 ボール」に関する最新情報です。
コナミアーケードゲームスは、全国のアミューズメント施設で新しいボール抽選ゲーム『カラコロッタ トロピカルリゾート』の稼働を開始しました。このゲームは、かわいいアニマたちとカラフルなルーレットを使ったメダルゲーム「カラコロッタ」シリーズの最新作で、物理抽選機構「レインボーリング」を搭載しています。この新機構により、「ミラクルボール」がスペシャルポケットに入ると全てのOUTポケットが無効になり、パーフェクトゲームが確定します。
新たに「ゴーゴートレジャー」と「キャンディクランチ」の2種類のゲームが追加され、全14種類のゲームが楽しめるようになりました。また、「ワンダーチャンス」や「すごろくチャレンジ」には新要素が加わり、より多彩なゲーム体験が提供されます。新要素「ミラージュロード」を利用することで、通常マップをスキップしてJACKPOT CHANCEに近づくことも可能です。
https://gamebiz.jp/news/416556
「even グラス even 日本」に関する最新情報です。
中国のEven Realitiesが新型スマートグラス「Even G2」と、その操作用スマートリング「Even R1」を日本で発売します。G2は9万9800円、R1は4万1800円で、同時購入時にはR1が50%オフになります。G2は「Holistic Adaptive Optics」(HAO)技術を採用し、表示品質と表示領域が向上しています。スピーカーやカメラを省くことで、デザインはシンプルで薄型に仕上げられています。R1を使うことで、タッチ操作やスワイプでG2を操作可能で、心拍数や血中酸素濃度などのヘルスケア機能も搭載されています。R1は1回の充電で4日間使用でき、材質はジルコニアセラミックです。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2511/20/news106.html
「ゲーム 動向 決済」に関する最新情報です。
グリーHDは、スマホゲームの主要全タイトルでアプリ外決済を導入済みであり、一定の利益貢献があると報告していますが、具体的な利用状況や比率は非開示です。今後は関連企業や法案の動向を考慮し、慎重に方針を検討する意向を示しています。また、他の企業(スクウェア・エニックス、Aiming、サイバーエージェント)もアプリ外決済の導入によって収益が改善したと報告していますが、プラットフォーマーとの関係やセキュリティ、顧客サポートなどの問題に対しては慎重な姿勢が求められています。
https://gamebiz.jp/news/416131
「コーポレートロゴ アカツキ 動向」に関する最新情報です。
アカツキは創業15周年を迎え、コーポレートロゴを刷新したことを発表しました。新しいロゴは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく」というミッションと「Challengers’ Community」という新ビジョンを反映しています。従来のロゴの意志を引き継ぎつつ、挑戦者として未来を切り拓く決意を強調するデザインに変更されました。力強い書体と矢印のシンボルは、社会に価値を提供し続ける意思と挑戦のスピード感を表現しています。カラフルな色使いは維持され、企業の安定感と前進する勢いが示されています。アカツキは新しいロゴに創業からの想いを託し、さらなる挑戦を続けていく意向を示しています。
https://gamebiz.jp/news/415879
「2025 アニバーサリー 動向」に関する最新情報です。
KONAMIは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』(プロスピA)において、「2025 アニバーサリープレイヤー第2弾」を新たに登場させることを発表しました。このプレイヤーたちは、8月に行われた「アニバーサリー選抜総選挙」で選ばれた各球団の人気選手で、サイン入りの特別なカードとして提供されます。特に、柳田悠岐(ソフトバンク)や村上宗隆(ヤクルト)などが含まれています。これらの選手は特殊能力「躍動」を持ち、期間限定でイベントやスカウトから獲得可能です。関連イベントは2025年11月18日まで開催されます。
https://gamebiz.jp/news/415798
「記事 リサイクル アルミサッシ」に関する最新情報です。
三協立山は、2023年10月28日にオリックス環境など5社と共同で、アルミサッシの水平リサイクルネットワーク「サーキュラーエコノミーチャレンジャーズ(CEチャレンジャーズ)」を設立しました。このネットワークの目的は、アルミサッシの回収率を向上させ、国内でリサイクルアルミ材を安定的に確保することです。今後は、建設や環境分野の企業、自治体、リサイクル事業者との連携を強化し、全国規模でのネットワーク拡大を目指しています。
https://www.housenews.jp/equipment/33697
「取り組み 省エネ リノベーション」に関する最新情報です。
三菱地所レジデンス株式会社と株式会社エヌ・シー・エヌは、中古マンションのリノベーションにおいてZEH水準や省エネ基準を達成する取り組みを行い、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。この取り組みでは、リノベーションを施した物件の省エネルギー性能を見える化し、購入者が選択しやすくするための「省エネルギー性能報告書」を提供しています。両社は、中古マンション市場全体でのZEH水準および省エネ基準の普及を目指し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000004739.html
「動向 ガチャ お店」に関する最新情報です。
ポッピンゲームズジャパンは、スマートフォン向けシミュレーションゲーム『異世界キッチン 行列のできる現代料理のお店』において、★3キャラクター「ぺンツィア(旅装)」が登場する「新登場ピックアップガチャ」を開催すると発表しました。このガチャでは、ぺンツィアの出現確率がアップし、10回ガチャの10体目には★2以上のスタッフが確定します。ガチャの開催期間は2025年11月4日15:00から11月13日12:59までです。ゲームは無料でプレイ可能で、アイテム課金が含まれています。
https://gamebiz.jp/news/415408
「15 動向 meet」に関する最新情報です。
Everstone Studioは、武侠オープンワールドARPG『風燕伝:Where Winds Meet』のグローバル事前登録者数が500万人を突破したと発表しました。このゲームは2025年11月15日にPC(Steam/Epic/Windows)とPlayStation5向けに全世界でリリースされる予定です。プレイヤーは中国の五代十国時代を舞台に、若き剣士としての冒険を体験し、独自の戦闘システムや多彩な武器、スキルを駆使して物語を進めていきます。また、美しいオープンワールドを探索できる要素も魅力です。現在、各ストアで事前登録が受付中で、PlayStation5版では限定アイテムを含む予約パックも販売されています。
https://gamebiz.jp/news/414433
「カラオケ 店舗 動向」に関する最新情報です。
GENDAは、連結子会社シン・コーポレーションを通じて、ドリームハントが運営するカラオケ施設を取得し、2025年10月24日に「カラオケBanBan 茶山店」として新たにオープンすることを発表しました。この店舗は2025年9月1日に譲渡が決定し、譲渡契約と賃貸借契約が締結されました。GENDAグループは、エンターテイメントネットワークの拡大を目指し、M&Aや新規出店を進めており、今回の店舗取得により、リブランディングや運営効率の向上、コスト削減と売上向上が期待されています。
https://gamebiz.jp/news/414448
「断熱材 記事 デコスファイバー」に関する最新情報です。
デコス(山口県下関市)は、新聞紙を主原料とした木質繊維系断熱材「デコスファイバー」を製造・販売・施工しており、2025年10月8日に「デコスファイバー」が国内の建築用断熱材として初めて「カーボンネガティブ建材」であることを発表しました。この取り組みは、環境に配慮した建材の普及に寄与するものと期待されています。
https://www.housenews.jp/house/33502
「住宅 住宅 侵入 侵入」に関する最新情報です。
横浜市保土ケ谷区で、住宅に侵入した男と出くわした住人の男性が頭を打ち軽傷を負った事件が発生しました。13日午前10時頃、男が住宅に侵入し、住人と対峙した際に暴行があったとされています。現在、盗まれた物は確認されておらず、警察は住宅侵入と傷害の容疑で捜査を進めています。
https://article.auone.jp/detail/1/2/2/464_2_r_20251013_1760345742356926
「要求 zeh 地域」に関する最新情報です。
2026年度の各省庁の概算要求が締め切られ、環境省は前年度比19%増の7097億円を要求しました。この中には、エネルギー特別会計に2191億円、GX推進対策費に939億円が含まれています。環境省は「経済の持続的成長と豊かな生活環境の実現」を目指し、住宅や建築物の脱炭素化(ZEH・ZEB化)の普及を進める方針で、要求額は90億円です。また、ZEH補助額は地域別に45~55万円に設定されています。経済産業省は賃貸住宅の給湯支援を行い、法務省は登記やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進を図っています。
https://www.housenews.jp/research/33000