台風、大雨、地震と災害は待ったなしで襲いかかってきます。
自然災害は、どれだけ想定しても「被災」しない方法を考えるのは難しいです。そもそも、災害の多い日本では「自然の脅威は受け入れ、耐え忍び、その後復興する」サイクルを確立していくことが大事。

まずは、自分でできることとして、「災害が起きた後の生活を立て直しやすくする」ことから始めようと思います。
今回は、エネルギーを溜めておき、復旧までの時間、生活を維持できるようにするための「蓄電池」についてご紹介していきます。
2024年の「家庭用蓄電池」新着情報まとめ
家庭用蓄電池について調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。
家庭用蓄電池に関する新着ニュース
家庭用蓄電池に関する新着ニュースをまとめています。
追い風吹く「蓄電池」関連株、再びの活躍ステージへ
- 原油価格が急上昇し、エネルギー価格の高騰が電気料金の上昇を招く可能性がある。
- 今夏も猛暑の予想により、電力需給の逼迫が懸念される。
- 2025年4月から東京都と川崎市での新築戸建て住宅などへの太陽光パネル設置が原則義務化される。
蓄電池関連の注目株
- ニチコン <6996> [東証P]: 23年3月期の営業利益は前期比71.1%増の110億円を予想。EV関連および家庭用蓄電システム市場での拡大を継続。
- オムロン <6645> [東証P]: 太陽光発電や蓄電池関連に注力。4月からグループ会社が自家消費型再生可能エネ発電設備のオンサイトPPAサービスを開始。
- 住友電気工業 <5802> [東証P]: 「レドックスフロー電池」に関心が高まる。2月に系統用蓄電池のマルチユースに対応したエネルギーマネジメントソリューション(sEMSA)の提供を開始。
- ファイバーゲート <9450> [東証P]: 商業施設や集合住宅向けWi-Fiサービスを展開し、新たに「オフグリッドパワー蓄電地」の開発に着手。
- 正興電機製作所 <6653> [東証P]: 住宅用・産業用蓄電システムに深耕。23年12月期の業績予想は、売上高が前期比20.0%増の300億円、営業利益が同38.8%増の20億円。
- ミライト・ワン <1417> [東証P]: 通信工事大手で、太陽光発電及び蓄電池システムの共同購入支援事業で実績が豊富。
- 日本工営 <1954> [東証P]: 大規模な蓄電プロジェクトを手掛ける。3月15日にベルギーで系統用大型蓄電池の供給を開始。
その他の蓄電池関連株
- ジーエス・ユアサ コーポレーション <6674> [東証P]、日本ガイシ <5333> [東証P]、**古河電池 <6937> [東証P]**なども蓄電池分野での動向に注目が必要。
蓄電池としてコスパに優れる電気自動車の評価
- バッテリー電気自動車(BEV)の大容量バッテリーは、V2H(Vehicle to Home)を使って家庭への給電にも利用可能。
- 家庭用蓄電池の相場は、バッテリー容量が4~16kWhで、100~250万円程度。
- テスラの「パワーウォール」は、バッテリー容量13.5kWhで1kWhあたり約8.15万円。
家庭用蓄電池とのコスパ比較
- 一般的に4人家族の1日の電力消費量は10~12kWh。
- 災害時の停電対策として、例えば5日分の電力50kWhを確保するには、パワーウォールを4台設置する必要があり、合計で440万円以上かかる。
BEVの蓄電池コスパランキング
- 2023年7月の日本でのV2H対応BEV車種は、10メーカー、14モデル。
- 1kWhあたりの価格で最もコスパが良いのはヒョンデ・アイオニック5のVoyageグレードで71,488円。
- 2番目はBYD・ATTO 3で75,137円。
- 7万円台はこれら2車種のみで、8万円台の5モデル、10万円以上の7モデルが続く。
BEVの導入を検討する際の提案
- BEVや太陽光パネル、V2H機器、家庭用蓄電池の導入には補助金が支給される場合がある。
- これらの導入は電気代の削減だけでなく、地球環境の観点からもカーボンニュートラル達成をサポートする。
家庭用蓄電池によるデマンドレスポンス実証を開始
- 伊藤忠商事と子会社のグリッドシェアジャパンが、家庭用蓄電池の遠隔制御の実証を開始。
- 今冬の電力需給逼迫回避と電力調達コスト低減を目的としている。
- 家庭用蓄電池を使用して、電力の需給バランスを調整する実証を行う。
詳細と背景
- 2022年度冬季はウクライナ情勢や新型コロナウイルスの影響で電力供給不足が懸念されている。
- 蓄電池による調整力が、再生可能エネルギーの更なる普及に寄与すると見込まれている。
実証の内容
- 蓄電池AIサービスを利用する顧客を対象に、電力の需給バランス調整実証を行う。
- 電力需給が逼迫する時間帯に、小売電気事業者の要請に応じて蓄電池を遠隔で充放電する。
- 実証参加者には対価が支払われる。
本実証の概要
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 提携小売電気事業者 | 東北電力㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、中部電力ミライズ㈱、九州電力㈱(2022年12月現在) |
| 対象 | 提携事業者の管内でグリッドシェアジャパンと契約の顧客 |
| 規模 | 最大約1万7千台、約51MW/167MWh |
| 実証期間 | 2022年12月中旬から2023年3月末頃まで |
伊藤忠商事は、この取組を通じて、日本の電力産業へのソリューション構築や脱炭素社会の実現に向けて貢献するとしている。
EVの使用済みバッテリーを蓄電池システムに活用
- 関西電力と東芝エネルギーシステムズが2023年度冬頃から電気自動車(EV)の使用済み電池を蓄電池システムに活用する実証実験を開始。
- 実証実験では、EV使用済み電池の特性や安全性を評価し、様々な充放電パターンにおける経済性評価を行う。
- 2024年度中に蓄電池システムの利活用に関するサービスを実用化する計画。
追加の情報とサービス展開
- 両社は以前から蓄電池の劣化診断技術を利用し、蓄電池の寿命を予測するアセットマネジメントサービスや、蓄電池システムの常時遠隔監視するスマート保守支援サービスなどの検討を進めている。
家庭用蓄電池の新製品情報
家庭用蓄電池の新製品情報についてまとめています。
新製品:Maxxta PowerBaseX’Pro 4610W
2023年5月31日時点での宏福商事合同会社のMaxxta PowerBaseX’Pro 4610Wについて紹介します。
Maxxta PowerBaseX’Pro 4610Wの特徴
- 1台で最大3,800W、2台接続で最大7,600Wの電力供給が可能。
- 6600wのマルチチャージ機能を持ち、単体で最大5,150W、PowerBaseX’Plusと接続すると6,600Wまでの充電が可能。
- 太陽光発電だけで最大3,000Wまで充電可能で、2〜3時間でのフル充電が実現可能。
価格
価格についての情報は提供されていません。
Maxxta PowerBaseX’Pro 4610Wのおすすめポイント
- 一般家庭の様々な電化製品の電力供給に十分な容量を持つ。
- 多機能な充電手段を持ち、緊急時や家庭のエネルギー管理にも最適。
- 他社製ソーラーパネルにも対応しており、既存のソーラーシステムに簡単に組み込める。
Maxxta PowerBaseX’Pro 4610Wの気になるところ、注意点
- 価格情報が明確に示されていない。
- 重量が55KGと少々重いため、運搬時には注意が必要。
Maxxta PowerBaseX’Pro 4610Wの購入時参考情報
- メーカー:RIVA BAY Holdings社
- 容量:4,608Wh
- 入力/出力:多機能で太陽光発電やAC電源からの充電が可能。
- その他の関連商品:PowerBaseXポータブルパワーステーション(PPS)、PowerBaseX’Traポータブルパワーステーション(PPS)、PowerBaseX’Plusバッテリーセルなど。
カナディアン・ソーラー、家庭用蓄電池「EP CUBE」を発売
- 大手電力7社の電気料金の引き上げを受け、太陽光発電への関心が高まる。
- 東京都では太陽光の導入に補助金を提供し、1キロワット時当たり15万円の補助が存在。
- カナディアン・ソーラーは家庭用の新しい蓄電池システム「EP CUBE」を発売。見た目の美しさと機能面での高性能を強調。
カナディアン・ソーラーについて
- カナダ・オンタリオに本社があり、全世界で業務用・家庭用のパネルを販売。
- 日本ではこれまでに個人向け住宅18万棟に太陽光パネルを設置。
- 新しい家庭用蓄電池システム「EP CUBE」はテスラの「パワーウォール」と同様のデザイン性を持ち、容量は3.3キロワット時のブロックから、積み上げることで最大13.3キロワット時まで増やせる。
- 「EP CUBE」の操作はスマホのアプリで行い、7月から日本と欧州での販売を予定。
パネル提供に関する情報
- 東京電力とLIXILの合弁会社「LIXIL TEPCOスマートパートナーズ」の太陽光パネル設置費用「実質ゼロ」プラン「建て得」に太陽光パネルを提供。
- 「建て得」は、太陽光発電システムの設置費用を実質的にゼロにするプランで、消費者の間で注目を集めている。
オムロン、家庭用蓄電池「KPBP-Aシリーズ」に新たな2機種を追加
- オムロンソーシアルソリューションズ(OSS)が家庭用蓄電システム「KPBP-Aシリーズ」に12.7kWhタイプと6.3kWhタイプの新機種を追加。
- KPBP-Aシリーズは太陽光発電とのハイブリッドシステムや全負荷対応のシステムとして組み合わせることができる。
- 新機種は夜間充電量を従来の50%から100%に倍増、夜間の料金が安価な電力を効率的に使用し、VPP市場などの電力取引にも対応。
新機種の詳細と価格
- 設置温度範囲の下限温度を従来の-10℃から-20℃に拡張。
- 価格(税込):
- 単機能蓄電システム:
- 12.7kWh: 430万円
- 6.3kWh: 266万円
- ハイブリッド蓄電システム:
- 12.7kWh: 492万円
- 6.3kWh: 328万円
- 全負荷型ハイブリッド蓄電システム:
- 12.7kWh: 575万円
- 6.3kWh: 411万円
- 単機能蓄電システム:
モノクローム、テスラ家庭用蓄電池Powerwallの認定販売施工会社に
- 株式会社モノクロームがTesla Powerwallの認定販売施工会社に認定された。
- Roof-1の購入者に対し、Tesla Powerwallの施工と販売をワンストップで提供する。
- Roof-1の導入顧客には、太陽光エネルギーの利用に関する全てのサービスをモノクロームが提供することを目指す。
Powerwallの仕様情報
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 蓄電容量 | 13.5kWh |
| 最高出力 | 7kW(ピーク)/5kW(連続運転) |
| 設置方式 | 床置き/壁掛け |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| サイズ | 高さ 1150mm x 幅 753mm x 奥行 147mm |
| 重さ | 114kg |
| パワーコンディショナー | 内蔵 |
| 太陽光発電システム接続 | 並列 |
| 販売価格 | 116万円(税抜) |
| 施工費用 | 別途かかります |
モノクロームに関する情報
- モノクロームは、2021年7月に創業者の梅田優祐とCTOのラス・イズラムによって設立。
- 理想の住宅用太陽光パネルとエネルギー制御ソフトウェアの問題を解決するために設立された。
- 事業内容は、屋根一体型太陽光パネルとHEMSの開発。
モノクローム公式HP
Instagram:@monochrome.so
Twitter:@monochrome.so
直近の家庭用蓄電池の補助金、お買い得なセール情報
家庭用蓄電池の商品で、補助金が交付される情報や「これはお得!」と感じたセール情報も残しておきます。購入の決め手となる価格の参考にどうぞ。
五泉市:住宅用省エネ設備等の設置費補助制度について
- 五泉市が、太陽光発電やエネファームの設置に関する補助金を提供。
- 令和5年度の補助金の予算は100万円。
- 募集期間は令和5年4月10日から先着順で、予算額に達した時点で募集締切。
補助対象システム
- 太陽光発電: JET等の認証を受けたもので、余剰電力の売電が必要。
- エネファーム: 国の補助対象となる機種。
- 定置用蓄電池: 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されている製品。
補助対象者の条件
- 五泉市内に住所を持つ者。
- 市税を滞納していない者。
- 五泉市内の業者に省エネ設備の設置を依頼した者、または新築住宅を購入した者。
- 他者との共有の場合、承諾書面が必要。
補助金額の詳細
| 太陽光発電 | エネファーム | 蓄電池 | |
|---|---|---|---|
| 補助基準 | 1kWあたり5万円 | 設置費の20% | 設置費の20% |
| 上限額 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
※補助金の算定には、太陽電池モジュールの公称最大出力とパワーコンディショナーの定格出力の低い方を基準とする。
手続きの流れ
- 交付申請→交付決定→実績報告→交付確定→請求→補助金のお支払い
恵那市住宅用新エネルギーシステム設置事業補助金
- 市が脱炭素社会を目指し、再生可能エネルギーを活用した住宅設備の導入を補助。
- 契約前に申請が必要。
- 予算が達した時点で受付終了。予算残額は約50%(8月10日現在)。
補助対象システムとその詳細
| 補助対象システム | 補助額と主な要件 |
|---|---|
| 定置用蓄電池システム | 3万円/kWh(最大15万円) – 太陽光発電と接続のシステム、環境共創イニシアチブ登録機器 |
| 次世代自動車充給電システム (V2H、VtoH) | 10万円 – 電気自動車から住宅に電力供給、次世代自動車振興センター登録機器 |
| 太陽熱温水システム | 設置費の3分の1(最大10万円) – 太陽熱を利用したシステム、ベターリビング認定機器 |
| 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 10万円 – ガスを利用し電気・熱を生成、燃料電池普及促進協会登録機器 |
補助の対象条件
- 補助対象システムを設置する住宅の所在地に住所があること。
- 自らが所有・居住する住宅や敷地に補助対象システムを設置。
- 申請年度の2月末日までに工事・支払いが完了見込み。
- 契約は交付決定後。
- 同じ住宅・補助対象システムに対して、過去にこの補助金を受けていないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 補助対象システム設置後、市の要請に応じて書類提出や現地確認を受け入れること。
注意:各システムには別の条件があるので、要綱や「補助金チェックシート」を確認してください。
会津若松市:令和5年度住宅用太陽光発電システム等設置補助金の変更点と概要
- 市は、住宅用太陽光発電システムや住宅用蓄電池システム、電気自動車用充給電設備の設置者に補助金を提供。
- 令和4年度までのFIT契約要件が撤廃され、FIT契約の有無は問わない。
- 子育て世帯の補助額が増額された。
補助金の詳細と交付条件
- 住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電池システム、電気自動車用充給電設備が補助対象。
- 各設備には特定の要件があり、該当しない場合は補助対象外。
- 補助金の交付は先着順で、予算上限に達した場合は受付終了。令和5年度の予算額は1,600千円、交付予定件数は16件程度。
- 申請は令和5年5月1日から令和6年3月29日まで、環境生活課にて行う。
| 設備の種類 | 一般補助額 | 子育て世帯補助額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 10,000円/㎾(最大40,000円) | 10,000円/㎾(最大40,000円) |
| 住宅用蓄電池システム | 8,000円/㎾h(最大40,000円) | 12,000円/㎾h(最大60,000円) |
| 電気自動車用充給電設備 | 40,000円(定額) | 60,000円(定額) |
| 補助額合計 | 最大80,000円 | 最大100,000円 |
現在の受付状況
- 令和5年度の補助金の交付件数は16件を予定。
- 現在の残り受付件数は12件(令和5年7月31日現在)。
- 受付は令和5年5月1日から開始され、先着順で行われている。
三豊市:令和5年度 住宅用太陽光発電システム・蓄電システム・HEMS設置費補助金
- 三豊市は、太陽エネルギー利用促進のため、太陽光発電システム、蓄電システム、及びHEMSの設置予定者へ補助金を提供。
- 令和5年度の補助金は予算額に達し、新たな予約受付は終了。ただし、繰越番号の交付は継続。
- 補助対象システムは、発電システム、蓄電システム、及びHEMS。
補足情報
- 予約申請期間は、令和5年4月14日から令和6年2月15日まで。交付申請は令和6年3月29日まで。
- 申請窓口は三豊市脱炭素推進室(三豊市役所1階環境衛生課内)。
- 予約申請には、現況を示すカラー写真や工事請負契約書のコピーが必要。
蓄電池が家庭での利用を勧められている
スマホのバッテリーに代表される「充電可能な電池」が蓄電池となります。
一般的な買い切り型の電池は、「放電」しかできませんが、蓄電池はその名の通り、「蓄電」することができるので、外部から電力が供給されれば、電気を貯めておき、繰り返し使用できることができます。
現在の主要バッテリーは「リチウムイオン」電池となります。高コストでしたが年々企業努力により価格が抑えられており、寿命も長いことから広く使われています。

ダイソンのバッテリーが死んだときに交換したのですが、その際にリチウムイオン電池について詳細な記事を書きましたので合わせてどうぞ。
蓄電池が注目されている理由

最近、蓄電池が注目されている理由として、以下の3つがあります。
- 災害対策として「停電時」に使用できるエネルギーを貯めておく
- 太陽光電池など「家で作ったエネルギーを貯めておく」システムとして組み込まれる
- 電気自動車の普及に伴い、自動車のバッテリーが「蓄電池」として利用できるようになった
蓄電池を家庭に設置するメリット
蓄電池はこれからのエネルギー問題を解決する「中心システム」になると考えられています。
電気料金が安くなる

夜間料金中に蓄電、日中に利用することで、「時間帯別電灯」という料金プランで契約している場合はお得になります。しかし、今後、夜間も同様にエネルギー消費が進めば夜間料金の値下げ幅は小さくなる可能性はあります。
創エネとの相性がいい
当サイトでも何度か扱いましたが、時代は「節電」に合わせて、各家庭で必要なエネルギーは自分たちで創り出す「創エネ」の時代です。さらに、作った電気を貯めておく「蓄エネ」にも注目が集まっています。

家づくりでは、ZEHにするかどうかで悩まれるところですね。
太陽光発電のFITが終了
太陽光発電による「固定価格買取」が終了し、2019年から売電期間が満了してきた家庭も出始めているところ。

「売れないんだったら、自分たちで効率よく使おう」というのが、蓄電池のメリット。
売電価格は今後も下がる
電気料金が値上げしている昨今、当然、売電価格が上がる見通しはありません。さらに、今後も家庭からの売電供給自体は増えていくことを考えると、あなたの家庭の売電価格が上がる可能性は薄いでしょう。
売電よりも購入電力を節約
つまり、売電については一旦考えるのをやめて、「電力を購入しないで済む方法」を考えた方が経済的ですし確実です。先ほども申し上げましたが、電気は今後も値上がりしていくものです。エネルギーロスを抑えつつ、自分たちで作った電気を効率よく使用することで、「全く電気を買わない」「買う電気は極力抑える」生活を目指すことで、エネルギー消費の心配を少しでも和らげることができます。
再生可能エネルギーと組み合わせる
京都議定書の目標となっていた2020年が終わり、2021年からは2030年のパリ協定で掲げられた「脱炭素社会」に向かって本格的に動き出すことになります。新しいエネルギーについては別記事でも紹介しています。

また、家づくりに関してのエネルギーの考え方についてもまとめてみました。

再生可能エネルギーという言葉の認知度は高まりましたが、「実際、何なの?」と聞かれて答えられる人は少ない。最低限、家づくりに関するエネルギーの話だけは知っておくと「未来で損することはない」ということで、簡単に情報をまとめておきました。
家庭用燃料電池
家庭用燃料電池としてエネファームの利用が進んでいますが、水素を使った家庭での発電には注目したいところです。

地熱発電
地熱発電に関する情報はこちらにまとめました。蓄電池は「電気エネルギーを貯める」いわば発電の受け皿になので、地域で地熱発電などに取り組む場合に、家庭に発電された電気を貯めるための蓄電池利用、という考え方はあると思います。

地中熱利用
地中熱と地熱がややこしいですが、地面の中は温度変化が少なく、地上との温度差を利用して冷暖房や給湯などの省エネに貢献することができます。
地中熱を家づくりに役立てる情報についてはこちらにまとめてあります。
蓄電池との関連で言えば、こちらは「消費電力を下げる」ための方法になるので、どちらかといえば関係ないかバッティングするシステムになりそうです。

小型風力発電
自宅に風力発電は実現可能性は低いですが、我々新潟県民は「冬場の日射量は期待できない」ため、太陽光発電と太陽熱利用が難しい地域と言えます。少しでも発電の助けにならないかと、風力発電についても調べてみました。
風力発電は、蓄電池が必要になるシステムです。しかも売電が難しいので発電した電気は家庭利用が中心になると考えると、蓄電池と連携したシステム構築を考える必要があります。

太陽光発電
太陽光は年中安定して利用できるエネルギーではなく地域格差が生じるので「冬も晴れ間が広まる地域が羨ましい」と指を加えてみているだけですが、そんな太陽光発電に関する情報も別記事にあります。
太陽光発電だけではありませんが、電気系統接続による売電をメリットにするというのは将来性の薄い話になります。自宅で利用するためのシステムとして、蓄電池は中心的な役割を担います。

太陽熱利用
太陽光を期待できる地域の場合、太陽光発電だけではなく、太陽熱を利用することも可能です。太陽熱利用は昔から存在する技術ですが、太陽光発電との相性も考えてハイブリッドに活用する方法についても開発が進められています。

非常用電源として利用する
私が「いいな」と思っているのがこれ。災害について改めて考えさせられた台風一過後、我が家でできることって何だと考えました。

意外と、人は避難しないし、避難したあとも、何やかんやでライフラインが途絶えた自宅で生活することになるよね
そう考えたときに、最低でも数日間は電気のある暮らしができればいいなと思い、容量の多いバッテリー、何だったら家庭用蓄電池でも取り付けようかと考えたところでした。
災害時に蓄電池があると便利

災害時に蓄電池を利用することをシムレーションしていきます。
電気が途絶えることでできなくなること
ざっと考えてみた、「我が家でできなくなること」です。
- スマホの充電
- 仕事
- 情報発信
- IP電話
- トイレ流せない
- 空調(冷房、暖房)
- 食糧保存(冷蔵、冷凍)
- 調理
- ミルク作成
仕事はまぁできないならいいとして(こら)、「思ったよりも電力に依存しているもの」が多いことに驚きます。
災害時に最低でも稼働させたい家電
- 冷蔵庫(食糧保持)
- 扇風機や最低限の空調
- PC
- スマホ
- 照明
上記家電を使用する場合、合計消費電力は約400Whとなります。
停電時に必要な電力
停電時に必要な電力は、家族の人数や稼働させたい家電によって異なるのですが、私なりにシミュレートしてみた結論としては、食糧維持のためにもできれば冷蔵庫は稼働させたいと思いました。

調理系はガスコンロにシフト、情報収拾のためのスマホ充電はモバイルバッテリーで十分かなと。

子供が不安になるから、必要な時は照明もつけられるといいんだけどね
電化製品の消費電力リスト
| 製品 | 消費電力 |
| IHクッキングヒーター | 1400~3000W |
| ドライヤー | 600~1200W |
| ホットカーペット | 500~800W |
| 洗濯機(洗濯時) | 200~400W |
| ノートパソコン | 50~100W |
| デスクトップコンピューター | 100~300W |
| 炊飯器 | 100~300W |
| エアコン | 300~3000W |
| 電子オーブンレンジ | 1000~1400W |
| 電気ポット | 900~1400W |
| 温水洗浄便座 | 300~700W |
| ファンヒーター | 10~450W |
| 冷蔵庫 | 100~300W |
| テレビ(液晶) | 300~500W |
パナソニックの蓄電池を実例

たとえば、パナソニックのスタンドアロンタイプの蓄電池システムなら、冷蔵庫、LED照明、液晶テレビ1台、スマホ2台充電で消費電力合計を265Whとした場合、約15時間使用することができます。
https://sumai.panasonic.jp/chikuden/lithium/feature.html

消費電力の算定がすこし甘いので、400Whで計算すると、9時間くらいといったところなので、つらい時間帯に関しては電気を使用することはできます。災害時は十分かと。
災害対策としては容量10kwhが狙い目
20時間程度使用する場合は、容量が10kwhになることが理想です。
モバイルバッテリーを組み合わせる
ただ、一つの蓄電池で賄わなくても、スマホはスマートバッテリーなどを利用し、キャンプ用の大型バッテリーなども併用すれば、家庭用蓄電池に関してはもう少し小型のものでもよくなります。
電気自動車を蓄電池として考える

2019年、たまに街で見かけはしますが、いまいち普及しない電気自動車(新潟だけ?)
ただ、蓄電池を買うことを考えると、「電気自動車導入が一番手っ取り早いな」という考えに至りました。
災害時に各家庭が電力を維持できれば、災害復興時の優先順位を変えてより多くの命を救うことができる可能性も増えます。また、考えようによっては、普及してしまえば、家庭への送電復旧は後回しにされてしまうとも言えます。補助金があるうちに電気系統を整備しておくのが得策です。
蓄電池として最高機能を持つ
将来的にはもっと電気自動車が広まるとは思いますが、水素式との兼ね合いもあるので振り切れないところはあります。

水素も利用方法が拡大されて、体内に取り込んでアンチエイジングに利用される時代です。水素も未来のある資源なので、将来的にどちらがインフラ整備されて利用しやすくなるのかがいまいち読みづらいところです。
私個人の読みとしては、既存の電気インフラが利用しやすい電気自動車に軍配が上がると思っていたのですが。
電気自動車は実用レベルでは日産と三菱が熱心に取り組んでいる一方で、TOYOTAとHONDAが「水素」なのか「電気」なのかがいまいち煮え切らない。
HONDAのエネルギー事業

HONDAはスマートコミュニティを提案しています。
TOYOTAは電気にシフト?
TOYOTAは2020年に大々的に電気自動車を投入する予定。
本当は、東京オリンピックが世界的なアピールの場になるはずだったけど、2019年現在、電気自動車の普及率を考えると、日本全体で後押し、というところまではたどり着けていないのが残念なところ。

オリンピックは万博のような「未来体験を展示」するのではなく、「未来を現実にした日本を体感」できるレベルまで落とし込んで欲しかったなぁ。
水素利用も検討しているけど、インフラ整備に時間がかかっているのと、世間の熱量との兼ね合いで、しばらくは電気に力入れるような感じかな。
蓄電池としてEVを買う

ちなみに、電気自動車の方が、蓄電池としてはより実用的なレベルで導入できます。
当然、車が実用レベルまで使えるくらいの蓄電池を搭載する必要がありますから、製品開発への力の入れようが違いますし、実際、高容量で実用的な蓄電池を搭載しています。
さらに、車が普及しないことには開発が無駄になってしまいますから、将来への投資も含めて、なるべく買いやすいような価格帯での販売努力がされています。
日産リーフ
たとえば、日産リーフであれば40kWh、リーフe+になると、62kWhの蓄電量をほこります。日産の試算ですが、家族が約4日間暮らせる電力を蓄えられるとのことです。(蓄電池は後ほど紹介しますが、10kWh程度)
https://ev.nissan.co.jp/LEAF/V2H
インフラ復旧は3日は想定すべし
電力のインフラ復旧は、3日以内に半分ほどが復旧できるとされていますが、お住まいの地域によっては復旧が遅れる地域もありますし、地域によっては1週間経っても復活しないところもあります。
EV用パワーコンディショナー
余談となりますが、リーフを買えば解決するわけではありません、残念ながら。

うっすら電気系統の工事が必要な予感がしますよね。
電気自動車(EV)とコンセントを繋ぐためには、EVパワーステーション(パワーコンディショナー)というものも必要になります。
EVパワーコンディショナーの費用
- ニチコンだと、50万円から90万円
- 三菱電機だと、170万円前後
V2Hシステム
V2Hシステムは、家と車を繋ぐシステムのこと(Vehicle to Home)です。先のパワーコンディショナー本体の価格や、車と家の電気系統を配線する工事などもあり、それなりの初期費用がかかります。
電気自動車にも補助金あり
一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金を利用するのが一般的です。記事執筆時が、補助金について調べるには微妙な時期だったので、公式HPを確認していただけると助かります。
家庭用蓄電池のコスト
これからお値段についても言及していきますが、電気自動車の導入費用をご覧いただけた方はうっすら勘付いたことでしょう。

さては、蓄電池って、高いな?
そうなると、気になってくるのがランニングコストの問題。投資に見合うだけの効果を、いつまで発揮してくれるのか。調べてみました。
使用できる期間・寿命について
バッテリー全般は「消耗品」ですので、買い替え・修理を考えなければいけないのですが、家庭用蓄電池は高額です。できるだけ長く使いたいのですが、「10年間」以上使うことを考えると損するかも。
サイクル数
リチウムイオン電池の寿命に関しては、サイクル数(空っぽになるのと満充電を繰り返すことができる回数)でカウントしていきます。各社寿命とするサイクル数を公表している場合もあります。
10年から20年が目安
しかし、使用しているごとに蓄電効率は落ちていくので、もう少し早く寿命が来ることが考えられます。
保証期間
メーカーごとに異なりますが、蓄電池自体の保証は10年が一般的なラインです。
蓄電池を選ぶポイント
- 蓄電容量
- 寿命(充放電回数)
- サイズ
- 創エネ(太陽光発電)などとの相性
- 停電時出力
- 保証
蓄電池各メーカーのワンポイント比較
ここから、さらに掘り進めて、どこの蓄電池を購入すべきか、ポイントをまとめました。
シャープ
シャープは太陽光パネルメーカーでもあるので、発電システムとの組み合わせに関してはトップクラスの実用性といえます。
長期利用を考えている場合
12,000回のサイクル数(充放電回数)を可能としているので、長期的な使用を考えている場合にはお得と言えます。
https://jp.sharp/e_solution/battery

コンパクトサイズや屋内型もあり、スペースに頭を抱える家庭にも導入しやすいのもポイントですね。
- 大容量タイプ:8.4kWh
- コンパクトタイプ:4.2kWh
パナソニック
パナソニックは、私の中では(好きか嫌いかは別にして)最強の家電総合メーカーです。
当然、太陽光プラス蓄電池のエネルギー業界にも顔を出しては、自社の強みである「家電開発力」の力でゴリ押しして業界を牽引しています。
https://sumai.panasonic.jp/solar_battery
家づくりはもうPana Homeにお任せだな
もう、最近ではパナソニックで家建てればもうそれで良くね、ってところまで感化されてます。日本のメーカーはもっと頑張ってパナソニックと競争しかけましょう。
全てのシステムをオールパナで
やはり、パナソニックの魅力は、「全部パナ」ができること。我々は自分たちで使う家電などのメーカーは多少気にしますが、蓄電システムで必要なってくる商品全てになると頭がこんがらがってきます。恐ろしいことに、パナソニックなら(ほぼ)全ての必要素材を自社提供することができます。

トラブルがあった時に、下手にたらい回しにされないのがいいですね。
しかも高機能
太陽電池モジュールも発電量が業界トップクラス、パワコンはもとより配電・分電盤も手がけるパナソニック、蓄電池もあれば省エネもできるパナソニック、スマートHEMS連携も容易とかなにこれ。
適宜追加もありか
連携システムが強力なので、最初はベーシックなシステムだけ組んでおいて、必要に応じて容量買い足しもありなんじゃないかと一考。
京セラ
災害時に、家で暮らすことまで考えると、10kWh以上は欲しいなとお伝えしたところですが、京セラの魅力は12.0kWhに対応し、約1日は家電製品を動かすことができるというところ。
https://www.shouene.com/battery/battery-compare/kyocera-battery.html
合計 約430W程度の場合、最大23時間※3連続使用できます。
https://www.shouene.com/battery/battery-compare/kyocera-battery.html
オムロン
オムロンは、太陽光発電のパワコンなどを手がける会社で、畜エネにも力を入れています。設計に自信があるので、塩害にも強くコンパクトであるため設置できる家庭を選ばないのが特徴。
https://www.omron.co.jp/energy-innovation/product
ニチコン
家庭用蓄電池のトップメーカー。もっとも「設置に対してリーズナブル」な製品を提供してくれるので、現実的に検討を始めた場合はまず「ニチコンか否か」を考えるといい。
https://www.nichicon.co.jp/products/ess/list.html
太陽光発電、E2H機器、トライブリッド、災害対策、モバイルなど、蓄電池に必要なトレンドワードは全て対応しているモデルもあるので、自分の必要性に合わせてニチコンからモデルを選び、必要時、他社と比較ってのが一番合理的。
伊藤忠商事 SmartStar L(スマートスターL)
伊藤忠の場合は、会社規模に着目し、独自のサービス展開に着目すべきです。
あいでんき
将来的には周辺住民と電気をシェアする構想ができています。

電気は送電距離が長いほどロスが大きくなるから、これからの時代を考えると画期的なアイデアだと思います。
2020年、HPが削除されていましたが、計画が進捗しているのか心配になるところです。
https://www.itochu.co.jp/ja/news/press/2018/181024_2.html
蓄電池を補助金を利用して購入するガイド
蓄電池を買いたいと思ったら、必ず「補助金」を調べてください。蓄電池が高いのは補助金のせいなんじゃないか、と思うくらいにお得に蓄電池を設置することができます。
ZEHで補助金
ZEH住宅は、1戸70万円に上乗せして、蓄電池最大で30万円あるいは設備費の1/3までの補助金を受けられます。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/zeh/h30.html
災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金
第二期の募集が2019年10月1日より開始しています。
https://sii.or.jp/kateichikudenchi31/public.html
対象となる蓄電システム
| 対象 | 10kW未満の住宅用太陽光発電を設置している(太陽光発電は新築・既築いずれも対象) |
| 対象外 | 10kW以上の太陽光発電を設置している |
| 対象外 | 太陽光発電を設置せず蓄電池だけを使う |
| 対象外 | 補助金交付が決まる前に蓄電池を契約・発注した |
補助金の概要
| 対象 | 10kW未満の住宅用太陽光発電を設置している(新築・既築いずれも対象) |
| 予算 | 38.5億円(1.5万件) |
| 補助額 | 上限60万円(蓄電池のタイプや容量により実際の補助額は異なる) 例:8kWh蓄電池システム※+HEMSが工事費込で42万円なら補助金額は23.6万円 ※ 災害対応型、15年保証の場合 |
| 公募期間 | 一次:2019年5月下旬(予定)~9月30日12:00必着 二次:2019年10月1日~11月29日12:00必着 |
災害対応型蓄電池を購入する場合のシミュレート
●家庭用蓄電システム販売価格:1,000,000円(蓄電容量8.0kWh 初期実効容量6.8kWh 15年保証) 家庭用蓄電システム工事費:250,000円
●HEMS機器販売価格 120,000円 、工事費 50,000円 の場合
蓄電容量8.0kWh×13.5万円=1,080,000円が目標価格となり、販売価格1,000,000円は目標価格以下のため2019年度目標価格以下の補助額を適用
家庭用蓄電システム設備費補助金額:初期実効容量6.8kWh×補助額20,000円=136,000円
HEMS機器設備費補助金額: 120,000円×1/2=60,000円だが、上限50,000円を適用
工事費補助金額 :(250,000円+50,000円)×1/2=150,000円だが、上限50,000円を適用
136,000円+50,000円+50,000円=236,000円が補助金の額となる
※上限価格は(1,000,000+250,000円+120,000円+50,000円)×1/3=473,333円
https://sii.or.jp/kateichikudenchi31/uploads/H31kaitei_kouboyouryou.pdf
https://sii.or.jp/kateichikudenchi31/uploads/H31kaitei_kouboyouryou.pdf
補助金の対象メーカー リスト
- アンフィニ株式会社
- 株式会社エヌエフ回路設計ブロック
- エリーパワー株式会社
- オムロン
- 京セラ株式会社
- シャープ株式会社
- 長州産業株式会社
- ニチコン株式会社
- パナソニック株式会社
- 株式会社Looop
- 田淵電機株式会社
















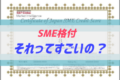
コメント
「業績 最高 最高 業績」に関する最新情報です。
旭化成ホームズは、2025年3月期の決算補足説明会を開催し、売上高9935億円(前年同期比8.8%増)、営業利益913億円(同14.9%増)を記録し、4年連続で過去最高業績を達成したと発表しました。2026年3月期の業績見通しとして、売上高1兆740億円(同8.1%増)、営業利益961億円(同5.2%増)を計画しており、5年連続での最高業績更新を目指しています。事業別では、建築請負事業や海外事業が好調でしたが、不動産開発事業は前年に比べて減益となりました。
https://www.housenews.jp/house/31480
「実証 運航 ドローン」に関する最新情報です。
テラドローン株式会社は、NEDOが推進する「次世代空モビリティ実現プロジェクト」の一環として、複数の異なるドローン運航管理システム(UTMS)が連携する環境での運航検証に成功しました。この実証では、KDDIを含む4社が異なるUTMSを使用し、同一空域内でのドローンの飛行計画の調整やフライトステータスの共有を行い、安全な運航を実現しました。特に、緊急空域設定時の情報共有や対応が確認され、「Terra UTM」の安定性と連携性が示されました。今後、テラドローンは「Terra UTM」の機能強化を進め、ドローン運航管理体制の確立を支援し、社会課題の解決に取り組む方針です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000352.000020194.html
「下旬 リフォーム 交付」に関する最新情報です。
国土交通省は、2025年度の長期優良住宅化リフォーム推進事業の事業者および住宅の受付を5月20日から開始しました。交付申請はⅠ期とⅡ期に分けて行われ、Ⅰ期の申請受付は5月下旬以降に始まる予定です。また、事前採択タイプの提案公募は5月20日から6月30日まで実施されます。詳細については、同事業の公式情報を参照することが推奨されています。
https://www.s-housing.jp/archives/385914
「サービス 産業 長州」に関する最新情報です。
長州産業と他2社は、5月8日に新しいHEMSサービス「+watt」を共同開発したと発表しました。このサービスは、NextDriveのゲートウェイ「Cube J」と、長州産業のエネルギーマネジメントシステムを基盤としています。家庭内のエネルギー管理を一元化し、蓄電池やV2H、太陽光発電と連携することで、スマートリモコンを通じて赤外線対応の照明や空調機器の遠隔制御も可能になります。
https://www.s-housing.jp/archives/385013
「合同会社 株式会社 会社」に関する最新情報です。
このコラムでは、会社設立における「株式会社」と「合同会社」の違いについて解説しています。著者の勝島一真氏は、個人事業主から法人化を考える際や新たに事業を始める際に、どちらの形態を選ぶべきかを検討する重要性を強調しています。
合同会社は2006年に新設された形態で、以前の有限会社に代わるものです。著名な企業も合同会社を選択しており、知名度は株式会社ほどではないものの、設立ペースは増加しています。両者の信用力は同等であり、融資の際も大きな差はないとされています。
コラムでは、株式会社と合同会社の特徴や利点を比較し、設立時の参考情報を提供しています。
https://www.niikei.jp/1575139/
「電力 競争 発電」に関する最新情報です。
公正取引委員会は、電力小売・発電分野における競争環境の実態や課題をまとめた調査報告書を公表しました。この報告書では、電力市場の状況や競争政策の課題が説明され、消費者が自分のニーズに合った電力会社や料金メニューを選択できることが重要であると強調されています。競争環境の整備が進むことで、効率化による価格低下が期待され、消費者の利益につながるとしています。また、電力の安定供給には、発電設備の整備と需給の調整が必要であり、火力発電の出力調整を活用することが有効であると指摘されています。
https://www.s-housing.jp/archives/384516
「hems スマホ スマホ hems」に関する最新情報です。
新しいスマホHEMSモデル「Nature Remo E2」と「Nature Remo E2 lite」が発売され、スタイリッシュな円筒形デザインと通信安定性の向上が特徴です。これにより、スマートメーターのスキャン時間が半減し、GX志向型住宅の補助金制度の要件である「高度エネルギーマネジメントの導入」に適合します。工事不要でコンセントに挿すだけで利用可能ですが、電力情報発信サービスの申し込みが必要です。
https://www.s-housing.jp/archives/384568
「アシスト自転車 アシスト自転車 万博 サイクル」に関する最新情報です。
2025年の大阪・関西万博では、YOUON JAPANが提供する「水素燃料電池アシスト自転車」が会場運営スタッフの移動手段として採用されています。この自転車は再生可能エネルギーを利用して水素を生成し、電気化学反応で走行をアシストします。具体的には、「H2 Bike Y800」「H2 Bike Y900」「H2 Bike S100」の3モデルが導入されており、1本の水素カートリッジで約50~60kmの走行が可能です。また、水素生成/充填一体機は現地で水素を生成し、太陽光パネルからの電力で運用されています。YOUON JAPANは持続可能な未来社会の実現を目指し、環境負荷の低減と移動効率の向上を図るとともに、今後のシェアサイクル事業への展開を進める意向を示しています。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/2012128.html
「万博 リング 上空」に関する最新情報です。
2025年大阪・関西万博では、好天に恵まれた日、一般来場者数が10万2810人に達しました。午後6時44分の日没前後には、「大屋根リング」がライトアップされ、木組みのシルエットが格子模様を生み出しました。午後7時過ぎには、大阪平野の夜景と対照的に、漆黒の夢洲に浮かぶリングの輪郭が際立って見えました。万博は開幕から1カ月を迎え、夜でも賑わいを見せています。
http://www.asahi.com/articles/AST55368WT55PQIP01SM.html?ref=rss
「万博 大阪 記者」に関する最新情報です。
2025年の大阪万博がゴールデンウィークに開催され、記者が急きょ訪れた際の体験が報告されています。会場は小雨の中、多くの来場者で賑わい、特に人気の「イタリアパビリオン」には長蛇の列ができていました。しかし、記者は事前予約をしておらず、当日予約も困難で、人気パビリオンには空きがない状況に直面しました。記者は「万博を舐めすぎていた」と反省しつつ、楽しそうに歩く人々を眺めながら、会場の熱気を感じていました。日本での万博開催は20年ぶりで、4月13日に幕を開けたことが強調されています。
https://gendai.media/articles/-/151787
「zeh 年度 最高」に関する最新情報です。
積水ハウスは、2024年度の戸建て住宅におけるZEH(ゼロエネルギーハウス)比率が過去最高の96%に達したと発表しました。これは、2013年に発売したオリジナルブランド「グリーンファースト ゼロ」の累積販売棟数が8万9352棟に達したことによるものです。2020年度以降、5年連続で90%超を維持しています。また、賃貸住宅「シャーメゾン」ではZEH採用率が77%に上昇し、分譲マンション「グランドメゾン」では2023年以降の販売物件が全てZEH-M Oriented以上となっています。さらに、同社は2030年までに製品使用時のCO2排出量を2013年度比で55%削減する目標を掲げており、2024年度には39.1%の削減を達成しました。
https://www.s-housing.jp/archives/383823
「zeh 補助金 京都」に関する最新情報です。
京都府では、令和7年度の住宅脱炭素化促進事業補助金(京都府ZEH補助金)の申請受付が4月1日に開始されました。補助金の上限は15万円/戸ですが、特定の条件を満たす住宅については、さらに25万円の上乗せが可能です。対象となるのは、京都府内産の木材や特定の製品を使用した住宅、または京都再エネコンシェルジュによる設計・施工の住宅です。この補助金は、新築戸建て住宅(店舗・事務所併用を含む)において、高断熱化や省エネルギー設備を導入したZEH、Nearly ZEH、ZEH Orientedに対して交付されます。また、4月24日には事業説明会が開催される予定です。
https://www.s-housing.jp/archives/383704
「ミャクミャク 万博 かわいい」に関する最新情報です。
大阪・関西万博会場で来場者を迎える「ミャクミャク像」が話題になっています。特にその後ろ姿が「かわいい」とSNSで注目を集めており、デザインを担当した引地耕太さんは、ミャクミャク像は日本の伝統的な「福助人形」をモチーフにしていると説明しています。像は正座して「いらっしゃいませ」とお出迎えするスタイルで、尻尾の存在にも驚きの声が寄せられています。引地さんは、多くの人がミャクミャクを可愛いと感じてくれたことに喜びを表し、デザインに込めた日本的な要素についても語っています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6805fbc3e4b079fefa27aaff
「ntt パビリオン 万博」に関する最新情報です。
大阪万博のNTTパビリオンでは、次世代通信インフラ「IOWN」を活用したユニークな建築技法やパフォーマンスが注目されています。特にPerfumeを起用した演出が話題です。また、NTTグループは来場者の体験を向上させるために「EXPO2025 Personal Agent」というスマートフォンアプリを提供しており、これにより来場者を効果的にナビゲートすることを目指しています。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2504/16/news038.html
「廃校 利活用 アイデア」に関する最新情報です。
新潟県上越市は、少子化による統廃合で廃校となった市立小中学校の旧校舎15施設について、民間からの利活用アイデアを募集する市場調査を2025年6月に実施します。この調査は、民間事業者との対話を通じて市場性や活用策を把握することを目的としています。対象となるのは、1991年から2025年に閉校した校舎で、すでに取り壊されたり他用途に転用された校舎は除外されます。参加を希望する法人や法人グループは、6月4日までに申し込む必要があり、説明会やバスツアーも開催される予定です。
https://www.joetsutj.com/2025/04/15/171504
「住宅 復興 プラン」に関する最新情報です。
国土交通省は、能登半島地震からの復興状況を報告し、2024年度末までの見通しを示しました。輪島市を含む8市町では、約3000戸の災害公営住宅の測量・設計が進められています。自力での住宅再建が難しい被災者に対しては、「災害復興住宅融資」や「高齢者向け返済特例」などの支援が行われています。また、被災者が具体的な再建イメージを持てるように、地震に強く地域産材を活用した55件の住宅プランを掲載した「いしかわ型復興住宅モデルプラン集」が作成され、仮設住宅に入居する世帯に配布される予定です。
https://www.s-housing.jp/archives/382029
「バッテリー バッテリー 給電 モバイル」に関する最新情報です。
山善は、モバイルバッテリーから給電可能な「PD仕様扇風機シリーズ」を3月下旬から発売します。このシリーズには、DCモーターを搭載したリビング扇風機やミニ扇風機、サーキュレーターが含まれ、価格は7,980円から14,800円の範囲です。全機種にはUSB Type-Cポートが搭載されており、付属のPD対応アダプターや市販のモバイルバッテリーを使用することで、電源が届かない場所でも利用可能です。また、従来のAC電源扇風機と同等の風量を実現しています。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/2001699.html
「cell car car cell」に関する最新情報です。
細胞免疫療法は、手術療法、抗がん剤療法、放射線療法に続くがん治療の第4の柱として、国内外で広がりを見せています。特に、治癒が難しい難治性がんに対して、キメラ抗原受容体T(CAR-T)細胞療法やT細胞誘導抗体(T-cell engager:TCE)が効果的な治療法として期待されています。2025年3月6~8日に開催された第22回日本臨床腫瘍学会学術集会では、これらの進展についての議論が行われました。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/60393
「システム ハイブリッド マルチ」に関する最新情報です。
マルチV2Xシステムに新たに「太陽光+EV」のハイブリッド仕様が追加され、これにより太陽光発電システムと電気自動車(EV)の導入が容易になります。このハイブリッドV2Xシステムを選ぶことで、発電した直流電気を直接EVに充電でき、従来の単機能システムでの電力変換ロスが解消されます。東京都港区では、住宅向けの「KPEP-A-2シリーズ」の販売を4月から開始する予定です。
https://www.s-housing.jp/archives/379259
「よく よく 電気 オムロン」に関する最新情報です。
オムロンは、家庭用の太陽光発電と電気自動車(EV)を連携させるマルチV2Xシステム「KPEP-A-2シリーズ」を2025年4月に発売予定です。このシステムは、従来の単機能型に加え、太陽光発電とV2Xを統合したハイブリッド型を提供します。V2X(Vehicle to X)は、EVと他のシステムとの相互連携を可能にし、電気自動車を大容量の蓄電池として活用できます。新製品は、EVとの接続を管理する「EVユニット」、太陽光発電システムとの連携を担当する「PVユニット」、および電力変換を行う「パワーコンディショナ」で構成されています。また、既存の太陽光発電システムに後付け可能で、段階的な導入によって初期費用を抑えることができます。
https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1660595.html
「一体型 一体型 太陽光発電 太陽光発電」に関する最新情報です。
YKK APは札幌市と連携し、ペロブスカイトを用いた建材一体型太陽光発電の実証実験を行います。実験は「さっぽろ雪まつり」会場で2月4日から11日まで行われ、ムービングハウス「SAPPORO ZERO BOX」が設置されます。この実証実験では、ペロブスカイト太陽電池を利用した内窓タイプの発電システムが展示され、札幌市の環境への取り組みも紹介されます。札幌市は2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げており、YKK APは窓や壁面を活用した発電システムの開発を進めています。今回の実験を通じて、雪国におけるこの技術の効果を確認し、社会実装を目指します。
https://www.s-housing.jp/archives/375704
「2024 ランキング 創業」に関する最新情報です。
2024年の有隣堂年間ベストセラーランキングが発表され、全店で『地球の歩き方 横浜市 2025~2026』が2位にランクインしました。この書籍は、横浜の観光スポットを紹介し、横浜銘菓「ハーバー」とのコラボや独自の表紙カバー展開などで話題を集めました。ランキングは、自社開発の店舗運営システム「Book Store Central(BSC)」を用いて収集した販売データに基づいています。2024年は有隣堂の創業115周年を迎え、未来に向けた新たな取り組みが進められています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000135515.html
「honda オデッセイ ヴェゼル」に関する最新情報です。
Honda Cars 新潟県央 U-Select燕三条では、1月10日版のおすすめ中古車情報を提供しています。注目の車両には、現行のオデッセイハイブリッド(2023年式、走行距離13,530km、支払総額5,003,230円)とヴェゼルハイブリッド(2014年式、走行距離65,765km、支払総額1,267,920円)が含まれています。特典として、「にいがた経済新聞を見た」と伝えた方にはダッシュボード抗菌コートがプレゼントされます。店舗は新潟県燕市にあり、営業時間は9:30から18:00まで、火曜日と水曜日が休店日です。興味のある方はぜひ訪れてみてください。
https://www.niikei.jp/1367947/
「申請 終了 受付」に関する最新情報です。
国土交通省などの3省が連携して実施している給湯省エネ事業において、ワンストップ申請の受付が12月19日に終了し、予算に対する補助金申請額が95%に達しました。リフォームの補助金申請は97%に達した時点で終了する見込みです。ワンストップ申請終了後も、予算上限に達するまで、または12月31日までは個別に交付申請が可能ですが、申請の集中による通信不安定や書類不備による却下のリスクがあるため、早めの申請が推奨されています。
https://www.s-housing.jp/archives/373750
「dr dr 実証 シャープ」に関する最新情報です。
東京電力ホールディングス、東京電力エナジーパートナー、エナジーゲートウェイ、シャープエネルギーソリューションの4社は、シャープ製の家庭用蓄電池を遠隔制御する需要応答(DR)の実証を2024年12月27日から開始します。この実証では、クラウドを活用したHEMSサービス「COCORO ENERGY」と連携し、蓄電池をPPHを通じて遠隔制御することで調整力創出量の検証を行います。クラウド連携された蓄電池をPPHに接続するのは今回が初めての試みです。
https://corporate.jp.sharp/news/241223-a.html
「本社 ppa エネルギー」に関する最新情報です。
シナネンホールディングスグループは、2024年11月から東京都品川区の新本社ビルに対して、オフサイトコーポレートPPAサービスを通じて100%の実質再生可能エネルギー電力供給を開始します。この取り組みは、クリーンエナジーコネクトが開発した太陽光発電所からの電力を利用し、脱炭素化を推進するものです。
PPA(電力購入契約)を通じて、シナネンホールディングスは運転開始から15年以内の太陽光発電所からの電力を調達し、環境価値を提供します。このモデルにより、再生可能エネルギーへの投資を促進し、化石燃料の代替を実現します。また、シナネンは小売電気事業者として、昼間に発電した余剰電力を市場に売却し、その環境価値を取得することで、全ての電力を実質再生可能エネルギー由来とすることが可能になります。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000053091.html
「停電 800 800 停電」に関する最新情報です。
2024年12月19日午後2時24分、新潟県上越市で約800戸が停電しました。停電の影響を受けている地域には飯田、北方、高和町、妙油、三和区、牧区が含まれています。停電の原因は調査中で、東北電力ネットワークが復旧作業を進めています。
https://www.joetsutj.com/2024/12/19/150929
「モデル 11 11 機種」に関する最新情報です。
ミーレは、食器洗い機「G7000シリーズ」の新モデル11機種を12月16日に発売することを発表しました。
https://www.s-housing.jp/archives/372134
「honda ステップワゴンスパーダ フリードハイブリッド」に関する最新情報です。
Honda Cars 新潟県央 U-Select燕三条では、12月13日版のおすすめ中古車情報を提供しています。注目の車両には、フリードハイブリッド(2020年式、走行30,661km、支払総額2,477,220円)とステップワゴンスパーダ(2020年式、走行43,453km、支払総額2,864,090円)が含まれています。どちらの車両も部分保証が付いており、特典として「にいがた経済新聞を見た」と伝えるとダッシュボード抗菌コートがプレゼントされます。詳細情報は店頭で確認可能です。
https://www.niikei.jp/1327751/
「体験 日産 ハンズオフ」に関する最新情報です。
新潟県上越市の「日産サティオ新潟西上越インター店」で実施されている「HELLO NISSANプログラム」が好評を得ています。このプログラムでは、日産の電気自動車に乗り、高速道路での「ハンズオフドライブ」機能を体験できます。参加者からは「わくわくする」「感動した」といった声が寄せられており、体験後の満足度も高いです。試乗は予約制で、一般道や高速道路を含む最長120分の体験が可能です。さらに、体験者にはカフェのオリジナルスイーツがプレゼントされる特典もあります。セールスを目的としないプログラムで、電気自動車の先進技術を体感できる貴重な機会です。予約は随時受け付けています。
https://www.joetsutj.com/2024/12/08/070000
「モジュール モジュール 機種 住宅」に関する最新情報です。
ネクストエナジーは、狭小住宅向けにN型セルを採用した太陽電池モジュール2機種の販売を2025年1月8日に開始することを発表しました。
https://www.s-housing.jp/archives/371663
「利益 最高 過去」に関する最新情報です。
積水ハウスは2025年1月期第3四半期(2~10月)の連結決算を発表し、売上高が前年同期比30.8%増の2兆8630億1600万円、営業利益が同24.6%増の2326億2500万円と、いずれも過去最高を記録しました。全てのビジネスモデルで増収増益が達成されました。戸建住宅事業では、ZEH住宅やスマートホームサービスの好調な受注により、売上高は3431億100万円(0.3%増)、営業利益は288億800万円(9.5%増)となりました。一方、国際事業は新築住宅の需要増加により売上高が8511億1100万円(155.9%増)、営業利益は573億5300万円(72.2%増)と大幅に成長しました。特に、米国のMDC社を完全子会社化したことが寄与しています。
https://www.s-housing.jp/archives/371769
「chrome chrome 売却 google」に関する最新情報です。
アメリカ司法省は、Googleに対してChromeブラウザの売却を求める提言を行いました。この要求は、Googleが他社に対して自社の検索エンジンを優先させるために支払っていたことに関連しており、ChromeやAndroidの売却は直接的には関係がないとされています。この動きは、Googleの市場支配に対する規制強化の一環として捉えられ、業界に大きな影響を及ぼす可能性があります。
https://www.lifehacker.jp/article/2412-doj-wants-google-sell-chrome/
「電力 実質 エネ」に関する最新情報です。
イオンディライト株式会社は、脱炭素社会の実現に向けて、2024年11月から全ての本社・支社事務所で使用する電力を実質再生可能エネルギーに切り替え、CO2排出量を実質ゼロにすることを発表しました。この取り組みでは、丸紅新電力が提供する非化石証書を活用し、年間約600トンのCO2削減が見込まれています。イオンディライトは、2021年に制定したサステナビリティ基本方針に基づき、ESG経営を推進し、環境負荷の低減に努めています。今後も脱炭素社会の実現に貢献し、持続的な成長を目指すとしています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000060460.html
「honda トラック アクティ」に関する最新情報です。
Honda Cars 新潟県央 U-Select燕三条では、11月29日版のおすすめ中古車情報を提供しています。特に注目の車両は、2019年式のN-BOX(走行距離94,591km、支払総額864,550円)と、2018年式のアクティトラック(走行距離11,638km、支払総額1,216,270円)です。どちらも部分保証が付いており、延長保証も可能です。また、にいがた経済新聞を見たと伝えると、成約特典としてダッシュボード抗菌コートがプレゼントされます。店舗の営業時間は9:30から18:00までで、火曜日と水曜日が休店日です。
https://www.niikei.jp/1306304/
「10 bev bev 環境」に関する最新情報です。
トヨタから独立したLean Mobilityが開発した3輪電動車「Lean3」は、全長約2.5mのパーソナルBEVで、2025年の量産を目指しています。この異質なモビリティは、10年の開発期間を経て完成に至りました。Lean3は、車体が傾く独特の感覚を提供し、変化し続けるBEV環境において新たな選択肢を提示しています。
https://toyokeizai.net/articles/-/840678?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「エヌ 利益 計算」に関する最新情報です。
エヌ・シー・エヌの2025年3月期第2四半期決算が発表され、売上高は前年同期比で8.7%減の38億5100万円となったが、営業利益は281.5%増の8800万円、経常利益は1億1800万円、最終利益は6800万円と、各段階利益が黒字化した。住宅分野では木材相場の安定により平均売上金額が減少し、SE構法の出荷数も減少したが、構造計算の出荷数は増加し、特に非住宅木造建築物の構造計算出荷数が好調だった。法改正に向けた準備が進んでいることも影響している。
https://www.s-housing.jp/archives/369946
「量産 honda パイロット」に関する最新情報です。
Hondaは2023年11月21日に、栃木県さくら市に全固体電池のパイロットラインを公開しました。このラインは2025年1月に稼働を開始し、量産プロセスの技術検証を行います。Hondaは2040年までにEVとFCEVの販売比率を100%にする目標を掲げており、パイロットラインを通じて量産技術やコストの検証を進めるとともに、バッテリーセルの仕様開発も行います。20年代後半には量産を開始し、電動モデルを市場に投入する計画です。本田技術研究所の大津社長は、全固体電池がEV時代の革新技術であり、Hondaの変革を推進する重要な要素であると述べています。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2411/21/news119.html
「box honda にい」に関する最新情報です。
Honda Cars 新潟県央 U-Select燕三条では、最新のHonda認定中古車情報を提供しています。特に、N-BOXとN-VANのモデルが紹介されており、N-BOXは2023年式で支払総額1,850,550円、走行距離454kmの車両が販売されています。また、N-VANは2020年式で支払総額1,390,950円、走行距離46,871kmのモデルがあり、どちらも部分保証が付いています。さらに、にいがた経済新聞を見たと伝えることで、成約特典として「ダッシュボード抗菌コート」がプレゼントされるキャンペーンも実施中です。
https://www.niikei.jp/1284306/
「価格 需給 連続」に関する最新情報です。
国土交通省が発表した調査によると、主要建設資材の価格は3カ月連続で「横ばい」となっており、需給動向も全ての資材で「均衡」を保っています。また、在庫状況は24カ月連続で「普通」とされています。この調査は、約2000社の生産者や建設業者からデータを収集し、建設資材の需給、価格、在庫の変動を把握することを目的としています。
https://www.s-housing.jp/archives/364564
「honda シビック ライフ」に関する最新情報です。
Honda Cars 新潟県央 U-Select燕三条では、Honda認定中古車のおすすめ情報を提供しています。現在、シビックタイプRとライフの2車種が特に注目されています。
シビックタイプRは、支払総額191.8万円で、2009年式、走行距離18.6万km、修復歴なしの車両です。俊敏な加速と優れた足回りが特徴で、希少なシルバーのボディカラーが魅力です。
一方、ライフは支払総額41.8万円で、2011年式、走行距離5.6万km、こちらも修復歴なしです。快適な車内空間とデザインが評価され、老若男女におすすめの軽自動車です。
さらに、にいがた経済新聞を見たと伝えると、成約特典として「ダッシュボード抗菌コート」がプレゼントされます。詳細は店舗にて確認できます。
https://www.niikei.jp/1199008/
「風呂敷 ルーム ふろしき」に関する最新情報です。
【OMO5京都三条 by 星野リゾート】は、2025年4月に「ふろしきルーム」というコンセプトルームを開設予定です。このルームでは、風呂敷専門店「むす美」との協力により、さまざまな風呂敷の魅力を体験できます。風呂敷は日本の伝統的なアイテムであり、日常生活での新しい使い方やアートとしての楽しみ方を提案することを目的としています。また、宿泊者には風呂敷の使い方を案内するパンフレットや、OMOオリジナル風呂敷のプレゼントも用意されており、旅行後も風呂敷を活用できるよう配慮されています。風呂敷はサステナブルなアイテムとして、文化を知り、創造する喜びを提供することを目指しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001106.000033064.html
「合同会社 系統 系統 蓄電池」に関する最新情報です。
日本エネルギー総合システム株式会社(JPN)は、系統用蓄電池事業の第1号案件「霧島蓄電所」の稼働を開始したことを発表しました。このプロジェクトは、JPNが開発・運営を行い、株式会社グリーンエナジー&カンパニーおよび合同会社DMM.comと共同出資で設立した「合同会社霧島蓄電所」がアセットを保有します。霧島蓄電所は、鹿児島県霧島市に位置し、定格出力1.99MW、定格容量8.128MWhのリン酸鉄リチウムイオン電池を使用しています。さらに、RE100電力株式会社のアグリゲーションシステムを活用して電力運用の最適化を図り、事業ノウハウの蓄積と運営基盤の強化を目指します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000113700.html
「シェア 値下げ タイプ」に関する最新情報です。
パナソニックハウジングソリューションズは、2024年9月20日に新製品「アラウーノ S160シリーズ」を発売し、便ふた自動開閉機能付きタイプの希望小売価格を現行製品から13%引き下げることを発表しました。この値下げは、グループ内の温水洗浄便座事業の一元化による合理化効果により実現しました。業界全体が原材料費や人件費の上昇を理由に値上げを続ける中、同社は逆行して値下げを行うことで中級価格帯のトイレ市場での販売数量増加とシェア拡大を目指しています。これは、2022年以降に価格改定を行った大手メーカーの中で初めての試みです。
https://www.housenews.jp/equipment/27680
「九州 台風 大雨」に関する最新情報です。
台風10号は30日未明から朝にかけて九州北部を横断しましたが、暴風域は消失しました。しかし、動きが遅いため、九州、中国地方西部、四国、関東、東海、近畿で断続的に大雨が降っています。気象庁は土砂災害や浸水、河川の増水に対して厳重な警戒を呼びかけています。台風は勢力を保ったまま9月1日まで四国付近を東へ進む見込みで、その後は熱帯低気圧に変わると予想されています。予想される雨量は、四国で400ミリ、東海300ミリ、近畿200ミリなど、各地で非常に多くの降水が見込まれています。
https://www.s-housing.jp/archives/362075