エネファーム、ややこしいですよね。

省エネ系は安易なネーミングが多くて、エネ〇〇に混乱している方も多くいらっしゃるかと思います。というか、いまだに人に聞かないとわかりません。
エネファームは、ガス会社がこぞってお勧めする「省エネ」製品です。
具体的な説明は後回しにしますが、大事なことがひとつだけあるので、それだけお持ち帰りください。
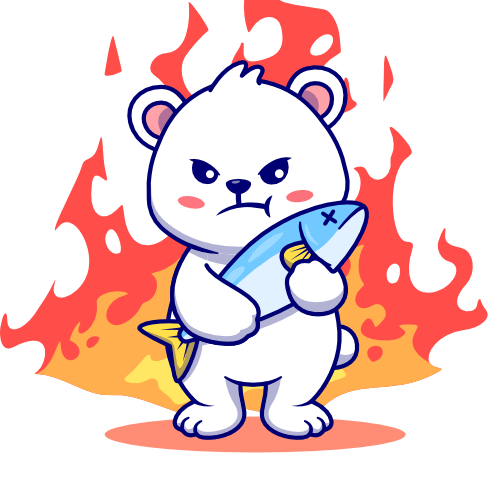
「エネファームで金銭的にメリットを生み出すことは難しい」
これだけ覚えておいてもらえれば、家づくりの際にエネファームを導入するかしないかを考えた際に、大きな失敗はしないはずです。
記事が古くなりましたので、このページでは「エネファームのメリット・デメリット」についてまとめることにしました。
エネファームタイプSの情報が知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

最新のエネファーム情報をまとめたページを別途用意しました。2023年以降に充実させていく予定です。

ただ、2022年ごろから全てのものが値上がりして、電気代の高騰も歯止めがかからない状態です。
ガス発電においても結局のところガス代に依存するため絶対にお得とは言い難いですが、電気だけに依存しないほうが対策の幅は広がるため、太陽光導入に合わせてエネファームのW発電が効果的になってきた時代になってきてしまった、というのは2024/03/22時点での感想です。
2024年の「給湯器全般」新着情報まとめ
エネファームの新着情報は別記事に移行したので、ここでは家づくりで知っておきたい給湯器全般について調べているついでに見つけた「新製品情報」や「発売が噂されるもの」などの情報をざっくりまとめて置いておきます。
給湯器に関する新着ニュース
給湯器に関する新着ニュースをまとめています。
パナソニック空質空調社のエコキュート事業拡大
2023年9月18日の、パナソニック空質空調社のエコキュート事業戦略に関する情報をお届けします。
- エコキュート市場の堅調な成長と未来の展望
- ZEH住宅の普及がエコキュート需要を更に推進
- 経済産業省資源エネルギー庁の補助金制度が日本のエコキュート事業を支援
エコキュート市場の現状と展望
2022年度にはエコキュートの出荷台数が70万台を突破し、累計出荷台数も100万台を更新するペースが加速しています。福永敏克氏(パナソニック 空質空調社 日本・広域事業担当 水ソリューションズビジネスユニット BU長)によれば、2025年度には80万台、2030年度には90万台以上の出荷が見込まれます。オール電化初期ユーザーの買い替え需要とカーボンニュートラルへの世界的な関心が市場成長の背景にあります。
ZEH住宅とエコキュート
ZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅の普及がエコキュートの需要を高める要因となっており、2021年度にはエコキュートのZEH住宅への採用率が約70%に達しました。今後、ZEH住宅の普及促進が進めば、エコキュートの採用量も更に増加すると予想されます。
経済産業省資源エネルギー庁の支援
日本政府は、エコキュートなどの省エネ給湯器の導入を支援するために5万円の補助金を提供する給湯省エネ事業を開始しています。これにより、日本のエコキュート事業は好位置にあると福永氏は指摘しています。
1
- 2025年度のエコキュート生産30万台達成 パナソニック 空質空調社の3つの戦略 (公開日: 2023年09月11日)
パナソニック、エコキュート市場拡大戦略を発表
2023年8月26日に、エコキュート(電気給湯機)に関する新しい事業戦略と新製品についてパナソニックが発表しました。
- カーボンニュートラルの取り組みとZEH住宅、省エネリフォームのトレンドを背景に、エコキュートの市場拡大が続くと予測。
- 新設された水ソリューションズBU(ビジネスユニット)では、エコキュート以外にもホームシャワー、ヒートポンプ式温水給湯暖房機(A2W)なども取り扱う。
- 2022年度には市場が過去最高の70万台まで拡大。2025年度には80万台以上になると見込まれる。
追加製品と市場展開
- 寒冷地向けの新製品も発表。最低気温がマイナス10度を下回る地域でも使用可能。
- 専用アプリを用いて太陽光発電の出力を予測し、自動で沸き上げる「スマートソーラーチャージ」を搭載。
製造・生産能力
- 滋賀県草津市の工場での生産能力を2025年度までに15万台から30万台に倍増する計画。
マーケティング戦略
- ショールーム「e-STATION KUSATSU」をオープンし、エコキュートの商品価値を体感を通じて発信する。
| 年度 | 市場規模(台数) |
|---|---|
| 2022年度 | 70万台 |
| 2025年度予測 | 80万台以上 |
エコキュート、国内出荷が70万台を突破
2023年8月26日の、エコキュート市場に関する情報をお届けします。
- 2022年度の国内年間出荷台数が70万台を突破し、前年度比15.9%増で過去最高を更新
- 買い替え需要とゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の普及が主な成長要因
- 出荷数は当面、増加傾向が続くと見られ、累計出荷台数は23年度上期には900万台を突破すると予想
補足:ZEHとの親和性
- ZEH住宅では約7割がエコキュートを採用
- 政府は2030年度以降に新設される住宅について、ZEH水準の省エネ性を求める方針
補足:補助金とメーカーの取り組み
- 給湯省エネ事業による補助金申請が始まり、一定の省エネ性能を満たしたエコキュートには5万円が補助される
- パナソニックは23年度に年間20万台の販売目標を掲げ、三菱電機は「十分な生産量を確保している」とコメント
| 要素 | 詳細 |
|---|---|
| 出荷台数(2022年度) | 70万台 |
| 増加率(前年度比) | 15.9% |
| 主な成長要因 | 買い替え需要、ZEHの普及 |
| 補助金 | 給湯省エネ事業で5万円 |
| パナソニックの販売目標 | 23年度で年間20万台 |
| 三菱電機のコメント | 「十分な生産量を確保している」 |
このように、エコキュート市場は買い替え需要とZEHの普及、さらには政府の補助金制度などによって、今後も成長が期待されます。特に、ZEHとの親和性や補助金制度は、新規需要を生む重要な要素となっています。
給湯器の新製品情報
給湯器の新製品情報についてまとめています。
新製品:エコキュート
2023年8月26日時点でのパナソニック株式会社空質空調社のヒートポンプ給湯機「エコキュート」について紹介します。
エコキュートの特徴
- 寒冷地向けに特化し、最低気温が-25℃でも約80℃の高温沸き上げが可能
- 「スマートソーラーチャージ」機能で日射量予報から太陽光発電の出力を予測、自動で沸き上げ
- シャワー流量を「高圧タイプ」と比較して約1.4倍にした「ウルトラ高圧」搭載
価格
963,600円~1,375,000円(税込、工事費別)
エコキュートのおすすめポイント
- 産業界初の「スマートソーラーチャージ」で再生可能エネルギーの有効活用が可能
- 2025年度の省エネ基準を達成し、補助金の対象となる省エネ性能をスタンダードクラスでも実現
エコキュートの気になるところ、注意点
- 外気温が-20℃以下の場合は、屋内設置用タイプを使用する必要がある
- 価格が高めで、工事費が別途必要
エコキュートの購入時参考情報
- 発売日:2023年11月1日
- 補助金制度「給湯省エネ事業」の対象となる可能性が高い
直近の給湯器の補助金/セール情報
給湯器の商品で、「これはお得!」と感じたセール情報も残しておきます。購入の決め手となる価格の参考にどうぞ。
給湯省エネ事業で最大30万円の補助、電気・ガス代の節約が可能
2023年8月26日の、給湯省エネ事業に関する情報をお届けします。
- 電気料金が高騰しており、特に給湯が家庭用エネルギー消費の約27.8%を占める
- 給湯省エネ事業は、高効率給湯器を導入する家庭に対し補助金を提供する制度
- 申請手続きは主に工事事業者が代行、消費者は特別な手続きをする必要はない
補足:補助金額と対象給湯器
- 家庭用燃料電池(エネファーム):最大15万円/台
- ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器:最大5万円/台
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート):最大5万円/台
補足:2030年度のエネルギー需給の見通し
- 事業は、2030年度の温室効果ガス排出量を46%削減する目的も含む
補足:申請手続きの流れ
- 事業者と消費者で売買契約を締結
- 事業者が工事に着工
- 工事完了後に、事業者が補助金の交付を申請
- 審査完了後、補助金が消費者に直接交付される
| 補助対象給湯器 | 補助額(最大) | 補助上限 | 性能要件 |
|---|---|---|---|
| 家庭用燃料電池(エネファーム) | 15万円/台 | 戸建て:2台まで | 特定条件 |
| ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器 | 5万円/台 | 戸建て:2台まで | 年間給湯効率108%以上 |
| ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 5万円/台 | 戸建て:2台まで | 2025年度の目標基準値以上 |
このように、給湯省エネ事業は、エネルギー消費の大きな部分を占める給湯分野での省エネを目指しています。特に、電気・ガス代が高い家庭は、この補助金制度を活用して高効率の給湯器を導入することで、出費を削減できる可能性があります。
エネファームは太陽光よりメリット少ない
と、我が家を建ててくれた営業担当が言ってました。

私の知り合いも、「太陽光とかエネファームとかって、お得なのかどうかわかんないよね」って悩んでましたね。
確かに疑問が多いこのあたりの問題を少しばかり深く掘り下げていこうと思います。
太陽光はほとんどの住宅会社が積極的に取り組んでいる
太陽光発電はハウスメーカーによっては力を入れているところもあり、ハウスメーカー選定にも大きく関わってきます。

でも、一方のエネファームって、あんまり住宅会社がお勧めしている印象はないよね。
エネファームをつけるかどうかでハウスメーカーを決める方はほとんどいないかと思いますが、つけるつもりであれば、どこにつけるのかなど間取りも考慮せねばなりませぬので、はやい段階でつけるかどうかは考えなければいけません。
太陽光発電をお勧めする理由
太陽光発電の方が住宅会社としてもメリットが大きかったりします。
エネファームは、ガス併用住宅にしか対応できませんからね。太陽光発電の方が扱いやすいというのが実情です。

ちなみに、ZEHについても、エネファーム単体でZEH基準を満たすのは至難の技となるのに対して、今でも創エネの基本は「太陽光」です。
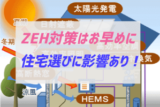
では、エネファームってどうなのでしょうか
エネファーム導入前に知っておきたいこと
エネファーム導入前に必ず知っておきたいことは、「お湯と発電の関係」です。
自分の家がどれくらい給湯を必要とするかで、エネファームが必要かどうか判断できます。
給湯の時しか発電しない
エネファームは、給湯の際に発電します。いや、発電の際の熱を利用して給湯している、というのが正しいのか。
エネファームが発電する方法
難しい説明は抜きにして、簡単に説明します。
- ガスの中には水素があります。
- これを利用して電気を作ります。
- 電気をつくるときの熱を利用してお湯を沸かします。
- 電気をつくって、お湯を沸かすことができました!
ちなみに、その分、ガスも使用されています。
たくさんお湯を使うならギリギリ得する場合も
つまり、電気をつくろうとすると熱も発生するからどうせだからお湯沸かしちゃおうぜ、っていうのがエネファームなのです。

なので、電気をつくろうとすればするほど、お湯が沸きます。無駄なお湯を沸かす必要はないので、十分なお湯があれば電気はつくられません。
給湯をあまり必要としないような人数の少ないご家庭には不向きです。
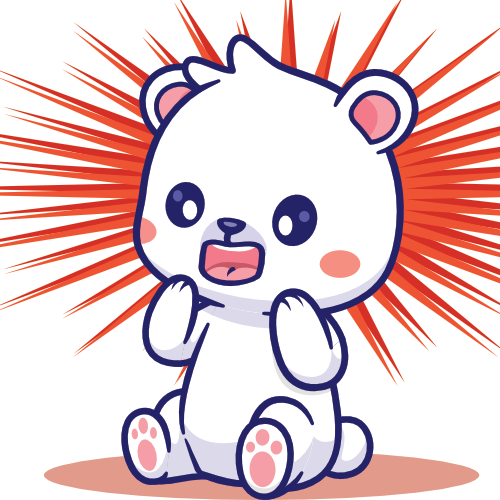
むしろ、エネファームを利用しようとすることで、エネルギー効率が悪くなった、なんて計算も出ているみたいです。
みんながみんな得をするわけではないので、利用者を選ぶ、とも言えますね。設置者を選ぶ高飛車なエネファームさまさま。
エネファームを4人家族で利用した場合の料金シミュレーション
ちなみに、試算になりますが。一般的な4人家族のご家庭では、ガス代がプラス6000円程度、一方、電気代はマイナス70,000円に。
また、こちらのエネファーム使用時のシミュレーションがわかりやすいですね。
ということらしいですが、ソースはどちらもガス会社発表のもの。実際のところはどうなのでしょうか。
一般的な家庭って何よ?
まず、比較対象となっている一般的なご家庭は少し電気代などが割高な気がします。

大体、最近の家電は省エネ製品を取り入れてますし、エコジョーズなど給湯時より高効率な給湯機も出ています。
そのあたりと比較した場合の利率はどうなるのでしょうか。
エネファームと他のエネルギー系商品を比較する
エネファームの検討を始める場合、「エネファームだけ」にするかW発電と称してハイブリッドに太陽光発電などを組み合わせるのか、という点についても考える必要があります。
他の再生可能エネルギーとの相性は
京都議定書の目標となっていた2020年が終わり、2021年からは2030年のパリ協定で掲げられた「脱炭素社会」に向かって本格的に動き出すことになります。新しいエネルギーについては別記事でも紹介しています。

また、家づくりに関してのエネルギーの考え方についてもまとめてみました。

再生可能エネルギーという言葉の認知度は高まりましたが、「実際、何なの?」と聞かれて答えられる人は少ない。最低限、家づくりに関するエネルギーの話だけは知っておくと「未来で損することはない」ということで、簡単に情報をまとめておきました。
家庭用燃料電池
家庭用燃料電池としてエネファームの利用が進んでいますが、水素を使った家庭での発電には注目したいところです。
エネファームも「燃料電池」です。燃料電池の今後の展望や水素エネルギーについてもまとめた記事があるので、退屈で死にそうな時に追い討ちをかけるつもりでどうぞ。

地熱発電
地熱発電に関する情報はこちらにまとめました。エネファームとはあまり関係ありませんが、地熱発電は自治体で取り組み、電気を住民でシェアできる、かつ観光資源として活用する、なんて未来がありそうな感じがします。
エネファームに関しては、コジェネを地域で共有するという街づくりが可能ですけど、それはまた別のお話。

地中熱利用
地中熱と地熱がややこしいですが、地面の中は温度変化が少なく、地上との温度差を利用して冷暖房や給湯などの省エネに貢献することができます。
地中熱を家づくりに役立てる情報についてはこちらにまとめてあります。

小型風力発電
自宅に風力発電は実現可能性は低いですが、我々新潟県民は「冬場の日射量は期待できない」ため、太陽光発電と太陽熱利用が難しい地域と言えます。少しでも発電の助けにならないかと、風力発電についても調べてみました。
W発電の相方として考えられそうな感じもしますが、風力発電システムの家庭配置は敷居が高そう。

太陽光発電
太陽光は年中安定して利用できるエネルギーではなく地域格差が生じるので「冬も晴れ間が広まる地域が羨ましい」と指を加えてみているだけですが、そんな太陽光発電に関する情報も別記事にあります。

太陽熱利用
太陽光を期待できる地域の場合、太陽光発電だけではなく、太陽熱を利用することも可能です。太陽熱利用は昔から存在する技術ですが、太陽光発電との相性も考えてハイブリッドに活用する方法についても開発が進められています。

エネファーム類似商品を区別する
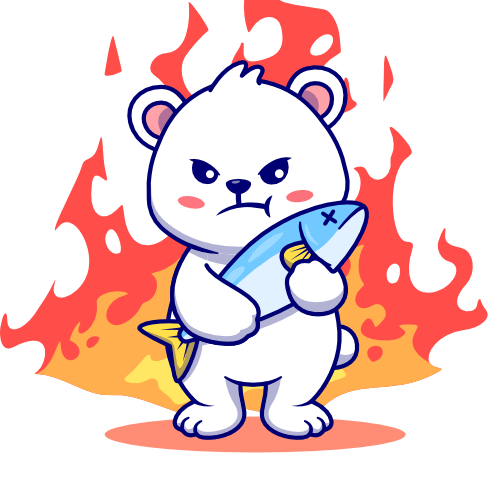
どうでもいい話ですが、エネファームとエコジョーズって似てるじゃないですか。

さらにエコキュートも入ってくるとややこしいですよね。
エコジョーズはガスの給湯
エコジョーズはガスの給湯システムになります。
お湯を沸かすときの熱を無駄にしないようにすることで省エネしよう、というものになります。
エコキュートは電気の給湯
エコキュートは、エコな給湯システムでエコキュート。
大気の熱をうまく利用することで、熱を効率よく移動させたり、圧縮して高熱にしたりして省エネするものです。
エネファームはガスによる発電
エネファームはガスによる発電機だと考えてもらっていいと思います。
つまり、エネファームとエコジョーズは畑が違うわけです。

これ知ってると打ち合わせの時に話が早いですよ。
エネファーム購入の分岐点となる情報
知りたいことは「家づくりやリフォームで、結局、エネファームは便利なのか、損はしないのか」ということだと思います。つまり、メリットやデメリットの話をしていきます。
エネファームで得する方法
とはいえ、エネファームで得する方法は必ずあるはずです。そのためにチェックすべきことなどまとめました。
購入費用を安くする
エネファームでもとはとれるのでしょうか。

20年後というのはちょうどエネファーム本体の寿命ですね。
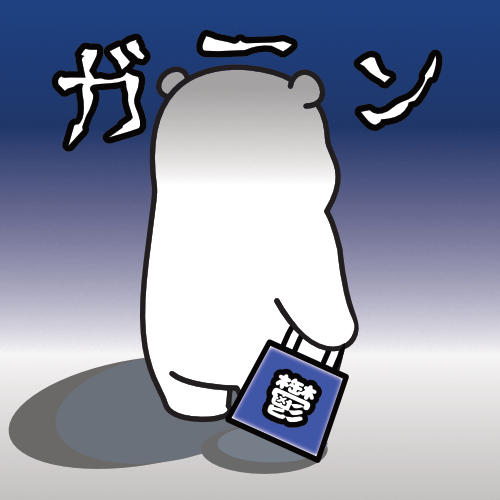
保証の効く10年間で償却するには、本体導入費を60万円に設定しないといけないね。
給湯器を購入する必要はなくなる
エネファームを検討されている方は、おそらく「給湯器の買い替え」か「新築」、あるいは戸建てを選ぶ際の参考などとして考えられているかと思います。

読者さまより、「給湯器の買い替えが不要になるよ!」という情報提供をいただきました!
新規にエネファームを購入する場合、ガス給湯器は不要となります。最近は後付エネファームSで、今ある給湯器とつなげて使用するタイプもあります。選択肢は様々ですので、一度、ガス会社などに問い合わせてみると、どれくらいの価格差になるのかはっきりしそうです。
維持費を検討する
通りがかりのブログなんかを見ると、「電気代は安くなった」と聞きますが、修理関連の話題はあまり聞きません。
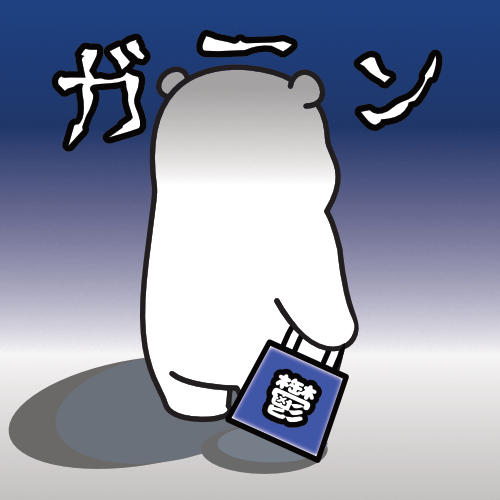
ただ、設置上問題があったのか、漏水や電気代が高くなった、なんてコメントも散見されましたね。
先述の通り、エネファームは20年もてば御の字という製品です。故障がなくても、電池の方が持たないはずです。また、電気効率は年々低下することが予測されるため、ベストパフォーマンスを維持するのは難しいでしょう。
補助金を利用する
2020年の以降の最新のエネファーム製品については、また別記事になりますが、製品自体の値段が下がってきてくれており、自治体によっては補助金上乗せもあるので自分の住んでいるところの情報は嗅ぎ回った方がいいです。

エネファームのデメリット
エネファームのデメリットをまとめてみました。
騒音問題
低周波騒音の原因になる可能性があり、近隣への配慮が不可欠とのことです。

設置場所は、平らで安定した土地であることにくわえて、近隣住宅との距離や振動の伝わり方など配慮しないと、思わぬトラブルに発展する可能性もありますね。
イニシャルコスト高し
導入に100万円以上かかります。
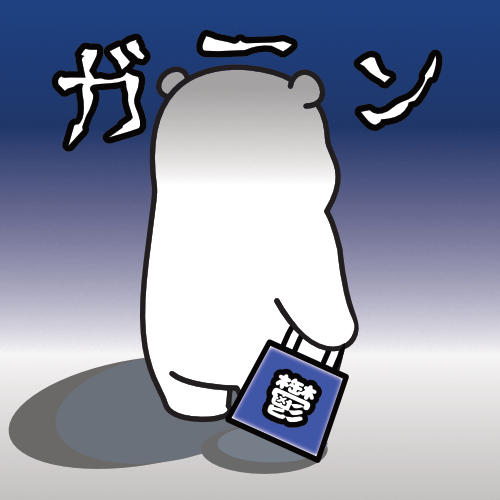
加えて、オーバーホール(修理)なんぞしたら結構な修理代がかかるそうです。

仮に導入費を少し抑えられたとして、自分の持ち物になったら自分で修理せねばなりませんから。
メンテナンスコストも高い
こちらのブログなんかは参考になりそうです。
記事内では漏水メンテナンスを行ったとのことなので、エネファーム本体の問題ではないようですが。
10年間は修理無料、なんて情報もあります。エネファーム自体の寿命は20年程度みたいです。(8年とするところもあるようですが)

うちの営業さんは、60万円くらいまで安くなってようやく検討できるもの、といっていました。ガス会社と懇意なHMでは説明も変わってくるのでしょうが。
新築時に安くなるという甘い話
ちなみに、冒頭部の知り合いの方は、HMから40万程度で導入できると勧められているそうです。
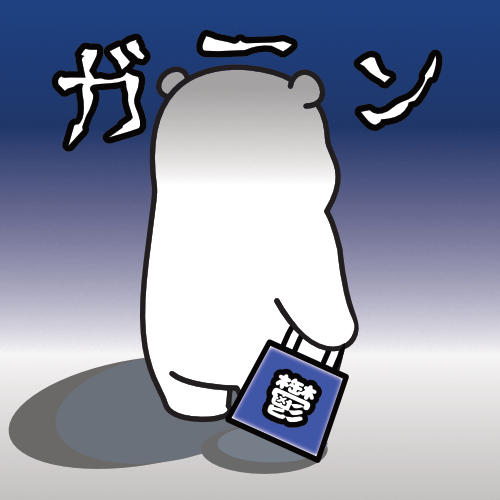
たぶん、40万で設置したらどこかで割の合わない話になっているはずですが、どこが負担しているにせよ、最終的に帳尻を合わせられてしわ寄せは消費者に来るようになっているはずです。

本来値引きされるべき金額がそちらに充当されているかもしれないですしね。
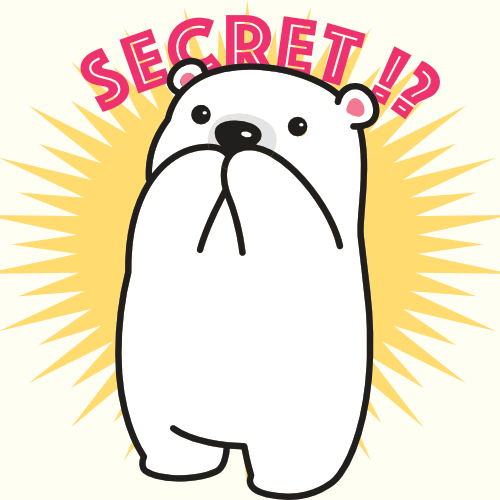
「そこ安くするなら、別のところを安くしてくれよ」と言いたくなるところですが、まぁ聞いてはもらえないよね。
知り合いの方は話を聞いているところ、予算はあるみたいなのでたぶんどこかの大手の話なんだけど、大手はW発電なる、太陽光とエネファームの発電で売電するのがいいみたいな話をするみたいです。

というか、もはや使えるお金は根こそぎ使わせようとしているようにしか見えないのだが。
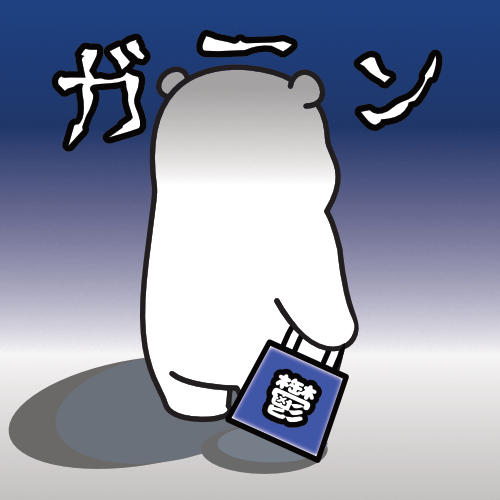
ちなみに、エネファームは売電に使えないらしく、さらにW発電では売電価格も下がってしまうのだとか。
もちろん、エネファームでつくられた電気を自宅用に使うことで、太陽光の売電量を増やすことができる、という理論な訳なのです。
導入費用は減少傾向
流石に底値にどこかで行き着くかとは思いますが、東京ガスのエネファームの初期費用は、2011年に267万円、2013年に190万円、2015年に167万円と年々減少傾向にあるとのこと。
こちらのサイトは参考になります。
https://tokyo-chumon.com/save_energy_housing/zeh/6054
2021年は100万円から
2021年のエネファームは、燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業費補助金がなくなったことが大きく影響しそうです。
新築・リフォームのタイミングと合えばZEH関連から補助金を引っ張ってくることもできそうですが、エネファーム単体での設置は少し向かい風の傾向かもしれません。
2021年のエネファーム価格目安値
| パナソニック | 90万円〜110万円程度 |
|---|---|
| 京セラ | 100万円〜130万円程度 |
| アイシン精機 | 190万円〜240万円程度 |
補助金がなくなった分の値下げがあるかもしれませんが、元々が高い製品なので、高止まりするような気がします。
本体価格なので、別途工事費(30万円〜80万円程度)が必要になると考えてください。
【2021年度 エネファーム導入補助金に係る全国自治体調査】
2020年は200万円
今、私がざっくり調べたところだと、だいたい200万円くらいでエネファームが設置できます。ただ、ここから工事費が入ったり、補助金が出たりと前後する幅は大きいようです。
結局どうしたらいいかといえばエネファームはスルーが堅実
悲観的なポイントが多くなってしまいましたが、これから先のことを考えると、自分たちで発電する方法があることはいいことです。
売電収入は以前ほど期待できなくなったけれども、電気代が何かの拍子に高騰する可能性はあるので、(同時に、ガスが高騰する可能性も十分にあるのだが)電気を自炊できるポテンシャルを有することは心強いことです。
エネファームを推奨できるタイミング
ぶちくま家では、暖房にガスによる温水ルームヒーターを導入しているので、ガスに対する依存度は高いです。
正直、エネファーム導入も本気で考えましたが、まだ時期尚早かなという印象を受けました。
ガス会社としては、住宅の暖房機能に対しても発電量向上するように改良してもらえれば、「ガス暖房+省エネ給湯+自家発電」で、トータルメリットが大きくなると思うのですが。
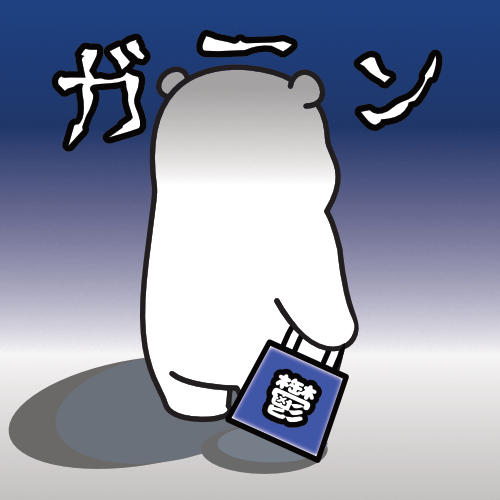
でも、イニシャルコストがこれ以上増えるのは歓迎できないね
企業努力により、だいぶ本体価格が下がっているようですが、率直な感想としては、「ローンを組んでまで取り入れる設備ではない」というところです。
導入するに値する条件
の条件がそろったときに、エネファーム導入はようやく検討の土台に上がれそうです。
10数年後に、エコジョーズが壊れた時に、エネファームが安くなったり、エネファームに代わるものが現れていることを期待しています。
ZEHとの相性は
ZEHで大事なことは、エネルギー消費を抑えるよりも、どのようにエネルギーをつくるか、と言うところにあると思います。
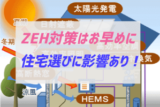
エネファームでは、家の電気の半分に満たない程度の発電力なので、これ一つではZEHは成り立ちません。
売電もできないので、あくまでも太陽光発電などの補助的な使い方となりそうです。



![NORITZ GT-C246AWX BL-13A エコジョーズ [ガスふろ給湯器 (都市ガス用 屋外壁掛型 前面排 スタンダード フルオート 24号)]](https://m.media-amazon.com/images/I/21vGBvI3SgL._SL160_.jpg)








コメント
「住宅 住宅 着工 前年」に関する最新情報です。
2025年2月の新設住宅着工戸数に関する国土交通省の発表によると、全体では前年同月比2.4%増の60,583戸となりました。特に貸家が増加した一方で、持ち家と分譲戸建ては減少しました。また、季節調整済みの年率換算値は前月比4.1%増の805,000戸となっています。
https://www.housenews.jp/research/30831
「建材 1日 1日 出荷」に関する最新情報です。
アイカ工業は、2023年3月25日に発表し、住器建材の設計価格を7月1日出荷分から約10%値上げすることを決定しました。
https://www.s-housing.jp/archives/380967
「2025 2025 2030 2030」に関する最新情報です。
A.T.カーニーのマクロ経済部門シンクタンク、グローバル・ビジネス・ポリシー・カウンシル(GBPC)が発表した「2025~2030年の予測~流動する世界」レポートは、今後5年間の世界的な見通しを示し、ビジネス環境に影響を与える5つの「ワイルドカード」に焦点を当てています。これらのワイルドカードは、経済成長を遂げる中堅国やアフリカ諸国の影響力の増大、米中間の緊張など、国際ビジネス環境における不確実性を反映しています。レポートは、企業や政治家がこれらの変化に対応し、リスクを軽減するための戦略を模索する必要性を強調しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000069.000046861.html
「価格 住宅 価格 高騰」に関する最新情報です。
東京都は、中間層向けの「アフォーダブル住宅」を普及させるためのファンド創設を進めており、2025年度の予算案に関連経費を盛り込むことを目指しています。最近の調査によると、東京23区の新築マンションの平均価格が1億円を超えるなど、都心部の住宅価格が急騰しています。この新ファンドは、民間事業者がアフォーダブル住宅を整備する際に必要な資金を提供する役割を果たします。具体的な規模や開始時期、制度の詳細は今後決定される予定で、都の出資に加え、企業の社会的責任を重視する企業からの協力も促進し、民間資金の活用を図る考えです。
https://www.s-housing.jp/archives/371903
「12 ファーム 戦略」に関する最新情報です。
2024年12月17日(火) 20:00より、ヤマトヒューマンキャピタルが主催するウェビナー「戦略ファームのポストキャリア論決定版」がオンラインで開催されます。このセミナーでは、外資系戦略ファームBain&Company出身の起業家河野博氏と、マラトンキャピタルパートナーズの和田耕太郎氏が登壇し、コンサルタントのキャリアパスにおける「PEファンド」「スタートアップ」「大手事業会社経営企画」「独立・起業」の各選択肢のメリット・デメリットを詳しく解説します。河野氏は自身の経験を基にキャリアの満足点や後悔点についても語り、和田氏はPEファンドの魅力や実態について掘り下げます。参加は無料で、コンサル出身者にとって貴重な情報が得られる機会です。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000137297.html
「ビジネス 新潟 戦略」に関する最新情報です。
濱畠太は新潟ビジネスのトレンドや戦略、地域課題、未来について発信するビジネス書作家であり、マーケティングやブランド戦略の専門家です。彼は新潟の企業を訪問し、地方発のイノベーションを探求する活動を行っています。これまでに多くの著書を出版しており、企業の広報やプロモーションの責任者としても経験を積んできました。彼の活動は、新潟地域の中小企業や自治体への経営コンサルティングにも及んでいます。
https://www.niikei.jp/1308840/
「北海道千歳市 逼迫 需給」に関する最新情報です。
北海道千歳市で、次世代半導体の量産化を目指すラピダスの工場建設が進む中、賃貸物件の需給が逼迫しています。ファミリー向けの平均賃料は、工場建設が始まった約1年前に比べて2.2倍に上昇し、現在は10万5409円に達しています。ラピダスの進出発表以降、工場関係者や関連企業の需要が増加し、シングル向けやファミリー向けの入居者募集件数が大幅に減少しています。新築物件も登場していますが、需要には追いついていない状況です。
https://www.s-housing.jp/archives/369988
「イチジク 出荷 生産者」に関する最新情報です。
新潟県産のブランドイチジク「越の雫」の出荷が最盛期を迎え、生産者と生産量が年々増加しています。2024年の計画出荷量は約220トンで、前年比10%増が見込まれています。生産者の鈴木哲也さんによると、今年の天候に恵まれたことから、イチジクの出来は良好で、特にこの時期は身が大きく瑞々しいとのことです。「越の雫」は新潟市や燕市で栽培されており、選果場で検査に合格したものだけがブランド名が付けられます。出荷は11月中旬まで続き、特に8月から9月初めのものが最も美味しいとされています。また、JA新潟かがやきでは新規栽培者を増やすために「いちじく塾」を開催し、栽培方法についての講座を実施しています。
https://www.niikei.jp/1180512/
「予測 着工 前年度」に関する最新情報です。
建設経済研究所の予測によると、2024年度の新設住宅着工戸数は79.6万戸で、前年度比0.6%の減少が見込まれています。これは持家や分譲戸建の減少と分譲マンションの増加が影響しています。また、民間住宅投資額は16兆6300億円で、こちらも前年度比1.5%の減少が予測されています。
2025年度については、建設コストの上昇が住宅需要を抑制し、着工戸数は79.8万戸(0.3%増)と微増にとどまる見込みです。民間住宅投資額は16兆8900億円で、1.6%の増加が予測されていますが、持家着工戸数は20.8万戸(0.7%減)と減少する見込みです。一方、貸家着工戸数は34.4万戸(0.7%増)、分譲住宅着工戸数は24.0万戸(0.5%増)と予測されています。
https://www.s-housing.jp/archives/361584
「着工 年度 見通し」に関する最新情報です。
2025年度の住宅着工戸数は前年比0.5%減の78万4千戸と予想されており、景気の回復が緩やかであることや海外の景気低迷、賃金引き上げによる住宅価格や資材価格の上昇がマイナス要因として挙げられています。一方、実質賃金の上昇や金利の緩やかな上昇により、住宅ローン市場は安定しているとの見通しもあります。
https://www.housenews.jp/research/27145
「26 26 年度 三菱電機」に関する最新情報です。
三菱電機は、伊丹製作所で次世代蓄電池の開発を進めており、電車がブレーキをかけた際に発生する電気をためて同じ車両の動力に使用することで、走行電力の3割削減を目指している。2026年度の商用化を目指しており、発生した電気を無駄なく活用することで効率的な電力利用が期待されている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3LmtvYmUtbnAuY28uanAvbmV3cy9lY29ub215LzIwMjQwNi8wMDE3ODEwMDc3LnNodG1s0gEA?oc=5
「エアコン 工場 エアコン 出荷」に関する最新情報です。
三菱電機は、2024年の夏に猛暑が予想される中、エアコンの需要が高まっており、工場はフル稼働状態でエアコンの出荷が増加している。電気代の高騰を背景に、省エネ性能の優れた新機種への買い換え需要も見込まれている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vd3d3LmZubi5qcC9hcnRpY2xlcy8tLzcxNjY4M9IBAA?oc=5
「増加 前年 前年 増加」に関する最新情報です。
TDBの調査によると、2024年夏のボーナスは前年比で増加し、増加する企業は39.5%であった。大企業では増加率が高く、中小企業や小規模企業は増加率が低かった。従業員1人当たりの平均支給額も2.0%増加し、大企業と中小企業の間で規模間格差が広がっていることが報告された。
https://www.s-housing.jp/archives/353897
「戸建 国内 最高」に関する最新情報です。
積水ハウスは2025年1月期第1四半期の決算で、過去最高の売上高を記録しました。国内の物件売却と米国の戸建住宅事業が収益に貢献し、特にZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やスマートホームサービスの提案により受注が好調でした。また、賃貸・事業用建物事業も増収増益となり、特にZEHを中心に受注が好調であることが報告されました。
https://www.s-housing.jp/archives/353281
「試乗 enne 出荷」に関する最新情報です。
2024年6月7日に開催されるENNE T350Proの試乗会のお知らせ。ENNE T350Proは発電機能を搭載した特定原付で、即日出荷可能な状態となっている。ENNE T250の成功を受けて、ENNE T350 Proでは発電量を8倍に向上させ、モーターも250Wから350Wにパワーアップ。この機種はペダルをこぐことでバッテリー消費を減らすことができ、バッテリー切れのリスクを軽減する。前回のT250は500台が10分で売り切れた人気商品だった。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000078121.html
「マーケティング 観光 地域」に関する最新情報です。
JTBと電通デジタルが協力し、持続可能な観光地域づくりのマーケティング支援を行うことを発表。全国各地域の自治体や観光関連事業者に対し、地域に合わせた戦略の立案と実行を行い、持続可能な地域づくりを支援する取り組みが行われる。JTBの観光開発プロデューサーが現場で支援し、診断結果を活用して地域に最適なプロセスやゴールを設計する。
https://marketing.itmedia.co.jp/mm/articles/2405/31/news116.html
「電気料金 水準 最高」に関する最新情報です。
東京電力の電気料金が過去最高水準に上昇し、エアコンの賢い使い方が注目されています。政府の補助金終了や燃料価格の高騰により、7月の電気料金は前月より約400円上昇し、9126円に近づく見通しです。節電方法として、エアコンフィルターの掃除や風向き・風量の工夫が紹介されています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiNGh0dHBzOi8vd3d3Lm5oay5vci5qcC9zaHV0b2tlbi9uZXdzdXAvMjAyNDA1MjNkLmh0bWzSAQA?oc=5
「工場 精機 精機 工場」に関する最新情報です。
樫山工業が長野県佐久市の精機第一工場に太陽光発電設備を設置し、2024年5月中旬から稼働を開始する。設備には780枚の太陽光パネルがあり、年間470MWhの発電見込み量であり、CO₂排出量の削減に貢献する。これにより樫山工業のエネルギー自給率が9.4%に向上し、電力需給の軽減につながる。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000139578.html
「空調 ai 予測」に関する最新情報です。
NTT ComとNTTデータが提供する屋内環境予測AIを活用した空調最適制御サービスが、NTT都市開発の5つの大規模オフィスビルで導入されることが発表された。このサービスでは、天候や室内温湿度、人流などのデータを活用し、AIが室温の変化やビル滞在者の快適性を予測して空調制御を行うことで、快適性と省エネルギー化を両立させる。空調設備を更新する必要がなく、クラウド上での分析と制御指示を行う仕組みを導入することで実現可能とされている。
https://www.s-housing.jp/archives/349301
「住宅 住宅 着工 新設」に関する最新情報です。
2024年2月の新設住宅着工戸数は、前年同月比8.2%減の5万9162戸だった。貸家は増加したが、持ち家と分譲住宅はいずれも2ケタ減となった。持ち家の減少は27ヵ月連続で低迷が続いており、首都圏や中部圏、近畿圏など各地域でも減少が見られた。
https://www.housenews.jp/research/26671
「新潟 29 予報」に関する最新情報です。
3月29日の新潟県内は昼ごろまで雨が予想され、黄砂の飛来も予報されています。気圧の谷や湿った空気の影響を受けるが、午後からは高気圧に覆われる見込みで、雨のち晴れとなる見込みです。また、明け方から昼前に雷を伴う所があるとのこと。下越地域では降水確率が高く、朝の最低気温は9度、日中の最高気温は16度との予報です。
https://www.niikei.jp/1004775/
「ショールーム 企業 太陽光」に関する最新情報です。
高知市の企業である荒川電工が、太陽光発電や蓄電池などの再生可能エネルギー設備を展示するショールームを改装し、防災面で需要が高まる取り組みを強化していることが紹介されています。改装されたショールームは広くなり、展示するメーカーの数も増えており、太陽光発電の重要性が強調されています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnN1bnN1bnR2LmNvLmpwL25ld3MvMjAyNC8wMy8yNzQ2MDU20gEA?oc=5
「エコキュート 太陽光発電 給湯機」に関する最新情報です。
大阪市では、太陽光発電の余剰電力を利用して、昼間に給湯機「おひさまエコキュート」とマルチカセット型エアコン「ココタス」を販売しています。これにより、エネルギー効率を高めることができます。
https://www.s-housing.jp/archives/337480
「kw 給湯 kw クラス」に関する最新情報です。
三菱重工サーマルシステムズは、欧州向けに新しいヒートポンプ式給湯暖房機のシリーズ「Hydrolution EZY」を追加することを発表しました。このシリーズには、10kWクラスと14kWクラスのモノブロックタイプが含まれており、今冬から販売が開始されます。これらの製品は、脱炭素社会に貢献するために設計されており、地球温暖化係数が小さいR32冷媒を使用しています。さらに、静音性が向上し、広い温度範囲での運転が可能です。これにより、寒冷地でのボイラーの代替として使用することができます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000546.000025611.html
「マンガ マーケティング マンガ マーケティング」に関する最新情報です。
株式会社コムニコは、マンガマーケティングを提供している株式会社シンフィールドとの事業提携を発表しました。この提携により、SNSとマンガを組み合わせたマーケティング支援を開始することが明らかになりました。具体的には、SNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」に「Xクチコミ推移機能」を追加し、バズや炎上の早期発見をサポートします。また、株式会社シンフィールドはマンガマーケティングの専門企業であり、マンガの特長を活かした集客支援を提供しています。この提携により、SNSとマンガのコンテンツを活用したマーケティングがさらに強化されることが期待されます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000129.000028382.html
「マイナス 価格 調査」に関する最新情報です。
2023年1月の全宅連の調査によると、土地価格のDI値がマイナスになったことが明らかになりました。これは、2021年1月の調査依頼以来初めてのことです。新型コロナウイルス感染症の拡大初期から続いていたマイナスの実感が、価格上昇に変化してきたことを示しています。全国の土地価格の動向に注目が集まっています。
https://www.housenews.jp/research/25451
「住宅 住宅 着工 新設」に関する最新情報です。
2023年8月の新設住宅の着工件数は、前年同月比9.4%減の7万399戸となり、持ち家の減少が21ヵ月連続で続いています。この数字は季節調整後の年率換算で、前月比では4.5%増の81万2千戸となっています。
https://www.housenews.jp/research/25255
「エコキュート パナソニック パナソニック 空調」に関する最新情報です。
パナソニックの空質空調社は、2025年度までにエコキュートの生産を30万台に拡大する戦略を立てています。エコキュートは再生可能エネルギーを活用した給湯機であり、地球環境への関心の高まりを背景に需要が拡大しています。2022年度には70万台の生産を達成し、需要の拡大が続いています。パナソニックは展示会やイベントを通じてエコキュート事業の価値を訴求し、今後も戦略的な取り組みを強化していく予定です。また、2023年には新たな拠点となるe-STATION KUSATSUをオープンし、エコキュート事業の説明会も開催されました。福永氏によれば、2025年度には80万台、2030年度には90万台の生産を見込んでおり、エコキュート事業の将来展望も明るいとされています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vYnVpbHQuaXRtZWRpYS5jby5qcC9idC9hcnRpY2xlcy8yMzA5LzExL25ld3MxMDAuaHRtbNIBAA?oc=5
エネファーム使って10年になります。
10年までは、毎年の点検代は、無料ですが、10年以降は、年数万円の点検代が毎年かかりそうです。
なので、10年になった時に、買い替えを勧められていますが、やめて通常の給湯器にするか、話しあっています。
今後の事を考えた場合、私としては、エネファームにしたくありません。
ぽよさま、コメントありがとうございます。
10年以降の点検代は必要経費ではありますが少しコスパが悪いと思ってしまいますね。ガスを利用したエネルギー効率を向上させる手段としてはエネファームは優秀ではあるのですが、実用のことを考えるとメリットが乏しいなと思ってしまいます。
実際に利用している方の声は大変貴重です。他の方の参考にもなると思いますので、貴重なご意見ありがとうございました。
初めまして
今のエネファームはお湯の使用量とか関係なく常時発電ですね。常時700Wの発電です。厳密にはガス漏れ誤検知防止のため、1カ月連続運転になる前に24時間停止するみたいですが。ほぼ常時ですね。
私は自分の料理のスタイルからオール電化はありえないし、冬のガスファンヒーターは幸せそのものなので、ガスありきの前提でしか考えてないので偏りはあると思いますが、メリット大きいです。
てことで、今の家を買って10年近いですが、後付けで発注しました。
大阪ガスの場合、エネファームの導入でそもそものガスの単価が3割安くなるプランが選択できますので、普通のガスの使用についてもメリットありです。
あと、自治体にも依るみたいですが、国の補助金だけでなく地方自治体の補助金も受けられます。
私の住む市では5万円もらえます。
別に私は利害関係者じゃないので構わないのですが、せめていつ時点の情報かを明記しておいてはとうか?と感じました。
コメントのせいだと思いますが、更新日が最近になってるので誤解を与えやすいと思います。
げんき。さま。コメントありがとうございます。
まず、情報の更新日時の記載についてのご意見、ありがとうございます。情報を仕入れた時の日付など、なるべくは入れるようにしているのですが、まだまだわかりづらいですね。
また、「エネファーム、使ってみていいですよ」という情報も他の訪問者さまの知りたい情報だと思いますので、コメントしていただけて参考になる方も多いと思います。
補助金に関しては、他の記事で書いてはみたものの、各自治体の利用条件や実施日などの更新を間違えると却って読者が混乱すると思い、初期に書いたこの記事には載せていません。もう少し深い情報が知りたくなったときに、知りたい情報を検索する方が誤解がないかと思いました。
私も温水ルームヒーターがガス由来の熱源で、快適に過ごしており、基本的には「ガス依存」の人間です。それ故に、もう少しお金が貯まったら、蓄電池価格が安くなったら、など考えてエネファーム情報を追っています。
至らぬところも多かったと思いますが、お読みいただきありがとうございました。
エネファームのコストの中に、給湯器として使える分が計算に入っていないと思います。
エネファーム無しでガス給湯を使う場合、給湯器を購入することになります。10年間保証付きの給湯器の購入価格をイニシャルコストから引くべきでしょう。
三浦様、コメントとご指摘ありがとうございます。
エネファームの機能として給湯器を賄っているから相殺できるということですね。初期費用の考え方に補足として追記させていただきます。
ガス給湯を選ぶか、あるいはオール電化なのかは読者さまの環境によるところがあるので、様々なパターンを検討することになると思います。
読者様が家づくりに失敗する可能性が減るよう、なるべく、考え方に多様性をつけられるように調べていきたいと思います。