私は家づくり情報を集めるのが趣味なのですが、何より「スタッフブログ」というものをこよなく愛しております。

広告用の作られた文章よりも、スタッフブログの方がよっぽど信頼性の高い情報が得られるよね。
というわけで、4年間、スタッフブログを読み漁ってきてブログ運営を手がける私がお勧めする、「スタッフブログの読み方」についてお伝えしようと思います。
スタッフブログの読み方
まずは、これから家づくりをする方は、スタッフブログのどこを読んだら「良い住宅会社」なのかわかる部分・ポイントをお伝えしていきます。
良いスタッフブログを見分けるポイント
- 更新頻度
- 画像の豊富さ・質
- 自社SNSとの連携
- 戦略的な更新となっているか
大雑把に言えば、こんな感じです。順を追って説明していきます。
更新頻度で本気度を図る
まず、シンプルでかつ分かりやすいポイントが、「ちゃんと更新されているか」ということです。更新されていない理由は、だいたい以下のような状況に置かれている会社が多いです。
- 更新できないほど忙しすぎる→人手が足りていない
- スタッフブログの集客効果を甘くみている→マーケティングが弱い
- スタッフがブログのネタに困る→家づくりの知識が不足
- ブログ以外で更新している→SNS連携不足
ブログ更新できない会社は注意
忙しいことはいいことでもあるのですが、キャパオーバーである会社は、施行ミスやコミュニケーションエラーが多くなるので注意しましょう。
Web集客できない会社も注意
Web集客は難しく考えると大変そうですが、このブログを見てもらえればわかる通り、特に何の変哲のない人が、特に何も考えずに更新していてもそれなりに人は集まってきます。

やることやってればちゃんと利益に繋がるし、テレビ広告よりイニシャルコストも維持費もかからない。それなのに、Webマーケティングを考えない会社は、将来性が薄いと私は考えています。
ちゃんと勉強して、ちゃんと取り組めばもっと成果が出るのにやらない、スタッフブログという枠組みを作るだけで満足して放置する会社は危険だと思った方がいいと思います。
スタッフの家づくりの知識をみる
スタッフブログでは、書いている情報も大事です。
家が好きな人はブログ記事に滲み出てくる
本当に好きで家づくりをしている人は、かなり勉強している方なので、ブログで書くことも家づくりのことが中心となります。説明の上手い下手はありますが、知識があれば話題を掘り下げますし、知識がない人が書けば上っ面の情報の羅列になります。

例えば、オープンハウスイベントを列記しているだけ、みたいなね。
家づくりを安心して任せられるスタッフを探す
家づくりに関しては、無知が一番の命取り。これは、顧客側もそうですが、対応するスタッフの質も大きく関わります。まずは、しっかりとスタッフブログから「家づくりができるか」値踏みするべきです。
「読まれる記事」を書いている
ものすごく当たり前ですが、ブログは「読まれる」ことで初めて価値が出てきます。ですが、業務として淡々とこなしているだけのブログ更新は、ページが開かれても読まれることはありません。
「読まれること」を意識しているか
これは、ブログに対する意識の問題。
「まーどうせ誰も読まないよね」というブログは、更新頻度が少ない上に、何が言いたいのかわからない。書いている目的もわからない。書いている本人もわかってないのかもしれない。
しっかり仕事として取りくめば、そこに真剣味が帯びるはず。家づくりだって同じように、手抜きはしないのが鉄則。一緒に家づくりをする際に、手抜きをする人は必ずミスを犯します。
誤字脱字はチェックされているか
これは、先述の「読まれること」にもつながりますが、誤字脱字のチェックは、自分でやるより他の人がやった方が捗ります。

自分で書いた文章は、無意識に流し読みするし、自分の癖や勉強不足で「正しい」と思い込んでいて間違いに気づかないことがあります。
つまり、誤字脱字チェックを「他のスタッフが行っているか」で精度が全く異なるブログになります。

会社単位で、しっかりと取り組んでいるか、姿勢が見えてきます。
SNS情報発信が豊富
スタッフブログの話をしているので、当然、自社HPの一部カテゴリをブログページにして更新していく場合が基本です。
ですが、大事なのは「SNS展開」も考慮して情報発信できているか、ということ。
ブログと連動させたいSNS
- インスタ
- 無料ブログと連動
- メルマガ
- LINE@
家づくりブログで一番助かるのが、「どんな家を建てているのか実際に見てわかる」ことです。言い換えれば、写真が豊富かどうか。

オープンハウスに行ければいいけど、最初は敷居が高く感じるし、営業かけられると面倒だし。
今は、写真はインスタを通して簡単にアップロードできるし、個人アカウントに直接訴求することができます。住宅会社のスタッフブログでインスタと連動していないのは、今の時代の広告のあり方を全く理解していないことになります。
無料ブログのアカウント
一昔前なら、無料ブログ全盛期で家づくりするときは「ブログ検索」したりして情報を集めていたところ。だから、あえてアメブロやYahoo!ブログにアカウント開設して上位記事目指したりする手法もありましたが、今は検索優位なので時代遅れです。
参考になるスタッフブログランキング
何でもかんでも「ランキング」にしたがる悪い癖があるのですが、とりあえず好きなスタッフブログをピックアップしておきます。
ディテールホーム
ディテールホームは当サイトでも取り上げており、「おしゃれな家を」「適正価格」で建ててくれるところです。
スタッフブログはシンプルな構造で、PCの画像幅で見ると少しサイズ感があっていますが、モバイルファーストにシフトしたんだと思います。

インスタの画像量が、いい
ディテールさんはおしゃれでクールな家づくりをしていることもあり、インスタに投稿される画像がいちいちカッコ良くて憎たらしいですね(笑)
家を建てないとしても、フォローだけでもしておきたい良アカウント。
https://www.detail-home.com/blog/
ユースフルハウス
ユースフルハウスは画像が大きく(未処理なだけかもしれないが)掲載されるので好きです。PCサイズだと少しくどくも感じますが、私は画像の質がいいに越したことはないと考えているので大変好感を持っています。
問合せが常時ブラウザ下部に表示されており、メニュー項目が構造化されておりわかりやすいのも好感が持てます。
http://yousefulhouse.com/blog/
オウルの家
サイト構造が10年ほど時を止めているような印象はあります。たぶんガラケーサイズの液晶で閲覧しているかのような長細いディスプレイに慣れている方が運営しているのでしょう。
ページトップボタンを常駐させるより、メニューボタンに変えてアクセス誘導した方が読者にはわかりやすそう。
馴染みやすい文体は好印象
更新頻度は高く、さらに馴染みやすい内容で「すでに顔見知りの顧客」であればとても楽しめそう。

アメブロあたりの家づくりブログの感じが好きな方にはお勧め!
ナレッジライフ

お金があれば、私が頼みたかったナレッジライフ。20年後にリフォーム依頼したい。
営業時間中はチャットにも対応し、現代風の読みやすいサイト構造になっています。スタッフブログは「世間話」を入れてからイベント誘導に入る細かな気配りがあり、別記事へのリンクも忘れずに配置する、スタッフブログとはこうあるべきという見本のようなブログです。
https://www.knowledge-pure.com/co_diary.html
オーガニックスタジオ
オーガさんは、「知識系」の記事投稿もあり、純粋に勉強になる良いブログです。ブログ導線として「メールマガジン」への出口も提案しており、会員になってもらってからじっくりオガスタの魅力を伝えられるいい事例。
https://www.organic-studio.jp/staff_blog/
清新ハウス
PCブラウザで見ると少しくどく感じるが、「SNSフォロー」から電話番号、資料請求など誘導すべきことは全て上部メニューバーに詰め込んだ、という例。
読者が「清新ハウスのイベント」を読みに来た方ならいいけど、家のメンテナンス情報など有意義な情報も配信しているのだから、タグにまとめて記事内にリンクを貼るなどすると導線ができそう。
https://www.seishinhouse.com/staff-blog
なんか、いつの間にか各ブログへのダメ出しみたいになってきたので、また別の機会に書き直します。
熊木建築事務所
私が愛してやまない熊木建築事務所のブログ。
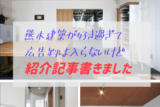
珍しく、更新が滞りがちなこの頃で少し心配していましたが、久しぶりの更新は土地の話題で実に専門的。知識系から、建築途中の工程を写した写真、丁寧な筆運びと、ブロガーの心をくすぐるコンテンツで読んでいて飽きません。
ハーバーハウス
ハーバーハウスは、なかなか「ブログ」というキーワードがとりづらい構成で仕掛けており勉強になります。
新人教育の一環
ハーバーハウスは、新人社員が専用ページで更新していくのが例年のお決まりとなっています。
別記事に分けましたが、新人がブログに取り組むことは大変有意義なことだと思います。読んでいるのは肉親や友人が中心かもしれませんが、自分が学んだことを「会社の看板」を背負ってアウトプットしている様子は、とても好印象です。
http://herbarhouse-blog07.com/
スタッフブログの書き方
スタッフブログの書き方についても書いていたのですが、流石に読みたい人は極々限られるだろうと思い、別記事にしました。





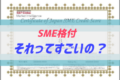

コメント
「上っ 収集 引き出し」に関する最新情報です。
長崎県佐世保市では、山の斜面に住宅が立ち並ぶ地域からのごみは「引き出し収集」によって回収されている。この方法では、ごみ収集車が入れないため、住民が斜面に設置された「ごみステーション」にごみを出し、それを清掃車が通れる道路まで引き出す必要がある。最近、佐世保市の清掃職員の協力を得て、この過酷な引き出し収集作業を体験した。この記事では、その体験を通じて佐世保市の引き出し収集の実態や、特殊な行政サービスの持続可能性について考察している。
https://toyokeizai.net/articles/-/872424?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「集客 web web 集客」に関する最新情報です。
新大陸(静岡県浜松市)は、工務店向けのWEB集客テクニックを8つのコンテンツにまとめた「WEB集客テクニック大全集」を無料で公開しています。このコンテンツは、650社以上の住宅会社の集客支援の実績を基にしており、イベント集客のアイデアやAIサービスの活用法、LINEを使った追客、GA4の分析手法などを紹介しています。知識がなくてもすぐに実践できる内容で、動画と資料が提供され、無制限に閲覧可能です。入手方法は、メールアドレスを入力するだけで、必要な情報が送られます。
https://www.s-housing.jp/archives/380405
「キシャメシ 読ま 2024」に関する最新情報です。
「キシャメシ2024年間ランキング」では、今年最も読まれた料理店が発表されました。1位には創業110年の「澤田そば屋」が選ばれ、続いて2位の「紫竹苑」や10位の「衆楽」なども多くの読者に支持されました。地域に根ざした長寿店が多くランクインしており、これらの店が持つ魅力が多くの人々に興味を引いたことが示されています。記事は156食の中から選ばれたベスト10を紹介し、読者への感謝の意も表明されています。
https://www.niikei.jp/1355571/
「スタジオ オープン house」に関する最新情報です。
長岡市にあるハウススタジオ『Sugar Photo House(シュガーフォトハウス)』が9月1日に移転オープンしました。このスタジオは、地域おこし協力隊のオーナー・佐藤さんが経営しており、家族の記念日や節目に写真を撮影するための場所です。新しい店舗は、ナチュラルテイストのアットホームな雰囲気で、一組ずつの個別対応が可能なため、小さなお子様連れのファミリーにも安心です。お宮参りや七五三、成人式など様々なシーンに対応し、ロケーション撮影や衣装レンタル、ヘアメイクのサービスも提供しています。また、オープン記念の撮影プランもあるので、ぜひ利用してみてください。住所は長岡市来迎寺甲2712番地1、電話番号は0258-40-9048です。
https://gatachira.com/local/115731/
「オウル オウル サンド オープン」に関する最新情報です。
新潟市中央区にある人気ベーカリー「OWL the bakery」が新たなブランド「オウルのサンド」を新潟伊勢丹にオープンする。この新ブランドはサンドイッチ専門店であり、6月28日にオープン予定。OWL the bakeryは手作りのパンやサンドイッチを提供し、自家製天然酵母のルヴァンを使用している。新店舗では様々な種類のサンドイッチが楽しめるとされており、注目されている。
https://gatachira.com/local/106688/
「ディスプレイ モバイル モバイル ディスプレイ」に関する最新情報です。
ASUS JAPANの「ZenScreen MB166CR」は、15.6型のモバイルディスプレイで、USB Type-C接続に特化しており、付属スタンドで横置き/縦置きに対応しています。背面がフラットで薄く、持ち運びや使い勝手が良い特徴があります。縦置きで使用したい場合にも適しています。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2406/14/news156.html
「看板 建築 看板 建築」に関する最新情報です。
築100年近いレトロな看板建築を巡る物語「看板ボーイズ」では、祖父が遺した建物が取り壊しの危機に瀕しているストーリーが描かれています。主人公たちは実在する看板建築を探し旅をする中で、建物の維持や保存の難しさに直面します。また、謎のチャラ男やミステリー要素も物語に絡んでおり、読者を引き込む要素も含まれています。建物の歴史的価値や保存に対する課題が描かれており、物語の展開に注目が集まります。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiR2h0dHBzOi8vYXJ0aWNsZS5hdW9uZS5qcC9kZXRhaWwvMS8yLzQvMzQ2XzRfcl8yMDI0MDMyNF8xNzExMjg4MjMzMTc2MTk00gEA?oc=5
「アーキテクト オープンハウス オープンハウス アーキテクト」に関する最新情報です。
オープンハウス・アーキテクトは、国産材の活用プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは、製材メーカーと協力して、日本の森林資源を活かし、国産材を使用した高級ブランドの杉材を開発することを目指しています。第一弾として、飫肥杉(おびすぎ)を使用した無垢カウンターの企画と開発が行われ、2023年12月12日から販売が開始されました。このプロジェクトは、持続可能な森林管理と地域の木材産業の振興を促進することを目的としています。
https://www.housenews.jp/house/25697
「教育 クラス クレタ」に関する最新情報です。
クレタクラスは、2023年のEDUtech Asiaにて革新的なAI早期教育解決案を展示することを発表しました。EDUtech Asiaはアジア最大の教育科学技術展であり、世界中の教育者や企業が集まるイベントです。クレタクラスのAI教育解決案は、人工知能を活用したインタラクティブな教育方法で、早期の子どもたちに効果的な学習体験を提供します。展示では、クレタクラスの専門知識と世界中の都市での実績が紹介されます。また、韓国の教育研究家である崔氏もクレタクラスの展示に参加し、AI技術とアニメーションコンテンツの融合による学習方法を紹介します。クレタクラスの展示は2日間にわたり行われ、子どもたちの学習に興味や自信を持たせ、長期的な学習習慣を築く役立つ解決案を提供します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000110977.html
「教育 クラス クレタ」に関する最新情報です。
クレタクラスは、EDUtech Asia 2023に出展し、革新的なAI早期教育解決案を展示しました。EDUtech Asiaはアジア最大級の教育イベントであり、教育者や企業が集まり、最新の教育科学技術の展示や講演が行われます。クレタクラスのAI教育解決案は、人工知能とインタラクティブな教育方法を組み合わせたもので、早期教育のトレンドに合わせた効果的な学習体験を提供します。クレタクラスは世界中で活動しており、500以上の都市で100万人以上の学習者にサービスを提供しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000110977.html
「18 ディスプレイ モバイル」に関する最新情報です。
「省エネで飢えしのぐ仕組み解明マウス寿命延ばす薬の効果にも関連?」という記事では、省エネルギーの仕組みについての研究が進んでいることが紹介されています。また、マウスの寿命を延ばす薬の効果にも関連している可能性があると述べられています。
「年内の衆院解散見送り、首相が意向固める支持率低迷おさまらない中」という記事では、日本の衆議院の解散が年内に見送られることが報じられています。首相は支持率の低迷が続く中で解散を見送る意向を固めているとされています。
「ライターの火を吹き消したあの日ハマスの人質になった「婚約者」」という記事では、ハマスによって人質にされたライターの婚約者の話が紹介されています。彼女はハマスによって火を吹き消す役割を強制され、困難な状況に置かれたことが明かされています。
「所得減税の期間「当然1年に」自民・宮沢税調会長、延長論を一蹴」という記事では、自民党の宮沢税調会長が所得減税の期間を1年にするべきだと主張し、延長論を一蹴していることが報じられています。
「憲法から考えるジャニーズ問題企業の
http://www.asahi.com/articles/ASRC74J71RC7PLBJ001.html?ref=rss
「18 ディスプレイ モバイル」に関する最新情報です。
アイティプロテックのモバイルディスプレイ「LCD18HCR-IPS」は、18.5型の大画面サイズであり、デスクトップ用スタンドも付属しています。また、VGA接続にも対応しています。このモバイルディスプレイの使い勝手を試してみた結果、圧倒的な内容の付属品や特徴に注目しました。このディスプレイは、1920×1080ピクセルの高解像度を持ち、持ち運びに便利なカバー付きの一体型デザインです。また、スタンドを使ってデスクトップに設置することも可能です。さらに、90度回転するスチール製のスタンドも付属しており、自由な角度でディスプレイを使うことができます。このモバイルディスプレイは、モバイルやデスクトップの両方で使える便利なアイテムです。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2311/08/news096.html
「マルシェ 少年 教育」に関する最新情報です。
新潟県長岡市にある新潟少年学院が、矯正教育の一環として「御山のマルシェ」を開催しました。このマルシェは、学院の取り組みを広く知ってもらうために行われたもので、地域の人々に手作りの商品や農産物を販売する場となりました。新潟少年学院は、18歳から20歳までの35人の少年たちを収容し、心身の育成や社会性の向上を図る矯正教育を行っています。
https://www.niikei.jp/869522/
「21 21 液晶 ディスプレイ」に関する最新情報です。
アイ・オー・データ機器は、USB Type-C接続に対応した21.5型液晶ディスプレイ2製品を発表しました。これらのディスプレイは、1920×1080ピクセルのADSパネルを採用しており、エンハンストカラー機能により映像の解像度を高めることができます。また、リフレッシュレート100Hzの機能も搭載されており、スタンドも付属しています。これらの製品は11月中旬に出荷が開始され、価格は2万3980円から2万7280円(税込み)と予想されています。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2310/25/news126.html
「新潟 21 21 yahoo」に関する最新情報です。
新潟市で開催される「蒲原まつり」が4年ぶりに再開されることが発表されました。この祭りは新潟市で行われる三大高市の一つであり、800年以上の歴史を持つ祭りです。約1kmにわたって約450の露店が並び、大勢の人々で賑わいます。過去3年間は中止となっていましたが、新型コロナウイルスの感染防止対策をしながら再開することが決定しました。7月2日までの3日間開催され、子供から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんです。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSmh0dHBzOi8vbmV3cy55YWhvby5jby5qcC9hcnRpY2xlcy81MjUyMGFmMzhmZDU1MWM5NmI1ZjVjZWY3MTI0ZWE1OWRmOWZmZTg10gEA?oc=5
「新潟 21 21 yahoo」に関する最新情報です。
J1アルビダイニチ工業が新たにパートナー契約を締結し、環境や体調管理のサポートも行うことを発表しました。このニュースはUX新潟テレビ21とYahoo!ニュースで報じられています。J1アルビダイニチ工業は、サッカーチームアルビレックス新潟のスポンサーであり、新潟市を本拠地としています。パートナー契約により、ダイニチ工業はアルビレックス新潟の選手やサポーターに対して、環境や体調管理に関するサポートを提供します。具体的には、空気清浄機の設置や暖房器具の提供などが行われる予定です。アルビレックス新潟のゴールキーパーである小島亨介選手も、このパートナーシップについて感謝の気持ちを述べています。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiSmh0dHBzOi8vbmV3cy55YWhvby5jby5qcC9hcnRpY2xlcy9jYzlmNjMxNjUxOWNkOTAxYzY1YWNjOWUzMzIxNjIyMjVhYTdkMzM40gEA?oc=5