玄関土間と、玄関周囲の床材について解説していきます。

玄関のデザインなんて、まだまだ考えられないよー、、、なんて思っているうちに、一回の打ち合わせである程度まで決めないといけなくなって大変だったね。
そんな私たちのような「情報収集は面倒、でも玄関土間で失敗したくない」という方のための情報を取りまとめております。
玄関土間について知っておきたいこと
まず、玄関土間について簡単に説明します。
玄関土間とは
まず、土間について簡単に説明すると、「地面と同レベル(段差がない)の屋内部分」を指します。

地面とつながっている作りになっている部分ですね。
日本の文化的には、この土間部分は「土足」であることが多いです。

玄関土間は、玄関における「土足部分」のことだと考えるとスッキリしますね。靴を脱ぐ場所、とも言い換えられます。
家づくりで大事になる、土間周辺のこと
これから割と細かく解説していきますが、玄関周りだと何を決めるのかをリストアップしておきます。
- 上がり框(玄関框)
- 付け框
- 郵便受け・宅配ボックス
- 玄関ドア
- 玄関用のライト(内・外)
このページでは、玄関土間として「玄関の床材には何を選べばいいのか」という情報についてまとめています。
土間に求められる特徴
まず、土間は「土足」で歩くために、屋内でありながら「それなりの耐久性」が必要になります。

土や小石のついた靴で歩くため、思った以上にも傷みやすいのですね。
また、雨にも濡れやすいため、水に対しても強い材質であることが求められます。
土間の床材となりうるもの
- コンクリート
- モルタル
- 土
- タイル
モルタル風タイルもある
モルタルの雰囲気だけなら、モルタル風の大判タイルである程度までは再現可能です。どうしてもモルタルという素材が好きだ、ということでないのなら、タイルの方が管理も「将来変更する」のも比較的簡単です。
タイルの種類は思った以上に多い
私のブログはローコストなので、モルタルを「コストが安いから」という理由で採用される以外には、ほとんどの場合ではベーシックなタイルを使用することになると思います。
タイルはさらに、材質によって以下の通りに分類できます。
磁器質
磁器質は高温で焼いたタイルです。非常に硬く、耐凍害性や耐摩耗性にも優れていることから外壁にも床用にも使用されることがあります。
せっき質
せっき質は磁器質よりほんの少し低いくらいの、1200℃程度で焼かれたタイルです。温度が低い分、磁器質よりもわずかに吸水性が生まれます。
陶器質
陶器質は、その名の通り陶器に使われるような土などを1000℃程度で焼いたタイルで、吸水性が高くなります。

吸水性が高くなると、水回りでは「凍結による劣化」や「カビ」などの原因となる可能性もあるので、採用する場所には注意したいところです。
土器質
土器質はレンガですね。
床材はどうやって決める?

我が家で「土間」をどうやって決めたか、参考になった情報などを取り纏めていきます。

玄関は思ったような床材が見つからなくて、コストをかけようと思った矢先に、普通にリクシルに表情のいいタイルがあって即採用、となった次第です。
素材の特性を知る
まずは、玄関土間の外装材として採用すべき項目を学んでいきます。
玄関はスリップ注意
私は看護師ということもあって、デザインよりも「安全」を優先させたいところがありまして、特に転倒に関しては甘くみない方がいいと思います。

人は思った以上に転ぶし、転ばないと思って転んでいると、パキンと簡単に骨が折れてしまうからね。
玄関は、階段というだけで転倒リスクが高い上に転んだ時の衝撃も強いので要注意です。耐久性の問題もあるので、柔らかい素材にする必要はないとは思いますが、転倒予防のためにある程度の凹凸で滑り止め作用のある素材を採用するのもありですね。
蓄熱性
玄関まで床暖房を張れる家は、おそらくこのブログは読んでいないと思いますが、例えば広めの土間を用意した場合、床暖房を入れると、蓄熱性が高いコンクリートやタイルの場合は熱効率が良く、体感としても温かい家だと感じられます。
クラック・メンテナンス方法
タイルのメンテナンスが簡単だというのは、「既に完成している耐久性の高い素材」を、「クラックにも配慮して目地を開けて貼る」からです。

タイル一枚だけ張り替える、ということもいざとなれば可能なので、長い目で見た管理としてもありです(同じタイルが見つからないので、結局総張り替えしますが、精神衛生上はありがたい)
素材の味わい・色合いを知る
玄関で使用されるタイル関連は、色合いも風合いも様々です。

前庭の印象と、玄関とのつながりを考えてタイルの色味を決めていくのがいいとは思いますが、出来上がっていないもので想像して考えるのはなかなか大変なことです。

見本は見せてもらえるけれど、実寸に変わると「思った以上に重たそう」とか、印象変わるしね。
汚れが目立つかどうか
車を買うときなんかも、「これ、汚れが目立つカラーだな」というのは気にする面倒臭がりなのですが、玄関タイルも要注意です。

ある程度、傷やクラックが入るのは仕方がないことですが、「白っぽいタイルにしたら、結局土汚れが目立つだけだった」ということはありがち。

水捌けの良さも大事ですし、掃除のしやすさなんかも考えておいた方が良さそうですね。目地が多いと擦るの大変だし。
サイズを知る
玄関タイルの場合は、タイルにサイズが依存します。基本的には30cm×30cmか、15cm×15cmですが、大判で30×60cmのものを組み替えて並べたり、45cm四方などもあります。

問題なのが、大判にするほど、玄関やアプローチのサイズを考えないといけないところだね。

もちろん、タイルなのでいくらでもサイズ調整して割ることはできますが、見栄えは悪くなります。少なくとも、私はスッキリしないなと感じます。
住人がそれでよければ問題ないと思いますが、仮に間取りを検討している最中であれば、自分の使用したいタイルの寸法をちゃんと調整できるのかどうかは確認しておきたいところです。
玄関と土間の関係を探る
ここからは、土間についての話題になります。
土間の役割
現代の日本家屋としては「靴を発揮変える場所」としての役割くらいしかありませんが、土間の価値が見直されていると書いているサイトもあるくらいです。

せっかくなら広めの土間を作って「土間にしかできないこと」を見つけてみるのもいいかもしれません。
屋内ガレージ、作業場
日本の農家なんかでは、雨天に農作業ができないときは、農具の調整などしていました。そのため、割合広めの土間があったりすることも珍しくありませんでした。
現代風に置き換えれば、ガレージが似たような役割かと思います。
家の中で屋外作業ができる
土間は、外部と交通している構造である場合が多く、気密面が少し心配ではありますが、家の中の暖かさで、好きな車やバイク、自転車なんかの整備をするのは、趣味としている人にとっては至福の空間となることでしょう。
重さのある荷物なんかは、屋内に置いておくよりも、耐久性の高い土間なんかに設置しておく方が家の耐久にとっては良さそうです。また、汚れの落ちにくい油汚れなども擦り落とせますし、匂いの気になる灯油なんかも土間収納が活躍しそうです。
外飼いの動物の飼育スペース
土間は、例えば屋外犬などが生活するスペースとして割り当ててもいいかもしれません。
牛舎のようなイメージとなりそうですが、最初から飼育スペースと考えて、水栓シャワーやトイレ、大量の餌なんかを保管しておく収納などを取り付けると利便性は大きく向上します。
外部とは遮断された空間になるので、物騒な事件から飼い犬を守ることはできます。
f例えば、土間に関しては掃除のしやすいタイルを使用したり、ペットの歩きやすいシートなどを使用して適宜交換する、なんて方法もあるかもしれません。土間というスペースは、割と便利な空間のような気がしてきました。
憩いの場、来客スペース
来客スペースとしても土間は便利です。
心理的に準プライヴェート空間のような場所に
外部からどれくらい露出させる土間にするかによりますが、近所の寄り合い会場になりやすいのであれば、土間を充実させることでみんなが来やすい場所にすることも可能です。

何せ、「靴は履いたまま上がれる屋内」ですから、ちょっと話にきた近所のおばさんなんかを通して、さっとお茶なんかを出せればもう立派な応接間となります。

靴を脱がなくていい、というのは気楽な感じがあるのとシンプルに面倒がなくていい。加えて、迎える側としても、家の中までは入ってもらうことがないので心理的な負担軽減となりそうです。
囲炉裏、キッチン
囲炉裏は土間とはまた違ったものではありますが、日本の家屋では、土間に調理スペースが置かれていたことも珍しくありません。

屋内では燃えやすい木材を使用していますが、土間は土と石が中心ですから、火も使いやすく、水回りとしても適性が高かったわけですね。
配管問題はある
土間は、前述の通り、基本的には地面と同じ高さ・レベルで作られます。水回り設備を設置する際には、配管処理の難易度が少々あがります。
配管は、基本的には傾斜を利用して排水するように作られるので、土間のような床下のない・薄い構造だと、しっかりと排水できるような傾斜が作れない(かもしれない)という問題があります。

ただ、できないこともないだろうから、経験の多い建築家などに相談してみるのが一番ですね。建築家への相談などは、auiewoなどのサイトが便利です。

土間に必要なスペースと配置
まず、前項で散々書き連ねた通り、土間の活用方法は様々です。言ってしまえばフリースペースなので「割り当てるスペース」は、使用目的と「居住空間」との兼ね合いになります。
必要な居住空間を削るなら、土間はいらない?
ガレージとしての使用法であれば、車庫以上のスペースを必要としますが、基本的には土間は土間。特に私のようなローコストで家を建てたい層にとっては、「不要なスペース」にも思えてしまいます。
使用頻度の少ない部屋ならあえて土間を割り当てる
例えば、使わない客間に間取りを取られるくらいなら、外からの流れで土間をあえて広くとることで、部屋を細かく作るよりも開放的な空間を作ることができます。

キッチンなども全てつなげて土間にし、ダイニング(食事を取る空間)までを1階スペースに集約し、2階部分に屋内としての機能を集約させるのも面白いかもしれません。
コスト的には、1階部分は柱と土間(モルタルなど)が中心となるので建材としてはローコストと言えそうですが、設計から力を入れないといけないので、むしろ高くつく可能性もありますね。

配管なども、床下を通さないことを考えないといけないので、メンテナンスしやすいようでいて、案外大変なのかも。
庭や外部との繋がりを遮らずに広げる
これは、土間云々とは話が逸れてしまうかもしれませんが、例えば、リビング周りから土間と中庭を繋ぐように配置することで、私のような狭小リビングでも外部との遮蔽物を減らすことで「実際よりも広く」見せることは可能かもしれません。

リビング、土間、庭をあえて区切らないように、開放したような構図になると羨ましいですね。

でも、ドアだけで気密性・断熱効果を撮ろうとすると、結構大変なんだよね。

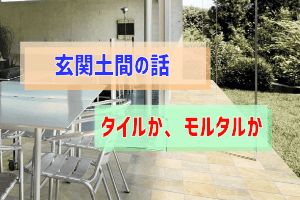



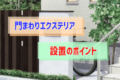
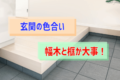
コメント
「火災 作業場 消火」に関する最新情報です。
新潟県魚沼市の住居兼作業場で、薪ストーブを完全に消火せずに就寝したことが原因で火災が発生しました。3月24日夜、家族が消防に通報し、火は廃材やごみに引火して天井の一部が焼損しました。消火活動中に煙を吸った40代の男性が病院に搬送されましたが、命に別状はないとのことです。
https://www.niikei.jp/1501479/
「カンガルー 飼育 撮影」に関する最新情報です。
神奈川県横浜市の金沢動物園で、カンガルーと飼育員が手をつなぐ瞬間が撮影され、話題になっています。撮影者のおーあさんは、飼育員がカンガルーの解説をしている際に、偶然手を重ねた瞬間を捉えました。この写真は16万以上の「いいね」を集め、「可愛い」とのコメントが寄せられています。金沢動物園の担当者によると、カンガルーの名前はイチゴパンで、展示方法は来園者との距離が近いウォークスルー形式を採用しています。今回のショットは、飼育員が給餌中にカンガルーが近づき、手を差し出した際に偶然撮影されたもので、非常に珍しい瞬間だとされています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6732f8aee4b07ebab74230ca
「ヒヨコ ヒヨコ 育て ヒヨコ 飼育」に関する最新情報です。
このウェブサイトでは、住宅街の自宅の庭で家族がヒヨコを育てる生活について紹介されています。飼育を始めるにあたり、近所迷惑や鳥インフルエンザのリスクなどの心配が浮かぶものの、家族の一員である文祥は「飼えなかったら俺が責任を取る」と言い、ヒヨコを育てることに前向きな姿勢を示しています。時にはヒヨコを「丸焼き」にすることも考慮されており、複雑な感情が交錯しています。
https://toyokeizai.net/articles/-/828722?utm_source=rss&utm_medium=http&utm_campaign=link_back
「火災 続報 作業場」に関する最新情報です。
新潟県新発田市で9月10日、有限会社山口製材所の作業場で火災が発生しました。火は同日夕方に近隣住民からの通報を受けて消防が出動し、約4時間後に鎮火しました。この火災により、火元の作業場を含む計9棟が焼損し、具体的には3棟が全焼、1棟が部分焼、4棟がボヤの被害を受けました。幸いにも負傷者は報告されていません。出火原因については現在捜査中です。
https://www.niikei.jp/1185128/
「火災 続報 作業場」に関する最新情報です。
新潟県新発田市で9月10日夕方、有限会社山口製材所の作業場で火災が発生しました。火災は同日21時48分に鎮火されましたが、火元の作業場を含む計9棟が焼損しました。具体的には、3棟が全焼、1棟が部分焼、4棟がボヤの状態です。幸いにも負傷者は報告されていません。出火原因については現在捜査中です。
https://www.niikei.jp/1185128/
「動物 理科室 伊勢」に関する最新情報です。
新潟市中央区で開催された2日限りの喫茶店「喫茶理科室」は、フリーアナウンサー伊勢みずほ氏とデザイン制作会社ファジカがタッグを組んで動物の幸せや地球の環境に配慮したコンセプトを持つ喫茶店でした。伊勢氏のアニマルウェルフェアへの想いや環境配慮の考え方を広めるために開催され、訪れた人々はそのコンセプトに共感し、喫茶店の提供する飲食物を楽しんだり、意識を高めるきっかけとなったと述べています。今後も不定期での開催を続け、さらにアニマルウェルフェアや環境配慮に関する活動を展開していく予定です。
https://www.niikei.jp/1050814/
「火災 続報 作業場」に関する最新情報です。
新潟市東区の建築会社の作業場兼倉庫が火災で全焼し、怪我人は確認されていない。火災は4月5日夜に発生し、消防によって6日2時28分に鎮火された。火災原因などは引き続き捜査中。【続報】
https://www.niikei.jp/1014356/
「建物 能登 憩い」に関する最新情報です。
石川県七尾市のカフェICOUは、能登半島地震で被災し、建物が大きな被害を受けた。再建のためにクラウドファンディングを行い、目標金額は1000万円。被災者として再建に向けて頑張る姿勢が伝わり、支援者からの励ましを受けながら再建を目指している。ICOUの建物復旧を通じて、憩いの時間と空間を提供することを目指している。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLWh0dHBzOi8vcmVhZHlmb3IuanAvcHJvamVjdHMvaWNvdV9uYW5hbzEzODQyMtIBAA?oc=5
「建物 能登 憩い」に関する最新情報です。
石川県七尾市のカフェICOUが、能登半島地震で被災し、建物の再建を目指すクラウドファンディングを行っている。建物は11年前に創業し、被災後は倒壊寸前の状態となり、再建には多くの支援が必要となっている。ICOUは再建後に感謝のイベントを計画し、日々の営業で憩いの時間と空間を提供したいとして、目標金額は1000万円としている。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLWh0dHBzOi8vcmVhZHlmb3IuanAvcHJvamVjdHMvaWNvdV9uYW5hbzEzODQyMtIBAA?oc=5
「建物 能登 憩い」に関する最新情報です。
石川県七尾市のカフェICOUは、能登半島地震で被災し、建物が大きな被害を受けた。再建のためにクラウドファンディングを行い、支援者14人から目標金額の10,000,000円を集めている。被災者の苦境を乗り越え、再建を目指すICOUは、復旧後に感謝のイベントを計画し、憩いの時間と空間を提供することを目指している。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLWh0dHBzOi8vcmVhZHlmb3IuanAvcHJvamVjdHMvaWNvdV9uYW5hbzEzODQyMtIBAA?oc=5
「動物 センター 愛護」に関する最新情報です。
新潟県長岡市の動物愛護センターで開催された「猫の日」のイベントについて報告されています。参加者は動物愛護に関心を持ち、センターの役割や動物保護の重要性について学びました。センターは犬猫の引き取りや保護、普及啓発活動などを行っており、地域の協力が必要と強調されました。参加者からは殺処分の問題への関心も示され、センターへの協力呼びかけが行われました。
https://www.niikei.jp/969656/
「動物 センター 愛護」に関する最新情報です。
新潟県長岡市の動物愛護センターで開催された「猫の日」イベントには市民が参加し、センターの役割や動物保護の重要性について学んだ。センターの業務や取り組み、地域の課題である多頭崩壊の防止方法などが紹介され、参加者からも関心が高かった。特に子供や動物愛護に興味を持つ人々が多く、愛護センターへの理解が深まったと報告されている。
https://www.niikei.jp/969656/
「モルタル 風合い 着色」に関する最新情報です。
埼玉県川口市が、モルタル・コンクリート床の風合いを生かしつつ、水性コンクリートステイン塗料「ルーセントカラー」を発売。この塗料はカラークリアで着色し、浸透強化・防塵が可能であり、下地のクラックや汚れ、色の濃淡を生かすことができる。左官仕上げと比較してコストが約1/10で手軽に施工できるという。
https://www.s-housing.jp/archives/340774
「ライト 建築家 文化」に関する最新情報です。
日本と米国で活躍した2人の建築家の個展が開催されており、彼らの業績とともにモダニズムの幅広さも再確認できる。また、日本で最も親しまれている外国人建築家の回顧展も開催されており、その建築家の知られざる一面を紹介している。
http://www.asahi.com/articles/ASS2B66TQS28ULZU002.html?ref=rss
「トイレ 汚れ キッチン」に関する最新情報です。
このウェブサイトでは、トイレや風呂の汚れを防ぐためのコツやキッチンの油汚れを簡単に落とす方法について紹介しています。トイレの予防掃除のポイントや即席の掃除シートの作り方、風呂の汚れの予防やカビの原因などが紹介されています。また、キッチンでは食器洗いやコンロの掃除の方法が紹介されています。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_65a87951e4b00bbb446dd3e6
「木造 三菱地所 探る」に関する最新情報です。
三菱地所が木造・木質の価値を探る取り組みに挑戦していることが分析データから明らかになった。三菱地所は大手デベロッパーであり、木造建築に取り組むことで、木質の魅力を最大限に引き出すことを目指している。具体的な取り組みとして、仙台市の泉パークタウンや都内、札幌市内での木造建築物の開発が挙げられる。また、三菱地所は直交集成CLT(クロス・ラミネート・ティンバー)の活用にも注力しており、中大規模の木造建築物の建設にも積極的に取り組んでいる。これらの取り組みは、木造建築の設計や施工の育成・推進、実務者向けの情報発信などを通じて行われている。三菱地所の取り組みは、木造・木質の価値を探り、その可能性を追求するものと言える。
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8veHRlY2gubmlra2VpLmNvbS9hdGNsL254dC9jb2x1bW4vMTgvMDA0NjEvMTExNTAwMDc0L9IBAA?oc=5
「飼育 動物 ひだまり」に関する最新情報です。
新潟県上越市にある動物愛護団体の一般社団法人あにまるシェルターひだまりは、行き場のなくなった犬猫を保護・飼育しています。この団体は岡田紀音さんが代表を務め、犬や猫約70匹を飼育しています。岡田さんは動物の愛護活動に取り組んでおり、病気や飼育放棄などの問題に対応し、命を救うために尽力しています。シェルターの運営には多額の費用がかかるため、活動資金の支援も必要です。
https://www.niikei.jp/853240/